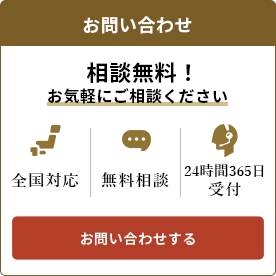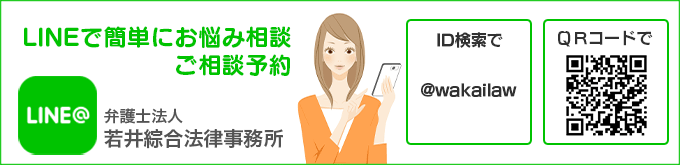婚約破棄(こんやくはき)とは、すでに婚約が成立しているにもかかわらず、一方的に婚約を取りやめることをいいます。
これは、当事者双方の合意によって婚約を解消する「婚約解消」とは異なります。
一方的に婚約を破棄されたことで精神的な苦痛を受けた場合、相手に慰謝料を請求したいと考えるのは自然なことです。
しかし、慰謝料が認められるためには、「婚約破棄に正当な理由がないこと」が必要です。
逆に、相手に正当な理由がある場合には、慰謝料請求が認められない可能性があります。
つまり、不当な理由による婚約破棄をされた場合には慰謝料請求が可能ですが、正当な理由がある場合には慰謝料請求はできません。
本記事では、婚約破棄に強い弁護士が、
- 婚約破棄の正当な理由・不当な理由
- 正当な理由がある場合・ない場合の違い
- 慰謝料以外に請求できる損害賠償
といった点について、わかりやすく解説します。
婚約破棄された方も、あるいは婚約破棄を考えている方も、本記事を最後までお読みいただき、もしも解決できないお悩みがある場合には、お気軽に弁護士にご相談ください。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|
目次
婚約破棄とは
そもそも婚約とは?
婚約とは、将来婚姻することを約束することです。法的には、将来夫婦になることに合意する契約といえます。
婚約は口約束でも成立しますが、口約束で婚約成立?婚約破棄で慰謝料請求できる?でも書かれているように、日常会話の中で交わされる「ずっと一緒にいようね」「早く結婚したいね」といった台詞は、リップサービスや一時の感情の盛り上がりから発せられることも多いです。
婚約が成立していたと言えるための条件は?
そのため、婚約破棄の段階で、「言った言わない」「本心で言った言ってない」といった揉め事になりがちです。そこで、以下で挙げるような客観的な事実があった方が、婚約が成立していたと認められやすいでしょう。
- 結納を取り交わしていた
- 互いの両親が結婚を前提とした挨拶をしている
- 結婚式場の下見や予約をしていた
- 婚約指輪や結婚指輪を購入していた
- 婚約者として親や友人、勤務先に紹介していた
もっとも、婚約破棄でトラブルになった場合に、上記事実があったことを相手が認めないケースもあります。その場合、婚約が成立していたことを客観的な証拠により証明しなければなりません。たとえば、以下で挙げるようなものが婚約成立の重要な証拠となり得ます。
- 結婚式の申込書、予約票、内金を払込みした際の領収書
- 婚約指輪、あるいは婚約指輪を購入したことを裏付ける資料
- 結納品、あるいは結納品を購入したことを裏付ける資料
また、結婚の約束を取り交わす内容のメール・LINE等のSNSのやり取り、通話を録音した音声なども婚約の証拠となり得ます。
婚約破棄とは?どんな法的責任を負う?
婚約破棄とは、婚約が成立しているのに、一方的にその婚約を取りやめることです。
婚約破棄は、いつでも自由に行うことができます。婚約は契約の一種とはいえ、結婚はお互いの婚姻意思が合致して初めて成り立つものですので、一方が途中で結婚する気が失せたとしてもそれを強制することはできないからです。
もっとも、一方的に婚約破棄をされた人は、心に大きな傷を残すことになり精神的損害が生じます。
そのため、婚約が成立しているにもかかわらず、正当な理由なく婚約破棄された側は、婚姻の予約(婚約)という契約の債務不履行責任(民法第415条)、または、結婚についての期待権の侵害として不法行為責任(民法第709条)に基づき、婚約破棄した側に、慰謝料を請求することができます。
婚約破棄の正当な理由とは
上記から分かるように、婚約破棄で慰謝料請求が認められるには、婚約が成立しており、かつ婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。
つまり、たとえ婚約が成立していたとしても、婚約破棄した側に正当な理由があれば、破棄された側は慰謝料を請求できません。
婚約破棄に正当な理由があるかどうかは、一律の基準で判断されるものではなく、裁判所が個別具体的な事情を考慮して判断します。
たとえば、交際期間の長さ、性的関係や同棲の有無、婚約破棄に至るまでの双方の行動などを踏まえて、婚約破棄が社会通念上やむを得ない事情に基づくかを総合的に判断します。
そのため、明確な基準は存在しませんが、以下に挙げるようなケースでは、婚約破棄の正当な理由があると認められやすいとされています。
- ① 相手の不貞行為・既婚者であることを隠していた場合
- ② 相手からの暴力や虐待を受けた場合
- ③ 結婚直前に相手が失踪した場合
- ④ 相手に重大な性的問題がある・肉体関係を強要された場合
- ⑤ 相手が回復困難な精神疾患を患った・重い障害を負った場合
- ⑥ 無断で結婚の段取りを決めたり、内容を変更したりする場合
- ⑦ 社会的常識を著しく逸脱した言動がある場合
- ⑧ 多額の借金を隠していた場合
- ⑨ 生活が困難なほどの貧困状態である・経済状況が著しく悪化した場合
① 相手の不貞行為・既婚者であることを隠していた場合
婚約者が他の異性と性的関係を持った場合、それは不貞行為に該当します。
婚姻に対する合理的な期待や、婚約者として保護されるべき権利・利益が侵害されるため、婚約破棄の正当な理由と認められます。
また、相手が実は既婚者であり、その事実を隠して肉体関係を持っていた場合も、重大な背信行為とされ、正当な理由になります。
② 相手からの暴力や虐待を受けた場合
婚約者から身体的な暴力(DV)や精神的虐待(モラハラ)を受けた場合、夫婦としての共同生活は著しく困難と判断され、正当な理由になります。
録音データ、診断書、LINEのやり取りなど客観的な証拠が重要です。
③ 結婚直前に相手が失踪した場合
結婚式直前で婚約者が突然失踪し行方不明になった場合、結婚の目的が達成不可能になるため、婚約破棄の正当な理由となります。
この場合、婚約を破棄した側に慰謝料を支払う義務はありません。
④ 相手に重大な性的問題がある・肉体関係を強要された場合
相手に性的不能や異常な性癖があると判明した場合、夫婦生活を円満に営むことが難しいと判断され、正当な理由になります。
また、肉体関係を一方的に強要された場合も、信頼関係の破綻を理由に婚約破棄が正当と認められる可能性があります。
⑤ 相手が回復困難な精神疾患を患った・重い障害を負った場合
婚約後に重度の精神疾患を発症し、回復の見込みがない場合や、事故・病気により重い障害を負った場合、結婚生活の維持が困難と認められれば、正当な理由となり得ます。
ただし、症状の程度や回復の見込みなど、個別事情が重視されます。
⑥ 無断で結婚の段取りを決めたり、内容を変更したりする場合
式場の決定、新居の場所、両親との同居など、重要事項は双方の合意が必要です。
一方的な決定や変更があると、信頼関係が損なわれ、正当な婚約破棄理由となる可能性があります。
⑦ 社会的常識を著しく逸脱した言動がある場合
繰り返される犯罪行為や著しい不潔さ、暴言・侮辱などは、健全な結婚生活を阻害する要因です。
改善の見込みがない場合、婚約破棄は正当とされる可能性があります。
⑧ 多額の借金を隠していた場合
借金の存在を隠していたことが発覚した場合、結婚後の生活設計に重大な影響を及ぼすため、婚約破棄の正当な理由とされます。
特に、借金の額が大きく、理由や使途にも不審な点がある場合は、その可能性が高まります。
⑨ 生活が困難なほどの貧困状態である・経済状況が著しく悪化した場合
婚約後に相手やその家族の経済状況が大きく悪化し、将来にわたって安定した生活が困難と判断される場合、婚約破棄の正当な理由になります。
一時的な困窮ではなく、長期的な見通しに基づいて判断されます。
婚約破棄に「正当な理由がある」と判断された裁判例
上記の通り、婚約破棄が法的に許容されるかどうかは、「正当な理由」があるか否かによって大きく左右されます。
実際の裁判例を通じて、どのような事情が正当な理由と評価されるかを知ることで、自身のケースに照らした判断の参考になります。
以下では、裁判所が婚約破棄に正当な理由があると認めた代表的な判例をご紹介します。
- ① 詐称によって婚姻意思を誤らせたケース
- ② 性的不能により婚約を解消したケース
- ③ 結婚式当日の非常識な言動
① 詐称によって婚姻意思を誤らせたケース
この事例では、女性が自身の年齢や出自について虚偽の事実を告げ、男性に誤信させた結果、婚姻意思を形成させたとして、男性が詐欺による婚姻の取消しと1,000万円の慰謝料を求めました。
裁判所は、実際は52歳の女性を24歳であると誤信していたことについて、「婚姻意思に重大な錯誤があったというべきである」として、正当な理由を認めました。
ただし、婚姻自体が両者の愛情に基づくものであった点が考慮され、慰謝料については一部の50万円のみが認められました(東京高等裁判所 平成18年11月21日判決)。
婚約は、将来の結婚を前提とした信頼関係の上に成り立つものです。そのため、婚姻の根幹に関わる重要事項について虚偽の説明があった場合には、相手方の意思形成を著しく歪めたものとして、婚約破棄が認められる可能性があります。
特に年齢や既婚歴、子どもの有無といった重要な事実についての詐称は、信頼関係を根本から損なう行為とされ、「信義則に反する行為」として婚約破棄の正当性が認められやすくなります。
② 性的不能により婚約を解消したケース
この裁判例では、女性からの婚約解消が争点となりました。男性に正常な性交渉ができない肉体的欠陥があったという事実が認定され、本件婚約の解消には正当な事由があったとされました。
裁判所は、「女性と正常な性交をすることができない肉体的欠陥があったものというべきであるから、…本件婚約を解消するにつき正当な事由があった」と判断し、損害賠償義務はないと結論づけました(高松高等裁判所 昭和46年9月22日判決)。
夫婦間の性生活は、結婚生活を営むうえで重要な構成要素とされます。
一時的な性的不一致では足りず、性交不能のような継続的・本質的な障害がある場合には、婚約破棄が正当と判断される可能性が高まります。
③ 結婚式当日の非常識な言動
この事例では、結婚式当日や新婚初夜において、新郎が社会常識を大きく逸脱した異様な言動を見せたことで、新婦がその場で結婚生活を継続する意思を失い、婚約を破棄したものです。
裁判所は、「新郎としてわきまえるべき社会常識を相当程度逸脱した原告の異様な言動」が直接の原因であり、それによって「新婦のそれまでの印象を一変させ、今後結婚生活を共にする決意を全く失わせた」として、婚約破棄には正当な理由があると認定しました(福岡地方裁判所小倉支部 昭和48年2月26日判決)。
婚姻は法的契約であると同時に、社会的・人間的な信頼の上に成り立つものです。
結婚式という人生の節目において常識を逸脱した行動があれば、婚約破棄の正当性が認められる余地は十分にあります。
正当な理由にならない婚約破棄の典型例
婚約破棄には「正当な理由」が必要であり、これが認められない場合には慰謝料請求の対象となることがあります。
以下では、裁判でも正当な理由と認められなかった典型的な婚約破棄の例をご紹介します。
- ① 性格の不一致
- ② 親と合わない
- ③ 婚約破棄をする側の浮気・不倫
- ④ 単なる心変わり
- ⑤ 信仰の不一致
- ⑥ 相手の親族の非行・犯罪歴
- ⑦ 差別的な理由
① 性格の不一致
「性格の不一致」は、婚約破棄の理由としてよく挙げられますが、多くの場合、正当な理由とは認められません。
なぜなら、性格の不一致は結婚生活において多少なりとも生じるものであり、それだけを理由に婚約を解消するのは、相手に対する誠実さを欠くと判断されるためです。
もっとも、性格の不一致が原因で相手から精神的・肉体的なDVを受けていたような場合には、婚姻関係の継続が著しく困難と認められ、正当な理由とされる可能性もあります。
② 親と合わない
「親と合わない」という理由も、婚約破棄の正当な理由とは認められにくいとされています。
たしかに、結婚は当人同士だけでなく相手の親族との関係も重要になりますが、法的には当事者の同意のみで婚姻は成立するため、親の反対を理由に婚約を解消することは合理性に欠けると判断されがちです。
ただし、相手の親から継続的に侮辱や人格否定を受けているといった場合には、社会通念上の限度を超えるとして正当な理由と認められる可能性もあります。
③ 婚約破棄をする側の浮気・不倫
自らの浮気や不倫を理由とする婚約破棄は、正当な理由にはあたりません。
婚約は、将来の結婚を約束する法的拘束力のある契約であり、当事者間には誠実な交際を継続する義務が生じます。
したがって、婚約後に他の異性と性的関係を持つ行為は、婚約者に対する重大な裏切りであり、不貞行為と同様に扱われます。
このような不貞行為をした当人が婚約破棄を申し出る場合、当然ながらその理由は正当と認められず、慰謝料請求の対象となる可能性が極めて高いといえます。
④ 単なる心変わり
「気持ちが変わった」「他に好きな人ができた」といった個人的な感情の変化は、正当な理由とはなりません。
婚約は感情的な関係だけでなく、法的な契約関係に基づくものです。
そのため、身勝手な感情の変化によって一方的に解消することは、社会的にも法的にも許容されません。
このような理由による婚約破棄は、相手に大きな精神的苦痛を与えたとして、慰謝料を請求される可能性が高いといえます。
⑤ 信仰の不一致
日本国憲法では信教の自由が保障されており、信仰の違い自体を理由として婚約を破棄することは、原則として正当な理由にはなりません。
当人同士の信仰が異なっていても、そのこと自体で婚約が無効になるわけではなく、婚約破棄の正当な根拠としては弱いとされます。
もっとも、相手が信仰を強要したり、差別的な言動を繰り返すような場合には、婚約破棄の正当な理由と認められる余地があります。
⑥ 相手の親族の非行・犯罪歴
相手の親族に前科や非行歴がある場合でも、それだけを理由に婚約を破棄することは基本的に正当と認められません。
なぜなら、親族の行動が本人の責任に直結するわけではなく、結婚生活に実質的な悪影響が及ぶと証明されない限り、合理的な破棄理由とはならないためです。
ただし、その親族が現在進行形で重大な犯罪行為を行っている場合などには、例外的に判断が変わる可能性もあります。
⑦ 差別的な理由
人種・出身地・性的指向などの差別的な理由による婚約破棄は、正当な理由には該当しません。
人種、民族、出身地、性的指向、性別、年齢、職業、容姿、身体的特徴、思想、信条など、これらに基づく婚約破棄は、社会的にも法的にも許されない差別行為とされています。
このような理由による婚約破棄は、相手の人格を否定するものであり、公序良俗にも反するとして、高額な慰謝料が認められるケースも存在します。
婚約破棄に「正当な理由がない」と判断された裁判例
婚約破棄が法的に問題となるのは、それが一方的・不合理な事情に基づいている場合です。
裁判所が「正当な理由がない」と判断したケースでは、婚約を破棄した側に慰謝料の支払義務が課されることも少なくありません。
以下では、実際の裁判例をもとに、どのような事情が「正当な理由」とは認められなかったのかを確認していきましょう。
- ① 被差別部落出身を理由に破棄したケース
- ② 信仰の継続を理由に破棄したケース
- ③ 相手の民族的出自を理由に破棄したケース
- ④ 性格や容姿、親の意見を理由に破棄したケース
- ⑤ 結婚式直前に失踪したケース
① 被差別部落出身を理由に破棄したケース
この事例では、婚約相手が被差別部落の出身者であることを理由として、婚約が一方的に破棄されました。
裁判所は、このような婚約破棄は公序良俗に反する差別的行為であり、婚姻予約上の地位を侵害する不法行為に該当すると判断しました。
違法性が極めて強いとされ、慰謝料500万円の支払いが認められています(大阪地方裁判所 昭和58年3月28日判決)。
婚姻の自由は尊重されるべきですが、差別的な理由による破棄は正当な理由にはなりません。
とくに、被差別部落に関する差別は憲法上の平等原則にも反するため、法的責任が厳しく問われる傾向にあります。
② 信仰の継続を理由に破棄したケース
本件では、女性が創価学会の信仰を継続することを理由に、婚約が一方的に破棄されました。
裁判所は、憲法で保障された信教の自由に照らし、このような婚約破棄には正当な理由がないと判断。
精神的苦痛に対する慰謝料として、100万円の支払いが認められました(京都地方裁判所 昭和45年1月28日判決)。
宗教や信仰は個人の自由であり、特定の宗教を信仰していることだけを理由とする婚約破棄は、原則として認められません。
ただし、宗教活動の内容や家庭生活への影響など、具体的事情によっては個別判断が必要とされます。
③ 相手の民族的出自を理由に破棄したケース
この事例では、婚約相手が朝鮮人であることに起因して、相手方に対する迷いや不安を抱き、婚約を破棄したものです。
裁判所は、民族差別に基づく婚約破棄は不法行為にあたるとして、婚約破棄をした側に賠償責任を認めました。
慰謝料としては、150万円の支払いが命じられています(大阪地方裁判所 昭和58年3月8日判決)。
婚姻は当事者の合意によるものであるものの、民族や出自を理由とした破棄は明確な差別にあたるため、法的にも厳しく否定されます。
④ 性格や容姿、親の意見を理由に破棄したケース
このケースでは、男性が女性の性格や体形に不満を抱き、また男性の母親の意見にも影響されて婚約を破棄しました。
裁判所は、性格一般や容姿など抽象的・主観的な理由による婚約破棄は正当な理由にならないと判断。
さらに、母親の関与も認定され、男性と母親に対して共同不法行為が成立し、慰謝料400万円が認められました(徳島地方裁判所 昭和57年6月21日判決)。
婚約の破棄は、当事者の自由意思に基づくものであっても、相手の人格を否定するような理由で一方的に破棄すれば、不法行為責任を問われる可能性があります。
⑤ 結婚式直前に失踪したケース
この事案では、男性が結婚式の10日前に突然家出し、行方をくらませたため、予定されていた挙式が不可能となりました。
裁判所は、男性が自らの帰責事由により婚姻の予約を一方的に破棄したと認定し、男性による不当利得返還請求や損害賠償請求をいずれも認めませんでした(大阪地方裁判所 昭和41年1月18日判決)。
婚姻に向けた準備が整い、挙式間近という状況での突然の失踪は、相手方の信頼を著しく損なう行為です。こうした婚約破棄に正当性は認められず、破棄した側が法的責任を問われる可能性が高いといえるでしょう。
婚約破棄の慰謝料相場と慰謝料が高額になるケース
婚約破棄の一般的な慰謝料相場は50万円~200万円が相場です。
もっとも、上記はあくまで目安であって、実際には以下のような事情を総合的に考慮して個別に決めていきます。
- ①婚約に至るまでの交際期間、経緯
- ②婚約後の期間、経緯
- ③結婚に向けた準備が進んでいるかどうか
- ④婚約破棄の原因、経緯
- ⑤婚約破棄の時期
- ⑥性交渉、妊娠、出産の有無
- ⑦年齢
- ⑧社会的地位、経歴、資産
上記事情を踏まえ、婚約破棄の慰謝料が高額になるケースとしては以下のようなものが挙げられます。
- 交際期間が長い
- 婚約後相当期間が経過している
- 婚姻することが周知の事実となっている
- 新居を購入した・賃貸借契約を結んだ
- 相手の浮気、肉体関係が原因だった
- 婚姻間近に婚約破棄された
- 結婚に向けて退職したことでキャリアを失った
- 相手の子を妊娠、出産した など
このように、婚約破棄の慰謝料が高額になるのは、婚約破棄の内容(実情)が悪質で精神的なダメージの度合いが大きいケースと言えるでしょう。
婚約破棄で請求できる慰謝料以外の損害賠償
婚約破棄では、慰謝料以外にも婚約破棄で生じた財産的損害の賠償も請求できます。財産的損害とは、婚約破棄に至ったことで被った費用、出費のことです。
財産的損害には、婚約や婚姻に向けた準備のことで出費を余儀なくされた積極的損害と、婚約破棄されなければ得ることができたであろう消極的損害があります。財産的損害の具体例は以下となります。
- 婚約指輪の購入費用
- 結婚式のキャンセル費用
- 招待状の発送費用
- 結納金
- 旅行のキャンセル費用
- 新居の賃貸借契約費や購入費
- 家財道具の購入費用
- 妊娠・出産にかかった費用
- 退職(寿退社)、転職に伴う減収 など
ただし、財産的損害は、必ずしも婚約破棄の原因を作った側が全額を負担するものではありません。たとえ正当な理由のある婚約破棄をした者であっても、その正当性の程度が低い(弱い)場合には、財産的損害を双方で分担する義務を負うことがあります。
婚約破棄で慰謝料請求をする流れ
婚約破棄で慰謝料請求する流れは次の通りです。
- まずは話し合いによって慰謝料を請求する
- 内容証明を送付して慰謝料を請求する
- 損害賠償請求訴訟を提起する
①まずは話し合いによって慰謝料を請求する
まずは、婚約を破棄した相手に対して、口頭やメール・電話などで婚約の不当破棄による慰謝料を支払うように請求しましょう。
相手が婚約破棄の不当性や、生じた精神的苦痛への責任を感じている相手であれば、前向きに話し合いに応じてくれる可能性があります。
相手にとって有利な事情は、相手が主張・立証することが筋ですので、請求の段階であなたがその点を考慮してあげる必要はありません。
②内容証明郵便を送付して慰謝料を請求する
任意での交渉では支払金額について合意に至らない場合や、そもそも慰謝料の支払いを拒否する場合には、内容証明郵便によって慰謝料その他の損害について賠償請求をしていくことになります。
内容としては、不当な婚約破棄により慰謝料等を請求すること、請求金額、支払方法・支払期限などを記載して請求します。内容証明郵便とは、郵便物の内容について、いつ、どのような内容のものを、誰から誰にあてて差し出したかということを差出人が作成した謄本によって証明するものです。
この内容証明郵便に配達証明を付すことで相手方に到着した日を記載したハガキが届き、このハガキによって郵便物が配達された事実を証明することができます。
このように内容証明郵便は、その後の裁判手続きにおいても、請求の時期や内容について重要な証拠となるため、あなたの本気度を示すことができます。また、時効間際の事案の場合には、時効の完成が猶予されます。
③損害賠償請求訴訟を提起する
内容証明郵便を送付しても相手が慰謝料の支払いに応じない場合には、損害賠償請求訴訟を提起することになります。
訴訟を提起した場合には、当事者双方が証拠に基づいて主張・立証を尽くし、最終的には裁判所が慰謝料等の請求の可否や金額を判断することになります。
訴訟を提起するためには、①婚約の有効な成立と②婚約破棄に正当な理由がないことについては、慰謝料を請求する側が証明する必要があるため、弁護士に手続きを任せるようにしましょう。弁護士に予め相談しておくことで、慰謝料の相場や回収できる確率などについて説明を受けることができます。
婚約破棄の慰謝料請求の時効は?
婚約破棄をされた場合の慰謝料請求権の時効は、3年または10年です。
既に触れましたが、婚約の不当破棄をされた、または、婚約破棄の原因が相手方にある場合、もう一方は相手方に対して不法行為(民法709条)または債務不履行(民法415条)に基づく慰謝料請求をすることができます。ただし、どちらに基づいて請求するかにより時効が異なります。
不法行為に基づいて慰謝料請求する場合は、婚約破棄されてから3年で時効により慰謝料請求権が消滅します(民法724条)。
一方、債務不履行に基づいて慰謝料請求をする場合には、婚約破棄されてから10年で時効により慰謝料請求権が消滅します(民法166条1項2号)。
婚約破棄の法的性質を債務不履行とした判例(東京高裁判決 昭和33年4月24日)もありますので、それによれば婚約破棄の慰謝料は10年で時効消滅すると考えられます。ただし、念のため不法行為に基づく損害賠償請求権(慰謝料も含む)の時効である3年以内には手続きをしておいた方が良いでしょう。
婚約破棄された場合、婚約破棄したい場合の対応
婚約破棄された場合の対応
「突然婚約を破棄され、納得できない」「慰謝料を請求できるのか知りたい」とお悩みの方に向けて、婚約破棄された場合に取るべき対応の流れをわかりやすく解説します。
- 婚約が成立していたことを証明する
- 相手に正当な理由がなかったことを確認する
- 内容証明で慰謝料請求を行う
- 精神的に辛い場合は弁護士に相談する
① 婚約が成立していたことを証明する
婚約破棄で慰謝料を請求するためには、まず相手との婚約が成立していた事実を証明する必要があります。
婚約の成立は、口約束でも認められる場合がありますが、当事者間で認識にズレが生じることも多いため、客観的な証拠が重要です。
たとえば、結納を取り交わした記録や、結婚式場の予約票、婚約指輪の購入記録、両家顔合わせの写真などが証拠となり得ます。
また、メールやLINEのやりとり、音声データなども補強資料として有効です。
② 相手に正当な理由がなかったかを確認する
婚約破棄された側が慰謝料を請求するには、相手に正当な理由がなかったことを証明する必要があります。
たとえば、相手が婚約後に「気持ちが冷めた」「親と合わなかった」などの理由で一方的に破棄した場合には、法的に正当な理由とは認められない可能性が高く、慰謝料請求が認められる可能性があります。
逆に、相手が不貞行為をされた、暴力を受けたなどやむを得ない事情がある場合には、慰謝料が認められない可能性もあるため、相手が主張している理由を正確に把握し、それが法的にどう評価されるのかを検討することが重要です。
③ 内容証明で慰謝料請求を行う
婚約の成立と相手に正当な理由がないことが確認できたら、内容証明郵便により慰謝料請求を行います。
内容証明には、婚約破棄の経緯や請求金額、支払期限などを明記し、法的効力を持たせます。配達証明を付けることで、相手に届いた日付も証明できます。
特に時効が迫っている場合には、内容証明を送ることで時効の完成が猶予されるため、早めの対応が望まれます。
④ 精神的に辛い場合は弁護士に相談する
婚約破棄の問題は、当事者にとって非常に大きな精神的負担となります。
証拠の収集や慰謝料請求に不安がある場合は、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士が介入することで、直接対峙するストレスを避けながら、適正な慰謝料請求がスムーズに進む可能性が高まります。
婚約破棄したい場合の対応
「婚約を解消したいが、慰謝料請求されないか不安」「どのように伝えるべきかわからない」といった方に向けて、婚約破棄をする際に注意すべきポイントと正しい手順を解説します。
- 破棄の理由が法的に正当と認められるかを確認する
- 相手に誠実に理由を説明し、話し合いの場を設ける
- 決断は早めに伝える
- 話し合いがまとまらない場合は示談で解決を図る
- 示談書に清算条項を明記し、署名・押印する
- 示談書の作成が不安な場合は専門家に依頼する
① 破棄したい理由を明確にし、正当性を確認する
婚約破棄を考えた場合には、まずその理由が法的に「正当な理由」として認められるかを確認することが大切です。
相手からの暴力や侮辱的言動、不貞行為などがある場合には、婚約破棄は正当とされる可能性があります。
一方、「気持ちが冷めた」「性格が合わない」などの理由では、正当性が認められず、逆に慰謝料を請求されるリスクがあります。
② 相手に誠実に理由を説明し、話し合いの場を設ける
正当な理由がある場合でも、相手に対して誠実に理由を説明し、納得を得る努力をすることが重要です。
突然の通告や一方的な連絡の遮断は、相手に深い精神的苦痛を与えるおそれがあります。
話し合いを通じて、冷静かつ円滑に合意に至るよう心がけましょう。
③ 婚約破棄の決断は早めに伝える
婚約破棄を決断したなら、可能な限り早く相手に伝えることが大切です。
先延ばしにすると、結婚準備が進行してしまい、相手に金銭的・精神的な損害を与える結果となる可能性があります。
婚約者に過度な期待を抱かせることを避け、誠実なタイミングで話すようにしましょう。
④ 話し合いがまとまらない場合は示談を検討する
相手が納得せず、話し合いが平行線をたどる場合には、示談によって解決を図る方法もあります。
特に、自身に一定の責任があると認める場合には、一定額の金銭を支払うことで相手と和解し、問題を収束させることができます。
⑤ 示談書には清算条項を盛り込む
示談が成立したら、示談書を作成し、清算条項(せいさんじょうこう)を必ず記載しましょう。
清算条項とは、「示談書に記載された内容以外に、お互い一切の権利義務を残さない」という合意事項です。
将来的な金銭トラブルや再度の請求を防ぐためにも、必須の要素といえます。
作成した示談書には当事者双方の署名・押印を行い、2通作成して各自が1通ずつ保管するのが基本です。
⑥ 示談書の作成が不安な場合は専門家に依頼を
示談書の文言や構成に不安がある場合は、弁護士や行政書士に依頼することで、法的に有効な書面を確実に作成できます。
特に慰謝料の金額や支払方法、清算条項などについてトラブルが生じやすいため、専門家のアドバイスを受けて作成することが望ましいです。
婚約破棄でお困りの方は当法律事務所までご相談を
婚約破棄をめぐる問題は、誰にとっても簡単に割り切れるものではありません。
突然の破棄に傷つき、何も手につかない日々を過ごしている方。
反対に、破棄を決断したものの「どう伝えればいいのか」「責任を問われるのでは」と葛藤している方。
そんなときこそ、第三者の視点で状況を整理し、あなたの声に耳を傾けてくれる存在が必要です。
当事務所には、婚約破棄に関する多数の相談・解決実績があります。
全国どこからでも無料でご相談いただけますので、お一人で抱え込まずにご連絡ください。
あなたのお気持ちを、私たちは決して軽く扱いません。
親身誠実に、経験豊富な弁護士があなたの未来を全力で守ります。
婚約破棄で悩まれている方は、どうか勇気を出して、当法律事務所へご相談ください。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|