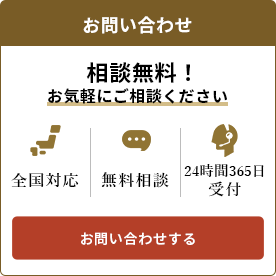検察統計調査によると、大麻事件の不起訴率は約48%です。不起訴になれば、刑事裁判にかけられることもなく、前科もつきません。前科がつかなければ、パスポートの取得や資格取得、特定の職業に就く際の制限を受けることもありません。そのため、大麻事件で捜査を受けた場合は、できるだけ早く不起訴獲得に向けた対応を開始することが重要です。
この記事では、薬物事件に強い弁護士が、
- 大麻所持で不起訴になりやすいケース
- 大麻事件で逮捕されても不起訴になるのはなぜか
- 大麻所持で不起訴になるためにすべきこと
などについて詳しく解説していきます。
さらに、2024年12月施行の法改正により、大麻所持の罰則が強化されました。これまで処罰の対象ではなかった大麻の使用も違法となり、取り締まりが厳しくなっています。この記事では、法改正による影響についても簡単に触れながら解説します。
なお、大麻事件で早急に対応を検討されている方は、この記事を参考にした上で、全国無料相談の弁護士にご相談ください。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
目次
大麻の所持は違法?使用は?
大麻所持は違法
大麻の所持は、日本において法律で明確に禁止されています。
2024年12月12日施行の法改正により、大麻所持に関する規制がさらに厳格化され、罰則も強化されました。これまで「大麻取締法」に基づいて処罰されていた所持の罪は、新たに「麻薬及び向精神薬取締法(麻薬取締法)」によって規制されることになり、より厳しい処罰の対象となります。
大麻取締法における「所持」とは、大麻を現実に支配・管理している状態を指します。具体的には、以下のようなケースが「所持」に該当する可能性があります。
- ポケットやバッグの中に入れて持ち歩いている
- 自宅の引き出しや車のコンソールボックスに保管している
- 借りている倉庫やロッカーに保管している
- 他人に預けているが、自分の指示で動かせる状態にある
なお、所持だけでなく、譲渡・譲受、栽培、輸出入も違法となっており、法改正に伴い、これらの行為に対する罰則も強化されています。
【法改正】大麻の使用も違法に
2024年12月12日以降、日本における大麻の使用が違法となります。
これまで、日本では大麻の所持や譲渡・譲受、栽培、輸出入が「大麻取締法」により規制されていましたが、個人の使用自体には刑罰がありませんでした。そのため、嗜好品として大麻を吸引することは違法ではありませんでした。しかし、2024年12月12日施行の法改正により、大麻の使用が「麻薬取締法」によって新たに規制され、一般人による使用はすべて違法となります。違反した場合、7年以下の懲役が科される可能性があります。
さらに、今回の法改正により、以下の行為についても刑罰が強化されました。
- 大麻の所持
- 大麻の栽培・輸出入
- 営利目的の栽培・輸出入
- 譲渡・譲受
以上のとおり大麻取締法の改正により、日本における大麻の使用は全面的に禁止され、違反者には厳しい刑罰が科されることになりました。加えて、大麻に関する罰則が厳格化されてるため、誤解のないよう正確な情報を把握し、適切に対応することが重要となります。
大麻事件の不起訴率は?
大麻取締法違反事件の不起訴率は約48%です。
2023年の検察統計(「罪名別 被疑事件の既済及び未済の人員」)によると、大麻取締法違反で立件された事件は合計9,872件でした。そのうち、起訴されたのは3,748件、不起訴となったのは4,755件です。つまり、全体の約48%が不起訴となっています。
このように、大麻事件では約半数が不起訴となっています。大麻事犯は、他の薬物犯罪と比較して不起訴となる割合が高い傾向にあります。
大麻所持で不起訴処分になりやすいケースは?
大麻所持では、すべてのケースで起訴されるわけではなく、状況によっては不起訴処分となる可能性があります。不起訴になりやすいケースは次の通りです。
- ① 初犯であり、所持量が少ない場合
- ② 証拠不十分の場合
- ③ 共同所持の疑いをかけられたが、関与が認められなかった場合
①初犯であり、所持量が少ない場合
大麻所持では、初犯かどうか、また所持していた大麻の量が少ないかどうかが、不起訴になるかどうかの重要なポイントとなります。
特に、所持量が少量(目安として0.5g未満)の場合、悪質性が低いと判断され、不起訴や起訴猶予となる可能性が高くなります。
また、初犯であれば「大麻を常習的に使用していない」とみなされることが多く、反省の態度を示せば不起訴処分となることがあります。
②証拠不十分である場合
大麻所持では、証拠が不十分な場合、不起訴となることが多いです。
以下のようなケースでは、証拠不十分と判断される可能性があります。
- 大麻の所持や使用を裏付ける証拠が見つからない場合
→例えば、家宅捜索が行われたものの大麻が発見されなかった場合、検察官は起訴できません。また、通報や情報提供があったとしても、実際に大麻を所持している証拠がなければ、不起訴になる可能性が高いでしょう。 - 譲渡の証拠がない場合
→大麻の譲渡が疑われたとしても、実際に取引を証明する証拠(やりとりの記録や現場の押収物)がなければ、起訴は困難です。
③共同所持の疑いをかけられたが、関与が認められなかった場合
大麻所持では、共同所持の疑いで逮捕されるケースもあります。共同所持とは、2人以上で大麻を管理・支配している状態を指します。
しかし、以下のようなケースでは、不起訴となる可能性が高いです。
- 同居人が大麻を所持していたが、自分はその存在を知らなかった場合
→例えば、ルームメイトや家族が大麻を所持していたとしても、自分がその存在を知らなければ、共同所持には該当しません。 - 自分は大麻を管理・支配していなかった場合
→共同所持と認められるには、「大麻を管理・支配していること」が条件となります。例えば、友人が持っていた大麻を一時的に預かっていた場合でも、実際には使用せず管理もしていなかったことが証明できれば、不起訴となる可能性があります。
大麻事件で逮捕されても不起訴になるのはなぜ?
日本では、大麻事件で逮捕されたとしても、不起訴になるケースが少なくありません。不起訴とは、検察官が事件を裁判にかけずに終了させることを指し、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3つの理由に分類されます。
大麻事件で不起訴になる理由はいくつかありますが、主に以下のような要素が影響します。
- 証拠不十分
→大麻の所持や使用が疑われても、確実な証拠が揃わなければ起訴は困難です。例えば、所持していたとされる大麻の鑑定が不十分であったり、本人が使用した明確な証拠がない場合、検察官は不起訴を選択することがあります。 - 情状酌量の余地がある
→検察官は、被疑者の反省の態度や更生の可能性を考慮して起訴するかどうかを判断します。初犯であり、反省の意思が強い場合は、起訴猶予となることがあります。 - 社会的影響の考慮
→起訴することで、被疑者の社会復帰が困難になる場合も考慮されます。特に若年層の初犯者に対しては、社会復帰を優先し、不起訴処分となるケースがあります。
大麻事件で起訴されたら執行猶予はつく?
大麻所持で起訴された場合、執行猶予がつく可能性は比較的高いといえます。
法務省が発表した令和3年の犯罪白書によれば、大麻取締法違反で有罪判決を受けた人のうち、実刑判決となった割合は11.4%にとどまりました。これは、約9割の被告が執行猶予付きの判決を受けたことを示しています。
特に、初犯者の割合が78.1%と高く、個人使用目的で所持していた場合、執行猶予がつく可能性がより高まる傾向があります。
しかし、全ての初犯者に執行猶予が適用されるわけではありません。裁判所は、所持量、反省の態度、再犯の可能性などを総合的に考慮したうえで執行猶予の有無を判断します。
そして、大麻所持で執行猶予がつきやすいのは、以下のようなケースです。
- 初犯であること:初めての違反であり、再犯のリスクが低いと判断される場合
- 少量の所持:個人使用目的で少量を所持していた場合
- 深く反省していること:反省の態度が明確であり、今後使用しないことを誓っている場合
- 社会的基盤がしっかりしていること:仕事や家庭環境が安定し、更生の見込みが高いと判断される場合
上記に対して、以下のようなケースでは執行猶予がつきにくく、実刑となる可能性が高まります。
- 営利目的での所持・譲渡:販売目的で大量に所持していた場合
- 常習性があると認められる場合:過去に薬物使用歴があり、依存症のリスクが高い場合
- 短期間での再犯:前回の判決から5年以内に再度大麻関連の罪で起訴された場合
- 執行猶予期間中の再犯:執行猶予中に再び大麻所持などで逮捕された場合
大麻事件で起訴された場合の刑罰
日本では、大麻関連の犯罪で起訴され有罪となった場合、基本的に懲役刑が科されます。罰金刑のみで済むことはなく、営利目的の場合に限り、懲役刑に加えて罰金刑が科されることがあります。
処罰の対象となる行為には、大麻の使用、所持、譲渡・譲受、栽培、輸出入などが含まれます。
2024年12月12日施行の法改正により、刑罰が厳格化され、特に営利目的の犯罪に対する懲役刑が重くなりました。改正前は罰則の上限のみが規定されていましたが、新法では懲役刑の下限が設けられ、より厳しい処罰が適用されます。
改正前後の刑罰の違いは、以下の表のとおりです。
| 【2024年12月12日以後の大麻の刑罰】 | |
| 犯罪となる行為 | 科される刑罰 |
| 栽培・輸出入 | 1年以上10年以下の懲役 |
| 営利目的の栽培・輸出入 | 1年以上20年以下の懲役(または1年以上20年以下の懲役および500万円以下の罰金) |
| 使用・所持・譲渡・譲受 | 1ヶ月以上7年以下の懲役 |
| 営利目的の使用・所持・譲渡・譲受 | 1年以上10年以下の懲役(または1年以上10年以下の懲役および300万円以下の罰金) |
| 【2024年12月11日以前の大麻の刑罰】 | |
| 犯罪となる行為 | 科される刑罰 |
| 栽培・輸出入(旧大麻取締法24条1項) | 7年以下の懲役 |
| 営利目的の栽培・輸出入(同法24条2項) | 10年以下の懲役(または10年以下の懲役および300万円以下の罰金) |
| 所持・譲渡・譲受(同法24条の2第1項) | 5年以下の懲役 |
| 営利目的の所持・譲渡・譲受(同法24条の2第2項) | 7年以下の懲役(または7年以下の懲役および200万円以下の罰金) |
大麻所持で不起訴になるには何をすべき?
大麻所持で逮捕された場合でも、適切な対応を取ることで不起訴となる可能性があります。不起訴になるためにすべきことは次の通りです。
- ①早期に弁護士を依頼する
- ②反省の意思を示す
- ③再犯防止策を講じる
① 早期に弁護士を依頼する
逮捕・勾留されている場合、不起訴に向けた準備を進める時間が限られているため、できるだけ早く弁護士を依頼することが重要です。
弁護士は、被疑者に有利な証拠を集めたり、検察官に情状酌量を訴えたりする役割を担います。特に、大麻事件では「更生の意思」を示し、再犯のリスクがないことを説明することが、不起訴を獲得するための重要なポイントとなります。
② 反省の意思を示す
検察官に対して、真摯に罪を認め、反省していることを示すことが重要です。具体的には、供述の際に反省の言葉を述べるほか、再犯防止のための具体的な取り組みを説明することが効果的です。
③ 再犯防止策を講じる
不起訴を獲得するためには、再犯の可能性が低いことをアピールすることが大切です。具体的には、以下のような対策が有効です。
- 大麻を入手できる環境や交友関係を断つ
- 更生プログラムへの参加を検討する
- 家族の協力を得て、生活環境を改善する など
検察官は、被疑者が更生の意思を持っているかどうかを重視するため、これらの取り組みを積極的に行うことで、不起訴の可能性を高めることができます。
大麻所持で逮捕された場合の流れ
大麻所持で逮捕された場合、手続きは以下のように進みます。
- 逮捕されるまで
- 逮捕後の流れ
- 勾留と起訴・不起訴の判断
- 起訴後の裁判と判決
①逮捕されるまで
大麻所持が発覚するケースには、職務質問や所持品検査、あるいは別の犯罪捜査中の家宅捜索などがあります。
職務質問では、捜査官(主に警察官)が対象者の挙動などから薬物を所持している可能性があると判断すると、職務質問を行います。その際、所持品検査の結果、大麻と疑われる物が押収され、現場での簡易検査で陽性反応が出た場合、その場で現行犯逮捕されます。
また、別の犯罪の捜査中に家宅捜索が行われ、その際に大麻が発見・押収されることで、大麻所持の容疑で通常逮捕されることもあります。
②逮捕後の流れ
逮捕されると、警察署の留置場に収容されます。逮捕前後には警察官による「弁解録取」が行われ、逮捕事実に関する認否や言い分を聴かれます。これは実質的には取調べと同様ですが、被疑者には署名・押印の拒否権や黙秘権などの権利があります。
警察官の弁解録取が行われた後、釈放されない場合、逮捕から48時間以内に検察庁へ送致されます。検察官による弁解録取を受けた後も釈放されなければ、送致から24時間以内に検察官が裁判官に対して勾留請求を行います。
その後、裁判官による「勾留質問」が行われ、逮捕事実についての説明を求められます。裁判官が勾留を許可した場合、引き続き身柄が拘束されることになります。なお、大麻所持のケースでは、この段階で釈放されることはほとんどありません。
③勾留と起訴・不起訴の判断
勾留が決定すると、まず10日間の勾留期間が設定されます。その後、検察官の請求により、裁判官が許可すれば最大10日間の延長が認められます。
この間に捜査が進められ、検察官が起訴するか不起訴にするかの判断を下します。
大麻の単純所持で執行猶予が見込まれるような比較的軽微な事件では、勾留の延長が行われないこともあります。しかし、大麻犯罪では勾留期間が延長されることが多いため、長期間にわたり身柄が拘束される可能性があります。
④起訴後の裁判と判決
起訴されると、刑事裁判を受けることになります。第1回の裁判は、起訴からおおよそ1〜2か月後に開かれるのが一般的です。
その後、裁判は一定の間隔で進行し、最終弁論から判決までは約2週間かかります。罪を認める「自白事件」であれば、判決を含め平均2回程度の裁判が開かれます。
一方で、否認事件の場合、被告人の認否や事件の争点によっては3回、4回、5回と裁判が続くこともあります。
判決を受けた日の翌日から14日間は、不服があれば控訴や上告を申し立てることができます。不服を申し立てずに14日間が経過した場合、判決で言い渡された刑が確定します。
大麻事件で不起訴を目指す人が弁護士に依頼するメリット
大麻事件で不起訴を目指す場合に弁護士に依頼するメリットは次の通りです。
- ①違法捜査による不当な立件を防ぐ
- ②取調べへの対応と自白の強要を防ぐ
- ③再犯防止、更生に向けたサポートを行う
①違法捜査による不当な立件を防ぐ
大麻事件で検挙された場合でも、大麻を押収する過程で違法な捜査が行われている可能性があります。そのため、捜査機関の手続きに疑問を抱く被疑者も少なくありません。
もし、大麻の押収時に重大な違法捜査が行われ、その手続きで得られた証拠の使用が「将来の違法捜査の抑制」という観点から相当でないと判断されれば、その証拠は証拠能力を否定され、罪を立証するために使用することができません。その結果、被疑者は嫌疑不十分による不起訴となる可能性があります。
弁護士は、違法捜査の疑いがある場合、検察に対し「違法な手続きによって得られた証拠は証拠能力を欠くため、起訴すべきではない」と主張します。違法な証拠が排除されれば、検察は十分な証拠を確保できず、結果として不起訴処分となる可能性が高まります。
②取調べへの対応と自白の強要を防ぐ
大麻事件では、大麻を所持していたことの認識や、犯罪の故意を否認するケースが少なくありません。しかし、客観的な証拠が不足している場合、捜査機関は被疑者の自白に頼らざるを得ず、強引な取調べが行われることがあります。
弁護士は、被疑者が犯罪の故意を否認する場合、違法・不当な取調べが行われていないかを注視し、その疑いがある場合は捜査機関に異議を申し入れるなどして取調べを牽制します。また、被疑者に取調べへの対応を助言し、不本意な自白を防ぐためのサポートも行います。
こうした弁護士の対応により、捜査機関が自白を証拠として確保できなければ、故意の立証が難しくなり、起訴が見送られる可能性が高まります。不当な自白を防ぐことが、不起訴につながる重要なポイントとなります。
③再犯防止、更生に向けたサポートを行う
大麻事件では、仲間内で使用するケースが多く、「仲間を警察に話せば孤立してしまうのではないか」という不安から、グループから抜け出せない人も少なくありません。しかし、そのような状況が続くと「再犯の可能性が高い」と判断され、検察の起訴判断に影響を与えることがあります。
弁護士は、こうした不利益について被疑者に丁寧に説明し、大麻グループと関係を断つことの重要性を伝えます。その上で、被疑者が自ら更生の意思を示せるよう、具体的なアドバイスを行います。また、大麻の使用に対する依存傾向がある場合、ご家族と連携し、薬物治療の専門病院への入通院や、精神保健福祉センター、ダルクなどの支援団体が提供するプログラムへの参加を促し、再犯防止に向けた環境を整えます。
さらに、弁護士はこうした更生への取り組みを裏付ける資料を作成し、検察に提出します。具体的には、被疑者が大麻グループと関係を断ち、社会復帰に向けた努力をしていることを示す証拠を整理し、監督者となる家族や支援者の協力体制が整っていることを強調します。これにより、検察が「再犯の可能性が低い」と判断すれば、起訴の必要性を再考し、不起訴となる可能性を高めることができます。
まとめ
従来、大麻の使用自体は犯罪ではありませんでしたが、大麻取締法の改正により、2024年12月12日以降、大麻の不正使用は麻薬取締法違反となり、逮捕・起訴される可能性があります。
また、法改正に伴い、大麻の栽培、輸出入、所持、譲受・譲渡に関する規制が強化され、厳罰化が進んでいます。
大麻に関する事件で警察の捜査を受けたり逮捕されたりした場合、早期の対応が極めて重要です。初動を誤らず、迅速かつ適切な対応をとることで、状況を有利に進めることができます。
そのため、大麻事件の弁護経験が豊富な弁護士に依頼することが大切です。早期釈放や不起訴処分の獲得、さらには裁判となった場合の執行猶予の獲得を目指すには、刑事事件に強い弁護士への早めの相談が不可欠です。
当事務所では、大麻所持を含む薬物事件での不起訴獲得実績があり、弁護士が親身かつ誠実に依頼者を全力でサポートします。大麻事件でお困りの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|