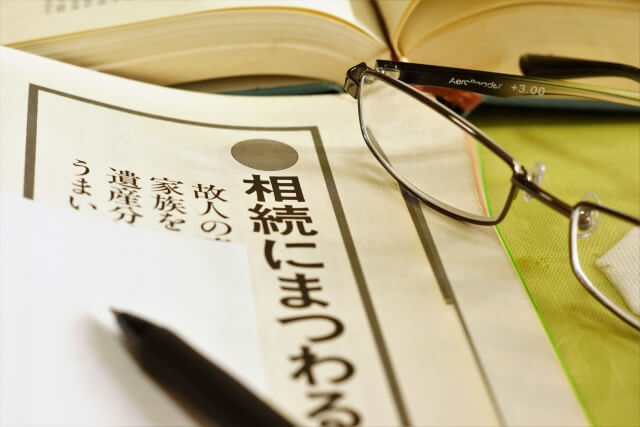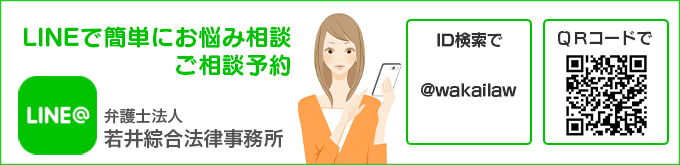- 私の死後、財産を相続させたくない相続人がいる…
- 「相続廃除」という制度で、相続権を剥奪できるという情報を耳にしたが、どんな制度だろう…
このような悩みや疑問をお持ちではないでしょうか。
そこでこの記事では、相続問題に強い弁護士が、
- 相続廃除とは、どんな制度なのか
- どのような条件(要件)を満たせば相続の廃除ができるのか?
- 相続廃除の事例
- 相続放棄の手続き方法
などについて分りやすく解説していきます。
記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には弁護士までご相談ください。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
相続廃除とは?
相続廃除とは、相続人が被相続人を虐待していたなど、被相続人が遺産を相続させたくないと考えても仕方のない事由があった場合に、被相続人の意思で家庭裁判所に廃除の申立てをすることによってその相続人の相続権をはく奪する制度です。
民法第892条では、相続廃除をつぎのように定めています。
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
相続廃除を出来る人はだれ?
相続廃除を家庭裁判所に請求できるのは、被相続人のみとなります。
したがって、例えば、母親一人と子どもA・子供Bの3人家族で、Aが「Bは母の介護にも一切関わってこなかったし、日常的に母を精神的に虐待する侮辱発言をしていた。母の遺産を相続するなんて許せない。私がBを相続廃除する請求をしよう」と考えても裁判所に受け付けてもらえません。
相続廃除の対象者「遺留分を有する推定相続人」とは?
相続廃除の対象者は、上記条文からもわかる通り、「遺留分を有する推定相続人」です。
まず「推定相続人」とは、現時点で被相続人が亡くなった場合に相続人になるはずの人のことです。例えば、夫婦と子ども一人の家庭で夫が亡くなったと仮定すれば、妻と子どもは夫の遺産を相続するはずの人ですので推定相続人にあたります。
次に「遺留分」とは、一定の範囲の相続人に対して、遺言でも奪うことのできない最低限の相続分のことです。例えば、上の例で夫が死ぬ前に愛人に全財産(4000万円とします)を譲り渡すという遺言を残していたとしても、妻と子には遺留分(ともに4分の1)がありますので、妻と子はそれぞれ1000万円ずつ遺産相続をすることができます。
上記例で考えた場合、残された妻と子は「遺留分を有する推定相続人」にあたりますので、夫が相続人を廃除する場合の対象者に含まれます。
他方で、遺留分を有しない推定相続人は相続廃除の対象者とはなりません。例えば、子どもがいない夫婦で夫に兄弟姉妹がいる場合(親や祖父母などの直系尊属は既に他界)、夫の死亡により妻と兄弟が推定相続人となりますが、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、相続廃除の対象者とはなりません。
なお、被相続人が推定相続人である兄弟姉妹に遺産を相続させたくない場合には、被相続人は第三者に生前贈与または遺贈などすることで遺産が兄弟姉妹に引き継がれることを防止できます。
| 相続廃除の対象者(遺留分あり) |
|
| 相続廃除の非対象者(遺留分なし) | 兄弟姉妹 |
相続廃除の要件
相続廃除が認められるためには、廃除される推定相続人において、つぎのどれかに該当する行為をしたことが必要です。
- ① 被相続人に対する虐待
- ② 被相続人に対する重大な侮辱
- ③ その他著しい非行
これらに該当する行為がある場合には、被相続人は家庭裁判所に相続廃除の請求をすることができます。
廃除が認められるための要件について、順を追って詳しく見てみましょう。
①被相続人に対する虐待
相続廃除が認められるためには、推定相続人が被相続人に対して虐待をしていることが要件の1つとされています。
ここで言う「虐待」とは、被相続人に対する肉体的な暴力などの加害行為だけでなく、精神的に耐え難い苦痛を与えるような行為を含みます。
具体的には、推定相続人においてつぎのような行為がある場合、相続の廃除が認められる可能性があります。
- 被相続人に対して日常的に暴力を振るっている
- 被相続人に対して日常的に暴言を浴びせ、精神的に虐待している
- 被相続人が要介護状態であるにもかかわらず、介護をせず放置している
②被相続人に対する重大な侮辱
ある推定相続人が被相続人に対して重大な侮辱を与えた場合、被相続人はその相続人に関して相続廃除を請求することができます。
「重大な侮辱」とは、被相続人に向けられた行為で、被相続人の名誉や感情を害する行為全般を指します。
具体的には、つぎのような行為が被相続人に対する重大な侮辱行為に該当します。
- 世間に被相続人の悪口を言いふらす
- 被相続人に対して裁判を起こす
③その他著しい非行
民法では、推定相続人に「著しい非行」がある場合、相続の廃除が認められることになっています。
しかし「著しい非行」と言われても、あまりに抽象的すぎて実際にどのような場合に相続廃除が認められるのか不明確です。
それでは、実際にはどのような行為が「著しい非行」に該当するのでしょうか?
具体的には、つぎのような行為がある場合、著しい非行として相続の廃除が認められる可能性があると考えてよいでしょう。
- 被相続人の財産を不当に処分する行為
- ギャンブルなどを繰り返して多額の借金を作り、これを被相続人に支払わせる行為
- 浪費、遊興、犯罪行為、暴力団など反社会集団への加入・結成をする行為
- 異性問題を繰り返すなど親族に迷惑をかける行為
- 重大な犯罪行為により、5年以上の有期懲役や無期懲役または死刑の宣告を受けた場合
- 愛人を作り、家庭に帰ってこないなどの不貞行為
上記は、あくまでも一例にすぎません。実際には、当事者の諸事情によっては廃除が認められないケースもありますので、ご注意ください。
推定相続人の廃除の具体的な事例(判例)
推定相続人の廃除が認められた事例(判例)
名誉棄損等による相続廃除が認められた事例
この事例は、被相続人の次女が、小学校・中学校・高等学校在学中を通じて非行を繰り返していた事例です。そしてさらにこの相続人は、暴力団の一員であった男性と婚約したものの、父親・母親は婚姻に反対していました。
しかし彼女は、父母のそのような態度を十分に認識しておきながら、披露宴の招待状に招待者として父親の名前を印刷して、父母の知人等に送付しました。
このような相続人の行為が、被相続人に対する精神的苦痛を与えその名誉を毀損し、被相続人と相続人との家族的協同生活関係が破壊されその修復が困難になる侮辱・非行であると認定されました(東京高等裁判所平成4年12月11日決定)。
裏切り・不貞行為により相続廃除が認められた事例
この事例は相続人である女性が、夫を裏切り父である被相続人や夫や子どもを捨てて不貞を継続していたとして、相続人廃除が認められた事例です。
この事例で裁判所は、審判の相手方となっている夫が現に経済的苦痛のない家庭であり、夫や父が寛大な復帰の勧告をしているにもかかわらず、夫や自身の父親、子ども2人を捨てて別の男性の元で同棲し既に3カ月近く不貞行為を継続していると認定しました。
そのうえで、このような相続人の行為は家族的協同生活関係を破壊しその修復が困難となる「著しい非行」に該当するとして、推定相続人の地位を廃除する審判が下されました(広島家庭裁判所昭和30年9月2日審判)。
推定相続人の廃除が認められなかった事例(判例)
被相続人側にも責任があったとして相続人廃除が否定された事例
この事例は、被相続人が生前に廃除の請求をしたうえ、更に遺言で同一事由により廃除の意思表示を示し、遺言執行者を指定して遺産の管理・処分を委ねていた事例です。
この事例では被相続人(父)が、その妻の生存中に妾を囲い非嫡出子を産ませたうえで妻の1周期も済まないうちに相続人(長男)らの反対にもかかわらず再婚をしていました。
そのうえで裁判所は、被相続人が再婚後に相続人夫婦との融和を図らず、再婚配偶者と長男の妻との確執を放置するなどしていたため、その責任の原因は被相続人側にもあると認定しました。結果的に推定相続人の廃除原因は否定されました(名古屋高等裁判所金沢支部昭和61年11月4日決定)。
被相続人を告訴したことが侮辱にあたらないとされた事例
この事例は相続人が、他人名義に仮登記された土地がさらに本登記されることを防ごうと警察当局の協力を得る目的で、被相続人を告訴した事案です。
裁判所は、たしかに被相続人を告訴した相続人の行為は、親である同人に対し侮辱を加えたといえるものの、相続人がそのような行動に出なければならなかった原因の一端は被相続人側にあり、さらに告訴も一時的な所業に過ぎないと認定されました。
以上より相続人の廃除の規定にある「重大な侮辱」にまでは及んでいないとして、廃除が否定されました(東京高等裁判所昭和49年4月11日決定)。
相続廃除の手続き方法
相続廃除を行うには、「生前廃除」と「遺言廃除」の2つの方法が認められています。
生前廃除の手続き方法
生前廃除は、被相続人が生前に行う相続廃除の方法です。
生前廃除する場合、被相続人が、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に「推定相続人廃除の審判」の申立てをし、その許可を得る必要があります。
必要書類は、
- 推定相続人廃除の審判申立書
- 申立人(被相続人)及び相手方(廃除したい相続人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
となりますが、このほかにも書類が必要とされる場合もありますので管轄裁判所に事前に問い合わせをしておきましょう。
また、費用として、収入印紙 800円、予納郵便切手(各裁判所により異なります)がかかります。
遺言廃除の手続き方法
相続廃除は、被相続人の死後に行うことも可能です。この場合には、被相続人は遺言によって相続の廃除の意思表示をすることになります。
遺言書には、廃除したい相続人のほか具体的な理由を記載する必要があります。例えば、「次女の〇〇は常日頃から遺言者に侮辱的な発言をしたり、暴力を振るって怪我をさせることもあったため、遺言者は次女を推定相続人から廃除します」といった記載です。もっとも、この事実を裏付ける証拠がなくては裁判所に廃除を認めてもらうことは難しいため、侮辱的な発言を録音したデータや医師の診断書などの証拠を生前に準備しておくようにしましょう。
また、遺言による相続の廃除の場合、かならず遺言執行者が廃除の手続きを行わなければなりません。そのため、遺言書で遺言執行者を指定しておいた方が良いでしょう。
相続廃除が認められた場合の届出について
家庭裁判所において相続廃除を認める審判が下り、それが確定した場合には、相続人廃除に関する届出(推定相続人廃除届)をする必要があります(戸籍法97条)。
届出先の役所
相続人廃除の届出を行う役所は、つぎのうちのどれかとなります。
- ①推定相続人の本籍地
- ②届出人の住所地
- ③届出人の所在地
届出をすべき人
届出を行うべき人は、相続廃除の審判を申立てた人です。生前廃除であれば被相続人が届出義務者であり、遺言廃除の場合には遺言執行者が届出義務者となります。
届出の期限
相続廃除の届出は、審判確定後10日以内に行う必要があります。
必要書類
相続廃除の届出を行うには、届出書のほかに審判書の謄本と確定証明書が必要となります。審判は通常2週間で確定するため、2週間以上経過した後に、手続きをした家庭裁判所で確定証明書をもらうことになります。
相続廃除について押さえておくべきポイント
相続廃除が認められる確率は約20%
相続廃除の申立てを受けた家庭裁判所は、証拠資料や当事者の主張などを総合的に判断して廃除を認めるかどうか判断します。
しかし、実際の運用では廃除が認められる事例は、それほど多くありません。
令和3年度司法統計によると、「推定相続人の廃除及びその取消し」の審判の総数は333件で、その内、年度内に結果が出た既済は212件、申し立てが認容されたものが42件です。この統計データは相続廃除だけでなく相続廃除の取消しの件数も含むため正確な数字とはいえませんが、それを前提に確率を求めると最大19.8%しか相続廃除は認められないことになります。
このように、相続人を廃除するのは、かなりハードルの高い行為だと考えておいたほうがよいかもしれません。
代襲相続は可能
相続廃除を受けた相続人は、被相続人との関係における相続に関しては相続権を喪失することになります。
しかし、廃除を受けた相続人に子や孫といった直系卑属がいる場合、その子や孫は廃除を受けた相続人に代わって相続することが認められます。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
例えば、Aさんには推定相続人である子Bがおり、Bには子C(Aさんからみて孫)がいるとします。この場合、Aさんの申立により裁判所がBの廃除を認めたとしても、Bの子であるCは代襲相続によりBの相続分を相続することができます。つまり、相続廃除の効果は代襲相続人には及ばないということです。
このケースでAさんが孫Cにも一切遺産相続させたくないと考えた場合には、代襲相続人である孫についても相続廃除するしかありません。ただし、孫が相続廃除の条件(虐待・侮辱・著しい非行)を満たしていない場合には裁判所が相続廃除の請求を認めることはありません。
相続廃除と相続欠格の違い
これまで説明したように、相続廃除とは、一定の要件を満たした場合に被相続人の意思により推定相続人を相続から廃除する制度です。他方で、相続欠格とは、相続人において、民法の定める一定の行為がある場合、法律上当然に相続権がはく奪される制度です。
相続廃除が被相続人の意思に基づいてなされるものであるのに対し、相続欠格は当然に相続権が失われる点で両者は異なります。
相続欠格にあたる行為としては、被相続人や先順位・同順位の相続人を殺害または殺害しようとして刑に処せられた場合、詐欺・脅迫によって遺言の妨害・遺言の撤回をさせた場合などがあります。
相続欠格については、相続欠格とは?5つの欠格事由と相続廃除との違いを徹底解説で詳しく解説されています。
相続廃除は取消すことも可能
被相続人は、特定の相続人に対してすでになされている相続廃除を取り消すことも可能です。
相続廃除の取消しは、被相続人の生前に家庭裁判所に申し立てをする方法と、遺言に取消しの意思表示をしておく方法の2つがあります。
相続廃除が取り消された場合、その相続人には被相続人に対する相続権が認められることになります。
相続廃除をすると相手に通知が行く
相続廃除の手続きをするとあいてに通知が行くことになります。
相続廃除の手続きについては、「生前廃除」と「遺言廃除」の2つの方法があると解説しました。
「生前廃除」の場合には、被相続人の請求を受けて家庭裁判所が審判によって廃除の可否を判断します。ただしこの手続きでは原則として家庭裁判所が推定相続人の陳述を聞く必要があるのです。そのため家庭裁判所から推定相続人に呼び出し通知が届いてしまいます。推定相続人に秘密裏に相続廃除を行うことはできず、当該人物との人間関係の更なる悪化を招いてしまう可能性があります。
対して「遺言廃除」の場合には、推定相続人に通知が行くことはありませんが、相続発生後に家庭裁判所が審判によって推定相続人の廃除を認めないという可能性もあります。
相続廃除の確認方法と戸籍への記載例
相続人が相続廃除されたかいなかについては、当該相続人の戸籍(全部事項証明書)を見れば確認することができます。そのため戸籍(全部事項証明書)によって当該相続人が相続廃除されているということを証明することができるのです。
廃除を受けた推定相続人は、戸籍の身分事項欄に「推定相続人廃除」と記載されることになります。右の欄には、「推定相続人廃除の裁判確定日」、「被相続人」、「届出日」、「届出人」、「届出を受けた日」、「受理者」が記載されることになります。
戸籍の記載例としては、以下のような内容となります。
令和〇年〇月〇日母山田花子の推定相続人廃除の裁判確定同月〇日母届出人
まとめ
今回は、相続人の「廃除」について解説させていただきました。
被相続人に対して虐待や重大な侮辱、その他著しい非行と認められる行動がある場合、被相続人は生前または遺言によってその相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。
しかし、請求したからといって、かならず廃除が認められるわけではありません。廃除を認めてもらうためには、家庭裁判所が相続人の廃除を認めるだけの証拠の提出や、相続廃除を正当とするための主張など裁判上の行為が必要です。
このような手続きは、法律の専門家なしには、なかなか行うことが難しいものです。相続人を廃除したいにもかかわらず、裁判上のミスから相続廃除が認められなかったりしたら一大事です。
そのようなことを防ぐためにもっとも有効な方法は、弁護士に相談することです。弁護士に相談すれば、どんな場合であれば相続の廃除が認められるのか具体的にアドバイスを受けることが可能です。
弊所では、相続廃除のお悩みを解決してきた実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力でサポートすることをモットーとしておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|