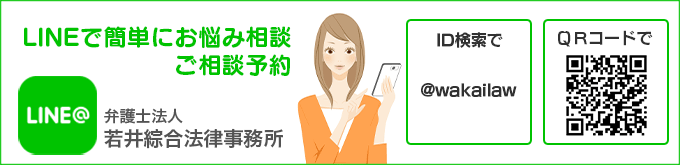- 「離婚裁判を考えているけど裁判にかかる費用の相場はどれくらいだろう…」
- 「離婚裁判を弁護士に依頼した場合の費用相場がわからない…」
- 「離婚裁判でかかる費用は誰が負担するの?」
このようにお考えではないでしょうか。
結論から言いますと、
- 離婚裁判費用(訴訟費用)の相場は2万円~
- 離婚裁判を弁護士に依頼した場合の費用相場は60万円~100万円程度
となります。
また、弁護士費用を除く離婚裁判でかかる費用の負担は、基本的には原告(裁判を申し立てた側)が負担します。ただし、その後、離婚裁判で原告が全面勝訴した場合は、訴訟費用は全額、被告(裁判を申し立てられた側)負担となります。つまり、原告が裁判所に納めた費用を被告に請求できることになります。
弁護士費用については原則自己負担ですが、離婚の原因となった不法行為(不貞行為やDV・モラハラなど)の損害賠償請求(慰謝料請求)の判決で認められた損害賠償額の10%ほどは相手に請求できます。
この記事では、離婚問題に強い弁護士が、上記内容につきわかりやすく解説していきます。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|
目次
離婚裁判でかかる費用とは
離婚裁判をするのにかかる費用は、
- 離婚裁判費用(訴訟費用)
- 弁護士費用
の2種類です。
離婚裁判費用とは、裁判手続きを行う際に発生する費用のことです。たとえば、離婚裁判費用には、
- 訴状を提出する際に必要な手数料(訴状に貼付する印紙代)、郵便切手代
- 証人が法廷に出廷する際に必要な旅費、日当及び宿泊費
などが含まれます。
他方で、弁護士費用とは、弁護士に離婚裁判の弁護活動を依頼した場合に伴って発生する費用、具体的には、法律相談料や着手金、報酬金などがそれにあたります。
離婚裁判費用の相場と内訳
離婚裁判の費用相場は約2万円~です。ただしこの金額は、裁判で離婚のみを求める場合の相場です。離婚の他に財産分与や養育費などを求めて訴える場合や、証人を呼ぶ場合には別途費用が掛かります。以下で、離婚裁判費用の内訳について見ていきましょう。
手数料
手数料とは、訴訟の提起の際に必要な訴状に貼付する印紙代のことです。
手数料は、離婚のみを求める場合は「1万3,000円」です。これは、親権者の指定を求める場合を含みます。
しかし、離婚に併せて財産分与、養育費、面会交流を求めて訴える場合はそれぞれにつき1,200円(養育費の場合は子供1人につき1,200円)が加算されます。
たとえば、離婚請求に併せて財産分与と子2人の養育費を請求する場合は、「1万3,000円+1,200円(財産分与)+1,200円×2人分(養育費)=1万6,000円」が手数料となります。
また、離婚の他に慰謝料請求もする場合、慰謝料請求額が160万円を超えると上記の1万3,000円に手数料が加算されます。
たとえば、離婚請求、財産分与と子2人の養育費に併せて慰謝料300万円を請求する場合は、「(慰謝料300万円を請求する場合の手数料は2万円)+1,200円(財産分与)+1,200円×2人分(養育費)=2万3,600円」が手数料ということになります。
具体的な手数料については、手数料額早見表|裁判所サイトで確認しておきましょう。
郵便切手代
郵便切手代は、裁判所が原告、被告などに対して書類を送る際にかかる費用のことです。
郵便切手代は裁判所によって異なりますが、6,000円前後から7,000円前後が一般的です。
金額のほか、切手の種類、枚数も裁判所により異なりますので、訴訟を提起する前に裁判所に確認しておきましょう。
証人が法廷に出頭する際に必要な日当、旅費、宿泊費
日当は、証人が出頭や出頭のための旅行に要した日数に応じてかかる費用です。1日あたり「3,950円」という固定の金額が設定されています。
旅費は、証人が裁判所に出頭するために要する交通費のことです。もっとも、交通費といっても実費で発生するわけではありません。旅費は「300円~」で、証人の住所地と出頭する裁判所までの距離に応じて増額されます。
宿泊費は、証人が出頭や出頭のための旅行に要した宿泊料のことです。宿泊地によって、一夜あたり「8,500円」の場合と「7,500円」の場合があります。
離婚裁判の弁護士費用の相場と内訳
離婚裁判の弁護士費用の相場は約60万円~100万円程度です。以下でその内訳について確認しておきましょう。
法律相談料
法律相談料は、弁護士にはじめて相談する「初回法律相談」の際に発生する費用です。
一般的には、離婚法律相談は1時間1万円、30分延長毎に5000円の追加料金がかかることが多いでしょう。ただし最近では、初回の法律相談に限って「無料」としている法律事務所も多いです。もっとも、無料といっても「30分」、「60分」などと時間制限を設けている場合もあり、超過分は有料となる場合もあります。
離婚請求が認められるのか、慰謝料はどの程度請求できるのか、有利な条件で離婚するためにはなにをすべきなのか、弁護士からアドバイスを受けるのにかかる時間は1時間程度が目安です。ただし、離婚問題は子どもの養育費や親権問題など多岐にわたりますので、1時間を超えて延長料金が発生する可能性があることも留意しておきましょう。
着手金
着手金は、弁護士と委任契約を締結した(弁護士に弁護活動を依頼した)直後に発生し、弁護士の弁護活動の成果の如何にかかわらず返金されない費用です。
着手金という文字通り、着手金を支払わなければ、原則として弁護士は弁護活動を始めてくれません。
着手金は一括で支払うことを求められる場合が多いですが、中には分割での支払いにも対応している法律事務所もあります。
離婚裁判の着手金は30万円から50万円が相場です。
協議、調停の段階から弁護士に依頼している方は、追加で発生する着手金がいくらなのかしっかり確認しておきましょう。
報酬金
報酬金は、弁護活動の成果に応じて発生する費用です。
報酬金については「基礎報酬金」と「追加報酬金」の2段階設定とされていることもあります。
基礎報酬金とは、裁判結果の内容にかかわらず発生する、裁判が終了した場合に支払う報酬金のことです。離婚裁判の「基礎報酬金」の相場は20万円から30万円です。
追加報酬金とは、離婚裁判の結果に応じて支払う報酬金のことです。お金にかかわらない事項(離婚成立、親権獲得など)については「10~30万円」と固定の報酬金が設定されています。
他方で、お金にかかわる事項(養育費獲得、財産分与獲得、慰謝料獲得、年金分割獲得など)については「経済的利益(相手方に請求できる、と確定された金額のこと)×10~30%」とされている場合が多いです。
日当費
離婚裁判の日当費は主に、弁護士の裁判所への出廷など、事務所外で弁護活動を行った際に発生する費用です。
着手金と同様、「1回の出廷につき3万円」などと固定の金額が設定されていることが多いです。
したがって、離婚裁判で争う事項が多く、弁護士の裁判所への出廷の回数が多くなれば多くなるほど日当費は高くなります。
実費
実費は、弁護士が裁判所へ出廷するための交通費、相手方や裁判所、公的機関などとの文書のやり取りをするための郵送費、訴状に貼付しなければ印紙代(手数料)など、弁護活動によって実際に発生した費用です。
実費も結局は弁護士の弁護活動により変動しますが、当初「5万円」と固定の金額(基本必要となる実費)を設定しておき、弁護活動の内容によって追加の実費が発生するとしている法律事務所もあります。
弁護士費用を少しでも安く抑える方法
可能であれば、離婚裁判前の協議、調停で解決させることです。
離婚裁判に進むと弁護士の負担も大きくなる分、それに比例して弁護士費用の負担も大きくなります。
また、離婚裁判に進んだ場合でも、離婚裁判を長期化させないことです。
離婚裁判を長期化させればさせるほど弁護士費用は高くなります。離婚裁判を長期化させないためには、むやみやたらにあれこれ争わず、離婚裁判で決着をつけたい事項を絞ることです。
そのためには、難しいかもしれませんが、相手方に譲るところは譲る、譲れないところは譲らないという風にメリハリをつけた姿勢でいることが必要です。
離婚裁判費用と弁護士費用は誰が払う?
離婚裁判費用は誰が払う?
離婚裁判費用(印紙代・切手代等)は基本的には原告(裁判を申し立てた側)が負担します。ただしこの負担は”一旦支払う”という意味合いです。
民事訴訟法第61条では「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする」と規定されていますので、冒頭で述べた通り、離婚裁判で原告が全面勝訴すれば、原告が一旦支払った離婚裁判費用を被告に全額請求できます。
もっとも、実際の裁判では一方の全面勝訴・敗訴というケースは少なく、一部勝訴・敗訴といったケースの方が多いです。そのため、判決後に裁判官が、原告と被告の離婚裁判費用の負担割合を決めることが多いです。例えば、以下のように負担割合が決められます。
- 「訴訟費用は原告2割、被告が8割負担するものとする」
- 「訴訟費用は各自負担(折半という意味)するものとする」
弁護士費用は誰が払う?
「離婚の原因を作ったのは相手方にあるのだから相手方に弁護士費用を負担させたい」とお考えになる方も多いでしょう。
しかし、弁護士費用は自己負担なのが原則です。
そもそも、弁護士費用はご自身で弁護士に弁護活動を依頼したことによって発生した費用であって、相手方に弁護士費用を負担させるべき根拠がないといわざるを得ません。
もっとも、弁護士費用が相手方の不法行為によって負担せざるを得なかった費用、といえる場合は、例外的に、相手方に対して弁護士費用を請求することができます。
あなたが負担した弁護士費用は「不法行為」による「損害」であって、この損害分のお金を相手方に請求できるというわけです。交通事故で怪我した際に、加害者に対して損害賠償金を請求できるのと同じ考え方です。
相手方に弁護士費用を請求できる「不法行為」とは、たとえば、離婚の場合、不貞行為やDVなどです。不貞行為は、相手方があなた以外の人と肉体関係を持つことです。DVには、生命・身体に危害を加えるおそれのある行為のほか、心身に影響を与える言動も含まれます。
ただし、請求できる弁護士費用は、判決で出た損害賠償額の10%程度が目安です。全額は請求できませんので注意が必要です。
離婚裁判の費用を払えない場合の対処法
離婚裁判の費用を払えない場合の対処法は次のとおりです。
訴訟救援制度を活用する
まず、訴訟援助制度を活用することが考えられます。
訴訟援助制度とは、裁判を申し立てる際に必要な収入印紙代などの支払いを裁判所が猶予してくれる制度のことです。裁判を申し立てると同時に「訴訟上の救助申立て」を行い、裁判所に認められると、収入印紙代などの費用負担なしで裁判を提起することができます。
もっとも、申立てが認められるには、
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと
- 訴訟費用を支払う経済的余裕がないこと
が必要です。
裁判で全面敗訴した場合は、原則通り、猶予してもらった費用を負担する必要があります。
分割払いが可能な弁護士に依頼する
次に、分割払いが可能な弁護士に依頼することです。
弁護士費用は離婚裁判の費用とは別に払う必要があり、金額も決して安くはありませんから、離婚裁判を提起する場合は、できる限り弁護士費用の負担も軽くしたいところです。
そこで、弁護士費用の負担を少しでも軽くしたい場合は、着手金や報酬金を分割で支払っていくことを認めてくれる事務所に依頼するのも一つの方法です。
ホームページなどに明記されていなくても、相談時に希望していることを伝えれば柔軟に対応してくれる事務所もあります。
法テラスの民事扶助制度を利用する
次に、法テラスの民事扶助制度を利用することです。法テラスの民事扶助制度は「法律相談援助」と「代理援助」にわかれます。
法律相談援助は、一案件につき、1回30分の法律相談を3回まで無料で受けることができる制度です。代理援助は、弁護士が依頼者の代わりに相手との交渉や裁判の手続きをしてくれる制度で、弁護士費用は法テラスが依頼者に代わって立て替え払いし、後日、依頼者が法テラスに立替金を分割で返済していきます。
法テラスを利用しない場合に比べて弁護士費用が安くなるほか、少額でも分割での返済を認めてくれる点がメリットといえます。また、生活保護受給者に対しては返済を猶予または免除される制度もあります。
もっとも、誰でも利用できるわけではなく、年収が一定以下など要件を満たす必要があります。また、要件の審査に2週間から1か月ほどかかり、すぐに弁護活動に着手してくれるわけではない点にも注意が必要です。
法テラスの利用を検討されている場合は、期間に余裕をもって依頼した方がよいでしょう。
まとめ
離婚裁判で金銭的に負担しなければならないのは「離婚裁判費用」「弁護士費用」です。
弁護士費用は原則、自己負担、相手方に請求できたとしても全額の約1割程度でしょう。
離婚裁判費用は、全面勝訴すれば相手方に負担させることができますが、一部勝訴や和解の場合は一部負担しなければならない場合もあります。
離婚裁判を検討されている方はまずは弁護士に相談するとともに見積もりを出してもらいましょう。料金体系は事務所によって全く異なりますので複数の法律事務所に相談して比較するのも良いでしょう。
ただし費用が安いという理由だけで離婚弁士を選ぶと、経験不足や熱意のない弁護士にあたってしまうことも。相談時に本当にその弁護士に依頼すべきかどうか、親身に対応してくれるのかどうかを見極める必要があるでしょう。
当事務所は離婚裁判で多数の実績があり、依頼者が有利な条件で離婚できるよう、親身誠実に弁護士が全力で対応します。信用できる弁護士を探している方、費用をできるだけ抑えて弁護士に依頼したいとお考えの方は当事務所までご相談ください。お力になれると思います。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|