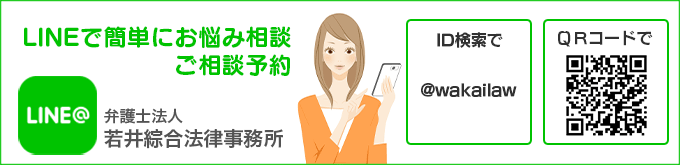離婚はあくまでも夫婦間の問題ですので、離婚によって夫婦関係が終了しても親子関係は残ります。親は未成熟の子に対して養育費を支払う義務があるため、離婚によって夫婦関係が終了しても、非監護親(離婚して子どもと別居している親)は監護親(子どもと同居している親)に対して養育費を支払わなければなりません。
とはいえ、
このようにお考えの方もいることでしょう。
結論から言いますと、養育費を払わないで逃げ続けていると、財産を差し押さえられたり、場合によっては刑事罰を受けることもあります。ただし、非監護親が無収入になった、監護親が再婚して子が養子縁組をした、子が成人したなどのケースでは養育費を払わなくて良い場合があります。また、非監護親の収入が減った、監護親の収入が増えたなどのケースでは減額が認められることもあります。
この記事では、養育費問題に強い弁護士が、
- 養育費を払わないとどうなるのか
- 養育費を払わなくても良いケース
- 養育費を減額できるケース
- 養育費の免除・減額を請求する方法
などについてわかりやすく解説していきます。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|
養育費を払わないとどうなる?
養育費は月々の分割支払いで合意することがほとんどです。そこで、監護親は扶養義務を果たすために入金していかなければなりません。では、この養育費の支払をせずにいるとどうなってしまうのでしょうか。以下で確認しましょう。
財産を差し押さえられる
養育費の支払い債務につき不履行があったとき、親権者は「債務名義」に基づき裁判所に強制執行を申し立て、支払義務者の「財産を差し押さえる」ことができます。
「債務名義」とは、強制執行(差し押さえ)を行う際に必要となる公的機関が作成した文書のことで、確定判決や調停調書、審判書、公正証書などが該当します。離婚時の養育費の取り決めに際して「公正証書」を作成し、その中に「強制執行認諾文言」が付記されている場合には、裁判所を通さずスピーディーに強制執行が行われてしまうリスクもあります。
差押えの対象となるのは、土地や建物等の不動産・家具や家電・貴金属等の動産・預金債権・現金などが挙げられますが、養育費の滞納による財産の差押えでは、「給与債権の差押え」が一般的です。債権者である親権者は給料の25%を差し押さえることが可能です。
そして、給与債権が差し押さえられた場合には第三債務者(会社)が債権者(親権者)に対して入金を行うことになります。この場合会社の経理を担当している同僚等に支払いが滞っている事実が把握されるという不利益を被ることになるのです。
刑事罰を受けることがある
養育費の未払いが続くと、債権者(養育費を受け取る側の親)は債務者の財産を差し押さえる前提として裁判所に財産開示手続きを申し立てることができます。財産開示手続きとは、裁判所が債務者(養育費の支払い義務者)を呼び出し、どのような財産を有しているかを質問したり、開示させたりする手続きです。
これまでは、財産開示手続きに非協力的な債務者に対しては、行政罰である科料(上限30万円)しか科すことができませんでした。つまり、刑事罰の対象ではなかったのです。
しかし、2020年4月に民事執行法の改正が実施され、債務者が財産開示手続きで裁判所からの呼び出しを無視した場合や、財産の内容につき虚偽申告をした場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられるようになりました。これは刑事罰ですので、有罪になれば前科がつくことになります。
養育費の未払いくらい大した問題ではないだろう…と高をくくっていると、最悪のケースでは刑務所で過ごすことになりますし、就業規則により勤務先の会社を解雇され、前科がつくことで資格制限(保有資格の停止・剥奪等)を受けることもあるのです。
参考:養育費の確保-厚生労働省
養育費を払わなくてもい良いケース
夫婦間の同意で取り決めたとおりに養育費を負担していても、いつどこで自分の経済状況が悪化するかは分かりません。もし突然、失業したり事業が失敗したりして収入が途絶えた場合どう対処したらよいのでしょうか。ここでは養育費の性質から支払わなくてもよくなる場合を複数説明します。
支払義務者に収入がない場合
扶養義務は「生活保持義務」といって、自己と同程度の生活を保障する義務です。自分の生活水準を下げても負担が必要なケースがある反面、生活水準を超えて子に良い生活環境を提供する必要はありません。したがって、支払う側の収入がゼロまたは生活するのにギリギリだった場合、支払いを強制することはできません。
しかし、リストラされ失業したケースで、健康や体調面に問題がなく再就職ができる場合には、あなたの意思に応じて働いて収入が得られるといえるので、支払義務は免除されないでしょう。
再婚相手と子どもが養子縁組した場合
受け取る側が新たに結婚して再婚相手が子と普通養子縁組した場合、支払う側の扶養義務は二次的なものとなります。
養子縁組により第一義的に子を扶養する責任は再婚者に移るため、支払義務は免除・減額の可能性があります。
しかしあなたの扶養義務が完全に消滅するというわけではないので注意してください。
例えば、再婚相手の給与が低額で子どもを満足に扶養することができない場合には、不足する金額をあなたが支払う必要があるでしょう。
なお、このケースで重要なのは再婚者と子どもとの間に法的に「親子関係」が生じている点です。
受け取っていた親が再婚したというのみで直ちに親子関係が生じるわけではありません。
したがって、親権者が再婚したといって、養育費の支払いを勝手にストップすると前述のように「財産の差押え」のリスクがあります。
扶養に関する取り決めについては相手が再婚した場合でも、まずは両親間でしっかりと話し合って決めていくことが重要です。
親権者が養育費の支払い免除について同意した場合
離婚する場合、養育費や親権の帰属、財産分与等については基本的には夫婦間の協議で決定するため、養育費を請求しないと相手方が同意すればそのような協議も有効です。
しかし、相手の同意は真に配偶者の意思に基づきなされる必要があるので錯誤・脅迫・詐欺による意思表示は取り消される可能性があります。
また、配偶者が養育費の請求権を放棄したとしても、子ども自身も養育費を請求する権利を有しています。そこで、事後的に子どもがあなたに対して養育費支払いを請求した場合にはあなたには支払う義務が発生しまので要注意です。
子供が経済的に自立した・結婚した
親が子どもに対して負っている扶養義務は、子どもが未成熟である期間について負っている義務です。
したがって、子どもが就職して経済的に自立した場合には未成熟であるとは言えませんので養育費の支払い義務はなくなります。
また子どもが結婚した場合にも同様です。ここで子どもが専業主婦になった場合であっても経済的に自立したことには変わりないと考えられています。
したがって、養育費の支払義務も子どもが結婚した時点で支払う必要がなくなると考えられています。
養育費を減額できるケース
「支払いの減額」であれば、正当な理由があれば支払いの免除よりも認められやすいです。
受け取る側の収入が増えた場合
養育費を受け取る親権者の収入・資産が増加した場合、減額を請求できます。前述のように扶養義務の内容は、父親と母親両方の収入をベースに算定されるため、片方の収入・資産が増加した場合には他方の負担の軽減が認められるのです。
ただし、必ずしも減額が認められるとは限らない点に注意が必要です。例えば、
- 離婚協議の段階で、親権者が将来収入を得る見込みを前提として合意された
- 増収しても子どもを扶養するのに十分ではない
と判断される場合には減額が認められない可能性が高いです。
支払う側の扶養家族が増えた場合
養育費を支払う側が再婚した場合、扶養義務を負う家族が増えることになります。それにより経済的な負担が増えることに配慮して支払額が減額される可能性があります。
ただし注意が必要なのは、支払う側が再婚したことから直ちに支払いが軽減されるわけではない点です。養育費の減額が認められやすいのは、
- 支払う側が再婚して子どもが生まれた
- 支払う側の再婚相手に子どもがいて、養子縁組をした
という場合です。
扶養家族が一人増えると金銭的な負担は大きなものになることが通常ですので、養育費の支払いに困っている場合には養育費の減額請求をすべきでしょう。
支払義務者の収入が減った場合
先ほど支払義務者の収入が減った場合であっても養育費支払義務が免除される可能性は限定的であると説明しました。しかし、免除と比較して減額が認められるのはそこまで難しくはありません。会社を解雇された場合や怪我・病気による退職などの失業の場合や、会社や自営業の経営不振により減収した場合にも養育費の減額については認められる可能性があります。
養育費の減額が認められる4つの条件|具体的な減額方法とその流れ
養育費の減額・免除の請求方法
相手方と話し合って減額・免除を交渉する
収入が減少した場合やご自身が再婚して扶養義務を新たに負った場合などには、これまでの約定どおり養育費を支払うことが経済的に困難になります。
離婚の際に父母双方が協議で決めたことを変更する場合には、まずは親権者である相手方と話し合うことが必要でしょう。
相手方が養育費の減額・免除に合意してくれる場合には、養育費支払い義務を軽減することが可能です。
ポイントとして合意した内容については、必ず合意書を作成し、養育費を減額・免除したことを客観的に分かる形で残しておきましょう。なぜなら、このように書面を残しておかないと事後的に「そのような合意は存在していない」と主張され未払いの養育費を一括で請求される事態に陥るおそれもあるからです。
養育費減額調停を申し立てる
相手方と交渉しても、相手が養育費の減額・免除に納得しない場合や、話し合いに応じようとしない場合などには、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てていくことになります。
調停は裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話し合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る制度です。
調停手続きでは、家庭裁判所の裁判官1名と民間の良識ある人の中から選ばれ調停委員2名で構成される調停委員が、当事者双方の間に入って事情や意見を聞きながら話し合いを進めていくことになります。
当事者双方が納得して合意に至った場合には、合意された内容を書面にして調停は終了することになります。話し合いがまとまらない場合には調停は不成立(不調)となり終了します。
この場合も裁判所が当事者のさまざまな事情を考慮して調停に代わり審判の形で結論が示されることになります。
審判に対して2週間以内に当事者から異議が申し立てられることなく確定した場合、審判は確定判決と同一の効力を持ちます。異議が申し立てられた場合には、審判は効力を失うことになります。
養育費調停の流れと費用|調停のメリットを最大化する5つの重要点
養育費を払わないことに関するよくある質問
養育費を払わない人の割合は?
離婚後に養育費が支払われていないケースは決して少なくありません。
厚生労働省が公表してる令和3年全国ひとり親世帯等調査結果報告には、母子家庭の母の養育費の受給状況は以下のようになっています。
- 現在も養育費を受けている世帯:28.1%
- 養育費を受けたことがある世帯:14.2%
- 養育費を受けたことがない世帯:56.9%
以上のように過半数の母子家庭世帯では、一度も養育費を受け取ったことがないと回答しています。さらに養育費の取り決めをしていると回答した世帯は全体の46.7%で、養育費の取り決めもしていないと回答した世帯が51.2%と過半数を占めています。
養育費の支払いは離婚した場合も親に課されている法的な義務であるにもかかわらず、半分以上の世帯でその取り決めも受給もされていないというのが現状です。
離婚した配偶者がDV夫で危害を加えられる可能性がある場合や、母子世帯のみで十分な稼ぎがある場合などには養育費の取り決めができない・必要がないというのも理解できます。
しかし母子世帯の母の養育費の取り決めをしていない理由として、「相手と関わりたくない(50.8%)」または「取り決めの交渉がわずらわしい(19.4%)」という理由だけで半数を超えます。これに対して、「相手から身体的・精神的暴力を受けた(15.7%)」や「自分の収入で経済的に問題がない(7.3%)」という理由は少数派です。
養育費が支払われているか否かは、子どもの学費や衣食住などの生活費に大きな影響を与えることになるため子どもの進学や将来を左右することになります。
したがって親権者としては、「関わりたくない」「わずらわしい」というだけの理由であれば子供の将来のことを考えて、相手方と適切に話し合って養育費の支払いを約束してもらうようにすべきでしょう。
公正証書がある以上は養育費を払わない方法はない?
公正証書で養育費の取り決めをしておくと、強制執行の手続きがスムーズに行えるようになります。
強瀬執行とは、債権者(養育費の支払いを請求する側)が債務者(養育費を支払う義務がある側)に有している債権(養育費支払請求権)を、国が強制的に実現するためのものです。公正証書に「執行認諾文言」を付しておくことで、訴訟を提起することなく強制執行の申し立てをすることができるのです。
しかし、このような公正証書があるからといって養育費を支払わない方法がないわけではありません。
公正証書で養育費の取り決めをしたとしても、以下のような事情変更によって減免が認められる可能性はあります。
- 親権者が再婚し、再婚相手が子どもを養子とした
- 養育費支払義務者が再婚し、再婚相手との間に子どもが生まれた
- 養育費支払義務者が再婚し、再婚相手と連れ子と養子縁組をした
- 子どもが経済的に自立(就職・結婚)したため未成熟子とは言えなくなった など
まとめ
養育費というものは、離婚したとしても子どもが経済的に自立するまでは親が負担すべき義務です。
しかし、その支払い期間は十数年にわたる長期的なものですので、その間あなたにどのような変化が発生するかは誰にもわかりません。
「経済状況が悪くて養育費が支払えない」と困っている場合には放置してはいけません。
適切な解決策を模索することで経済状況が改善する可能性もあります。
ご自身のケースで養育費の支払義務について見直すことができる余地があるのかどうか、免除や減額を受けることができるかどうか、一度法律の専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士に相談することで適切なアドバイスと法的なサポートをうけることができるでしょう。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|