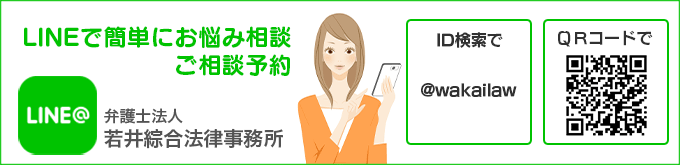養育費については離婚する際に取り決めが行われることが一般的です。しかし、子どもが幼い場合には将来に起こるさまざまな事情を反映して支払い約束ができるわけではありません。
養育費を受け取っている親権者の中には、
という疑問を抱いている方もいらっしゃることでしょう。
そこでこの記事では、
- そもそも養育費を事後的に変更することはできるのか
- 養育費の増額を請求できるのはどのような場合か
- 養育費増額を請求する具体的な手続き など
について、養育費問題に強い弁護士解説していきます。
養育費について増額をして欲しいと悩まれている親権者の方は是非この記事を参考にしてご自身のケースではどうなのかを考えてみてください。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|
目次
そもそも養育費の増額は認められるのか?
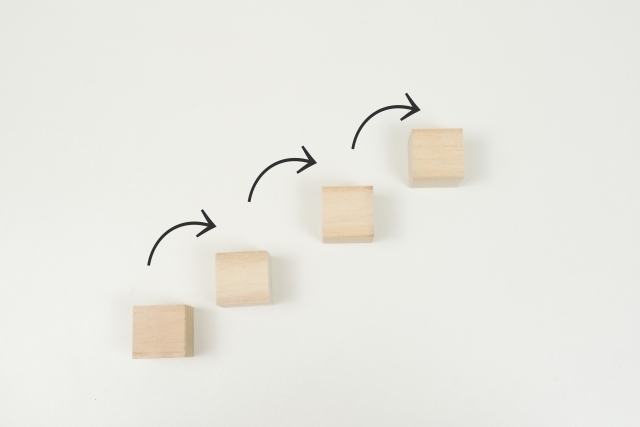
養育費の法的性質
まず「養育費」とは、生活するために必要な経費・教育費・医療費など子どもの監護や教育のために必要となる費用全体を指します。
この扶養義務は法律の規定に基づき親に課されている義務です。
民法には「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある。」と規定されています。(民法第877条1項)
「直系血族」には親と子の関係が含まれ、実子か養子かで違いはありません。
「扶養」には未成熟子の「生活保持義務」が含まれていると考えられています。
この「生活保持義務」とは親と未成熟子間や夫婦間のように一体的な共同生活関係がある場合には扶養義務者は「自己と同程度の生活を保障する義務」を負うと解釈されています。
一方で夫婦・子ども以外の親族については、自分が社会的地位にふさわしい生活を営んで「なお余裕がある場合に」相手方の最低限度の生活を保障する扶養を行えば足りると考えられていることとは対照的です。
なぜ子どもや配偶者には生活保持義務のような高いレベルの義務が求められているのかというと、子どもや配偶者の生活は「自己の生活の一部」として保障するのが相当であると考えられているからです。
夫婦関係は離婚によって消滅してしまいますが親子関係は離婚によっても消滅しませんので、養育費支払い義務は離婚により親権者で亡くなった親も負担しなければなりません。
したがって、離婚後も親権者でなくなった親は養育費の支払合意に基づいて親権者である親に対して不足する養育費を支払わなければならないのです。
養育費算定の方法
そして養育費の具体的な金額は離婚する際に父と母の合意によって決定することができます。
ただし、実務上「養育費算定表」に基づいて算定されることが一般的です。
この算定表は「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」をテーマに東京と大阪の家庭裁判所の裁判官により公表されている表です。
この算定表は裁判所のホームページで公表されていますのでどなたでも自由に参照することが可能です。
この算定表を利用すれば、父・母双方の年収、子どもの年齢と人数をあてはめてご自身のケースでの養育費や婚姻費用の相場が算出することができるのです。
事後的に養育費の増額請求をすることができるのか
養育費は離婚する際にその具体的な内容が決められます。
当事者同士の話し合いや調停・審判などで一度決まった養育費の内容を変更することは容易ではありません。
基本的には養育費の支払義務者である非親権者の同意がなければ事後的に金額を変更することは難しいでしょう。
しかし、相手方が簡単に増額に同意しない場合であっても「正当な事情変更」がある場合には増額が認められる場合があります。
以下どのような場合に養育費の増額請求が認められやすいのかという点を詳述していきましょう。
養育費の増額が認められやすいケース

離婚する際に協議や裁判所の手続で内容が取り決められた養育費であっても、その後に予測していなかった収入の増減、必要経費の増加などが遭った場合には養育費の増額または減額が請求できます。
それではどのような事情変更があれば養育費の増額が認められるのでしょうか。養育費の増額が認められやすいのは以下のようなケースです。
①子どもが進学するため授業料等がかかる場合
子どもの進学にともなって授業料やテキスト代など教育費が増えた場合には養育費の増額請求が認められる可能性があります。
ただし前述の「養育費算定表」では一般的な教育費は既に考慮され算定金額の中に組み込まれています。ここでいう「一般的な教育費」とは公立中学校や公立高校に進学した場合に必要となる教育費のことです。
したがって、これを超える部分については養育費が不足することになりますので不足分を支払義務者に分担請求することができます。
具体的に不足するものとして考えられるものは、私立中学校や私立高校、4年生大学や専門学校への進学に必要となる教育費です。
なお養育費の支払いについて決定された際に進学について承諾・同意しているといえる場合に増額が認められます。
つまり明示的に私立高校への進学や大学進学について反対していた場合にはそれを前提として養育費の支払内容が決定されているとして認められない可能性も高いでしょう。
②子どもが病気・負傷したことで医療費がかかる場合
子どもが疾病や怪我を負ったことによって不測の医療費が必要となった場合には養育費の増額請求が認められる可能性があります。
継続して通院が必要となったり投薬治療やリハビリが必要となったりした場合には、養育費全体の合意内容を変更して、必要となる医療費負担分を上乗せした内容に改めることが相当だと考えられます。
ただ、一時的な怪我や疾病の場合には医療費が必要となったとしても養育費全体の内容を改める必要はなく別途一時的な援助を取り決めればよい場合には養育費の増額までは認められない可能性が高いです。
③親権者の側の収入が大きく減ってしまった場合
養育費の支払いを受ける側である親権者の収入が大幅に減ってしまった場合には相手方親に分担を求めることができます。
養育費は父と母双方の収入額に応じて決定されますので、親権者の収入が大幅に減少してしまった場合には他方の親の分担割合が増える場合があります。
収入の減少として認められる場合は、病気・精神疾患・怪我などで親権者が働けなくなった場合や子どもや親の監護・介護で継続的に働けなくなったような場合でしょう。
ただし収入が減った場合であってもそれが一次的な減給の場合には増額請求が認められない可能性が高いです。会社を解雇・退職した場合であっても自己都合の場合や再就職の意思や能力がある場合には増額する必要性が否定されることも考えられます。
④支払義務者の収入が大きく増えた場合
養育費の支払義務者の収入が大きく増えた場合も養育費の増額が認められる可能性があります。
支払義務者の扶養義務は前述のような生活保持義務ですので、「自己と同等の生活を保障する義務」です。そのため非親権者の収入が大幅に増大した場合には自己の生活レベルの上昇に対応する養育費を負担しなければなりません。
養育費を増額させる手続きの流れを解説

協議・書面による請求
まず養育費の増額を求めたい場合には支払義務者である非親権者と任意での話し合いを行いましょう。
この話し合いの時点で相手が納得して増額請求に応じてくれた場合には手続きはスムーズに進みます。養育費の増額請求は子どもの将来のためになされるものです。
父母間の怨恨は脇において、子どものために必要である合理的な理由を、説得力を持って説明できれば相手方も応じてくれる可能性は決して低くはないでしょう。
相手が拒否して話し合いではまとまらない場合、書面を用いて請求していきます。
この場合「内容証明郵便」を利用して増額請求していきます。内容証明郵便とはいつ・いかなる内容の文書を・誰から・誰あてに差し出されたかということを日本郵便株式会社が証明してくれる郵便サービスです。
あなたが増額請求した事実が証拠によって証明できますので増額請求に応じない場合には法的手段に出るという間接的な意思表示にもなります。
内容背証明郵便を送付するのは電話やメールでの話し合いがまとまらなかった場合の次の手段として有効でしょう。
養育費増額請求の「調停」の申し立て
養育費について父母の話し合いで合意できない場合には非親権者が居住している地域を所轄する家庭裁判所に養育費増額請求の「調停」を申し立てることになります。
調停手続きとは「家事審判官」と呼ばれる裁判官と民間から選出された「調停委員」が当事者の間に介入してそれぞれの言い分を聴きながら話し合いにより妥当な解決を目指す手続のことをいいます。
調停委員には様々な分野における専門的な経験を有する一般人の中から選ばれています。
養育費増額請求の「審判」
調停では話し合いがまとまらず不成立になった場合には自動的に審判手続きが開始されます。裁判官が一切の事情を考慮して審判をすることになります。
弁護士に依頼
養育費の増額に関する話し合いや調停・審判はもちろんご自身で進めることもできます。
しかし、法律の専門家ではないあなたが時間を割いて手続きや内容を調査しながら妥当な結論を勝ち取ろうとするのは至難の業でしょう。
そこで法律の専門家である弁護士に手続きの早い段階から相談・依頼しておくことが良いでしょう。
弁護士に依頼することで適切な法的サポートと助言を受けることもできますし、相手方も真剣に交渉に応じてくれる可能性が高くなります。また裁判手続についても裁判所を説得したり適切な主張・証拠を提出することでご希望通りの結果に近づけることができます。
まとめ
今回は養育費の増額が請求できる場合やその手続について解説しました。一度決定された養育費についても事後的な事情変更があれば変更を請求することができます。
養育費の増額について悩まれている方は是非一度養育費や離婚問題に精通した弁護士にご相談ください。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|