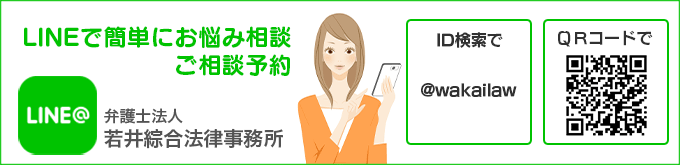- 養育費は課税対象になる?
- 養育費を払っている親は扶養控除を受けられる?
結論から言いますと、原則的には、養育費は課税対象になりません。また、養育費を払っている親は扶養控除を受けられます。
この記事では、養育費問題に強い弁護士がこれらの疑問を解消していきます。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|
目次
養育費を受け取ると税金を納めないといけないのか?

個人が何らかの原因で現金や財産を受け取った場合には所得税や贈与税などの各種税金を納める義務が発生するのが一般的です。
しかし、原則的には、養育費は課税の対象にはなりません。
そもそも養育費とは、扶養義務にもとづき、子と離れて暮らすことになった親(非監護親)から子と暮らして監護する親(監護親)に対して支払われる、未成熟の子を監護・教育するために必要な費用のことです。つまり、養育費はあくまでも「子が健やかに成長するためのお金」ですので、受け取った監護親の収入と見做されて課税されることはないのです。
養育費に税金がかからないことを法律の条文でも確認しておきましょう。
所得税法では、次に掲げる所得については所得税を課さないと規定されています。
「学資に充てるために給付される金品~(省略)~及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品(所得税法第9条1項15号)」。
養育費を支払っている非監護親は、収入(会社員であれば給与)を得た際に既に所得税を払っています。そのため、その収入から子の学費や医療費などの生活費(養育費)を支払っていることを考えると、監護親が受け取った養育費に改めて課税する必要はないと判断されるのです。
また、相続税法では、次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しないと規定されています。
「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの(相続税法21条の3第1項第2号)」。
このように、子どもに生活費・医療費・教育費がしっかり提供されるよう、養育費から税金として差し引かれることがないように配慮されています。
以上から、養育費には所得税や贈与税の税金がかかることは原則としてありません。
ただし、贈与税については例外がありますので以下で解説していきます。
養育費が課税対象となる例外

離婚に伴う養育費の支払いを一括で受け取った場合には贈与税がかかることがあります。
贈与税の非課税財産について規定されている相続税法21条の3第1項第2号の条文をもう一度確認してみましょう。
(贈与税の非課税財産)
第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
(前略)
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
養育費を一括で受け取る場合には額も大きくなる可能性が高いでしょう。そのため、事案によっては金銭の支払段階で子どもの養育に”通常必要な額を超える”として贈与税の課税対象となる可能性があります。
国税庁「相続税法基本通達21の3-5」によれば、贈与税の非課税財産について以下のように示しています。
21の3-5 法第21条の3第1項の規定により生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする。(平15課資2-1改正)
これによると、養育費を「必要な都度」、つまり月払いで受け取っていた場合には課税されないが、養育費を一括で受け取った場合は「必要な都度」を超え、贈与税が課税される可能性があります。
また、生活費や教育費として受け取った養育費を預貯金や株式購入などに回した場合は、その養育費は贈与税の課税対象になる可能性もあるということです。
一括で養育費を受け取るといくら税金がかかる?
養育費は親から子どもに支払われる金銭なので一般贈与財産として計算します。この場合以下のような速算表に基づき贈与税を算出します。
| 基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1000万円以下 | 1500万円以下 | 3000万円以下 | 3000万円超え |
| 税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | - | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
贈与税の計算はその年の1月1日から12月31日までの1年間で贈与され財産の価額を算出したのち、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。次にその残額に税率を乗じて税額を計算します。
例えば一括で500万円の養育費を支払った際にそれに贈与税が課された場合を考えてみましょう。
基礎控除後の課税価格は 500万円-110万円=390万円 と算出されます。
贈与税額の計算は 390万円×20%-25万円=53万円 となりますので53万円の贈与税を納めなければなりません。
養育費を支払う親は「扶養控除」が受けられる?

扶養控除とは
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族にあたる者がいる場合には一定の金額の所得控除を受けることができます。このような税制上の有利な取扱いを「扶養控除」といいます。
行政解釈(扶養親族|国税庁)ではその年の12月31日の状況で以下の4つの要件のすべてにあてはまる人を「扶養親族」として取り扱っています。
- ①6親等内の血族および3親等内の姻族(これを「親族」といいます。)で配偶者以外のもの又はいわゆる里子(都道府県知事から教育を委託された児童)や市町村長から養護を委託された老人
- ②納税者と生計を一にしている
- ③年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前については合計食金額が38万円以下)
- ④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払をうけていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
離婚後別居していていても「生計を一にしている」といえるか
親に監護されている年齢の子であれば、上記の①、③、④の要件を満たしていることがほとんどでしょう。しかし、非監護親(子と別居して養育費を振り込んでいる親)が扶養控除を受けたい場合に、別居している子が「②納税者と生計を一にしている」と言えるのか疑問が生じてきます。
この点「生計を一にする」とは、必ずしも同じ家で同居していることを指すものではなく、所得税法基本通達2-47によると次のような場合も含まれるとされています。
- 家族と日常的に同居していない親族であっても、勤務・修学・療養などの余暇には他の親族のもとで生活をともにすることが常例となっている場合
- 親族間で、常に生活費、学資金、療養費などの送金が行われている場合
- 親族が同一の家屋で生活を共にしている場合(明らかに互いに独立した生活を営んでいるといえる場合を除く)
そして離婚にともなう養育費の支払いが次の2つにあたる場合には「生計を一にしている」と認められています。
- ①扶養義務の履行として金銭が支払われていること
- ②一定の年齢までに限定して金銭が支払われていること
なぜなら、①②を満たす場合には離婚に伴う養育費の支払いが、上記で説明した「常に生活費、学資金、療養費などの送金が行われている場合」に該当するとして非親権者と子どもは「生計を一にしている」と認めることができるからです。
扶養控除が受けられる金額について
「扶養親族」のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の者を「控除対象扶養親族」といいます(所得税法第2条1項34号の2)。さらに、「控除対象扶養親族」のうち年齢が19歳以上23歳未満のものを「特定扶養親族」といいます(同条項34号の3)。
そして、扶養控除により控除が受けられる金額については、「控除対象扶養親族」と「特定扶養親族」によって以下のように異なります。
| 控除対象扶養親族 | 特定扶養親族 | |
| 所得税 | 38万円 | 63万円 |
| 住民税 | 33万円 | 45万円 |
養育費を払っても扶養控除が受けられないケース

以下で解説する3つのケースでは、養育費を負担していても扶養控除を受けることができませんので注意が必要です。
16歳未満の子どもを扶養している場合
子どもが16歳未満の場合には扶養控除の対象となりません。
なぜなら「年少扶養控除廃止」がなされたからです。かつては0歳〜16歳の子どもについても年少扶養控除として扶養控除が認められていましたが、2012年の改正でこの制度が廃止されてしまいました。
ただし年少扶養控除廃止の代わりに16歳未満の子どもは、養育費の補助として児童手当を受給することができます。
親権者と扶養が重複している場合
確定申告での扶養控除は、両親のうちどちらか一方のみに適用されるため、親権者と養育費支払義務者である親の両方が扶養控除を申請することはできません。
ケースによっては養育費の支払いを負担している非監護親だけではなく、子どもと同居して暮らしている監護親も子どもを扶養しているという場合があります。この場合、両親が重複して扶養控除を申請することはできません。
ここで、子ども一人に対して2人の親が扶養控除を申請しなければ問題はありません。つまり、養育費を負担している親の扶養親族に長男を、子どもと同居している監護親の扶養親族に次男を設定しておけば2人とも扶養控除を受けられるように調整はできます。
一括で養育費を支払う場合
一括で養育費を支払う場合には、原則として扶養控除を申告することができません。
扶養控除を受けるためには子どもと養育費扶養義務者が「生計を一にしている」という要件を満たす必要があります。そして別居している親子が「生計を一にしている」と言えるためには、「親族間で、常に生活費、学資金、療養費などの送金が行われている」ことが必要であることは前述した通りです。
しかし、養育費を一括で払うことは、”常に~送金が行われている”ことにはなりません。したがって、養育費を一括で支払った場合には原則として扶養控除の申請をすることができません。
ただし、養育費が一時金・一括で支払われる場合であっても、子どもを受益者とする信託契約(一括で支払われた養育費を信託銀行が預かり、信託銀行を経由して、養育費として定期的に子供に支払っていく契約)により養育費に相当する給付金が継続的に給付されているときには、扶養控除の対象とすることができます。なぜなら、その給付がされている各年について「常に生活費等の送金が行われている場合」に該当していると考えられているからです。
また、信託契約の契約解除については、元夫と元妻の両方の同意を必要とするものに限定されていますので、養育費の支払いを確保できるというメリットもあります。
養育費の扶養控除を受けるための手続き

養育費の扶養控除を受けるための手続きは会社員の方とフリーランスの方で異なります。
まず会社員の方は年末調整を行うため、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を会社に提出することになります。同申告書には「控除対象扶養親族(16歳以上)」に記入する必要があり、子どもの名前や申告者との続柄、子どもの生年月日・個人番号・住所や居所、子どもの所得の見積額を申告する必要があります。
添付書類として必要となるものは以下のようなものです。
- 勤労学生控除を受ける場合には、勤労学生に該当する旨を証する書類 1部
- 源泉徴収において非居住者である親族に係る扶養控除を受ける場合には、その親族に係る親族関係書類 1部
- 年末調整において非居住者である親族にかかる扶養控除を受ける場合には、その親族に係る送金関係書類 1部
次に個人事業主やフリーランスの方は、「確定申告」手続き内で扶養控除を申告することができます。具体的には、確定申告書の第一表にある「所得から差し引かれる金額」の扶養控除の箇所と、第二表の「配偶者や親族に関する事項」に記入するだけで申告することができます。
第一表には申告する扶養控除の金額を記入します。第二表には、扶養する親族をすべて記入し、扶養控除を受けるには子どもの氏名・個人番号・続柄・生年月日を記入する必要があります。住民税の欄には子どもと別居しているため「別居」の箇所に印をつける必要があります。
まとめ
今回は養育費を受け取る側と支払う側双方について税金の仕組みについて概要を解説してきました。
受け取る側は原則として税金が課されることはありません。他方、支払う側は一定の要件を満たすことで扶養控除のメリットを受けることができます。
ご自身のケースで実際にどのような税制上の措置が取られるのか判断が難しいという場合には税務署に確認したり税理士・弁護士に相談したりすることも検討してみてください。
ご自身の事案で具体的にどのように処理されるのかという点についてアドバイスを受けることができるでしょう。
誰でも気軽に弁護士に相談できます