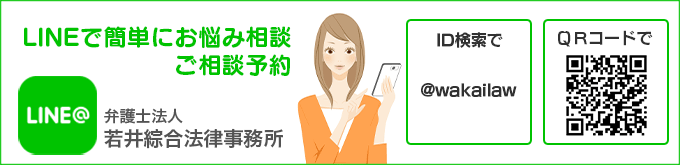協議離婚では、離婚届を市区町村役場に提出して初めて離婚が成立します。
裁判離婚(調停・審判・判決など)の場合は、調停成立や、審判・判決の確定で離婚は成立しますが、報告的に離婚届の提出が義務付けられています。
つまり、どのような方法で離婚した場合でも、離婚届の提出は必須なのです。
とはいえ、
- 離婚届の書き方がわからない…
- 離婚届を出す際に、ほかに必要な書類はあるのだろうか…
といった不安を抱えている方もいることでしょう。
そこでこの記事では、離婚問題に強い弁護士が、離婚届の書き方や必要書類についてわかりやすく解説していきます。
離婚届の記入例や、必要書類の一覧表も載せてありますので、初めて離婚届を書くので不安…という方も、安心して最後まで読んでいただけると思います。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|
目次
離婚届を書き始める前に決めておくべき2つのこと

いざ、離婚届を書き始めても、以下の2点を事前に決めていないと、書く手が止まってしまい効率が悪くなります。書き始める前に必ず決めておきましょう。
- ①未成年の子がいる場合、親権者を誰にするのか
- ②戸籍をどうするのか
①親権者を誰にするのか
夫婦の間に未成年の子供がいる場合、離婚後どちらが親権者になるかを、離婚前に決めておかなくてはなりません。離婚届を提出するに際して親権者をどちらにするかが決まっていない場合には、離婚届が受理されないからです。
夫婦の協議で親権者が決まらない場合は、家庭裁判所の調停や審判に頼ることになります。しかし、それにより親権者にならなかった方の親が、「であれば離婚に応じない」という態度をとってくることもあるでしょう。その場合は、離婚裁判を提起して、裁判所に親権者を判断してもらう必要があります。
②戸籍をどうするのか
一般的には、結婚に際して妻が夫の戸籍に入ることが多いため、それを前提にすると、離婚が成立した場合、妻は夫の戸籍から抜けることになります。夫の戸籍から抜けた場合、妻の戸籍をどうするのかに関しては、妻の選択に従いつぎの2つのパターンが認められています。
以前の戸籍にもどる
離婚した場合、原則として結婚前の戸籍にもどることになります。一般的には、結婚前の両親の戸籍にもどるパターンが多いでしょう。
ただし、離婚後子供を引き取り自分と一緒の戸籍に子供を入れたい場合には、このパターンを選択することはできません。戸籍の中には、親子二世代までしか入れないというルールがあるためです。子供を自分と同じ戸籍に入れるには、以下で説明する、新しい戸籍を作らなくてはなりません。
新しい戸籍を作る
離婚後、婚姻前の戸籍にもどらず、妻だけの戸籍を新しく作ることも可能です。
離婚に際して子供を引き取り、その子供を自分の戸籍の中に入れたい場合には、こちらを選択しなければいけませんので、ご注意下さい。
離婚届のもらい方

離婚届は、各市区町村役場の戸籍課(戸籍係)または市民課、その他、出張所でも貰うことができます。なお、戸籍法で様式が定まっているため全国共通です。つまり、自分の住んでいる地域以外の役場や出張所で貰ったものでも構いません。また、土日祝日や夜間であっても、役場の夜間・休日窓口や宿直室に行けば貰うことができます。
また、ネットからダウンロードすることもできます。ただし、離婚届の用紙はA3サイズですので、一般的な家庭用プリンターでは印刷できないことが多いでしょう。その場合は、A4で印刷したものをコンビニの業務用プリンターでA3サイズに拡大印刷するか、ダウンロードしたPDFファイルをUSBメモリなどのメディアに入れ、同じくコンビニの業務用プリンターに繋いで印刷すると良いでしょうお。なお、離婚届は白黒でも構いませんので、わざわざ高い料金のカラー印刷をする必要はありません。
離婚届の書き方
【離婚届記入例(左側)】
.jpg) 【離婚届記入例(右側)】
【離婚届記入例(右側)】
.jpg)
以下では、離婚届の書き方を、上の、記入例の画像に沿って解説していきます。
また、離婚届を書く際には、以下の注意事項に必ず目を通してから書き始めるようにしてください。
- 鉛筆や消せるタイプのペンなどは使用不可です。通常のボールペンやサインペンで書きましょう。
- 修正ペンや修正テープの使用不可です。書き損じた箇所は二重線を引き、訂正印を押しましょう。
- 印鑑はシャチハタ使用不可です。認印は可です。
- 夫婦で同じ印鑑を用いるのは不可です。姓が同じでも別々の印鑑を使用してください。
- 離婚届で用いる印鑑は夫婦各1種類のみです。訂正印や捨て印を押す際も、届出人欄で押印した印鑑と同じものを使用して下さい。
①届出をする日付
離婚届への記入日ではなく、実際に届け出る日を記入します。離婚届を書く段階でまだ提出日が明確に決まっていない場合には、とりあえず空欄のままでよいでしょう。その場合には、実際に役所に提出する日またはポスト投函する日(離婚届を郵送する場合)に、忘れず日付を記入するようにしてください。
なお、離婚届を届出して受理された日が「離婚成立日」となります。窓口提出の場合は受理されたその日が離婚成立日となりますが、郵送の場合は、離婚届が役所に届いて受理された日が離婚成立日になります。離婚届の記載内容に不備があると不受理となり、離婚が成立しませんので、離婚届を書く際は慎重に一つずつ埋めていくようにしましょう。
②離婚届提出の宛先
この場所には、実際に届出をする市区町村の名前を記載することになります。たとえば、東京都の千代田区役所に提出する場合には「千代田区長殿」と記載します。
③氏名・生年月日
名字(氏)は、調停などによってすでに離婚が成立している場合であっても、婚姻中に名乗っていたものを記載してください。
④住所・世帯主
現時点で住民登録をしている住所と世帯主を記入してください。夫婦が既に別居している場合はそれぞれ異なった住所と世帯主の記入が必要です。住民票の記載どおり、都道府県名から省略なしで正確に記入しましょう。
⑤本籍・筆頭者の氏名
婚姻中の本籍地と筆頭者を記入します。「筆頭者」とは、戸籍の一番初めに氏名の書かれている人のことを言います。書き間違いのないよう、戸籍謄本を見ながら書くと良いでしょう。
⑥父母の氏名・父母との続き柄
父母の氏名欄には、実父母の氏名を書きます。父母が婚姻中であれば、父の欄には氏名を、母の欄には「氏」を省略して「名」だけ記入してください。また、父母の双方、または、一方が既に亡くなっている場合でも、この欄は記入が必要です。
続き柄については、「長男・二男・三男」「長女・二女・三女」などと記載します。「次男」「次女」は正式な表記ではないので注意しましょう。
なお、養父母がいる場合は、「⑱その他」の欄に、養父母の氏名と続き柄を記入します。
⑦離婚の種別
協議離婚以外の離婚の場合には、それぞれ法律上離婚が成立した日付も記入する必要があります。
離婚が調停や和解離婚、認諾離婚で成立した場合には、裁判所によってそれぞれの調書が作成された日付が離婚の成立日となります。これに対して審判や判決によって離婚が成立した場合には、審判・判決が確定した日に離婚が成立することになります。
⑧婚姻前の氏にもどる者の本籍
婚姻により相手の戸籍に入った者が記入する欄です。もとの戸籍にもどる、または、新しい戸籍をつくるのどちらかにチェックを入れ、本籍地と筆頭者を記入します。
もとの戸籍の本籍地は、戸籍謄本の「従前戸籍」を確認すればわかります。一方、新しい戸籍を選択する場合、日本全国の地番がついている場所であればどこでも本籍地にできますので、離婚後に住む予定の住所地を記入する人が多いでしょう。筆頭者の欄は、新しい戸籍を作る場合には、自分が筆頭者になります。
なお、離婚後に婚姻中の氏(名字)をそのまま継続して名乗ることもできます(これを「婚氏続称」といいます)。その場合、離婚成立後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に提出しなくてはなりません。
ただし、この届は、離婚届の提出と同時にすることもできます。同時提出する場合は、「⑧婚姻前の氏にもどる者の本籍」の箇所は何も記入せずに空欄にしておいてください。
⑨未成年の子の氏名
この欄は、夫婦に未成年の子供がいる場合、夫婦のどちらが親権者になるのかを記入するための場所です。
すでにご説明したように、離婚する夫婦の間に未成年の子供がいる場合には、離婚後夫婦のどちらか一方が親権者になります。離婚届に際して、どちらが親権者になるか指定されていない場合には、離婚届は受理されない扱いとなっています。
「夫が親権を行う子」には、夫が親権者となると決めた子供の名前を、「妻が親権を行う子」には妻が親権者となる子供の名前をそれぞれ明記してください。
なお、この欄に書き間違いをした場合には、訂正箇所に関して夫婦両方の訂正印を押す必要があります。
⑩同居の期間
夫婦が実際に同居を始めた日付と、別居することになった日付を記入します。まだ別居していない場合には、同居を始めた日付のみを記載すればよいでしょう。
⑪別居する前の住所
夫婦がすでに別居している場合には、同居していた時の住所を記入してください。まだ同居している場合には、こちらは空欄で構いません。
⑫別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業
同居していた時における、夫婦どちらか収入の多かった方の主な仕事の欄にチェックします。
なお、「夫妻の職業」に関しては、離婚届を出す日付が、国勢調査が行われる年の4月1日から翌3月31日までに該当する場合にのみ、記入が必要となります。ただし、上記期間外に離婚が成立しており、たまたま離婚の届出が上記期間内となった場合には記入不要とされています(例:3月中に調停離婚が成立し、離婚届を4月に入ってから提出するような場合など)。
ちなみに、次回の国勢調査は2025年に行われることが予定されています。
⑬その他
夫婦の一方または両方が養子縁組していて、実父母以外に養父・養母または養父母がいる場合には、次のように記入します。
例えば、夫に養父母がいる場合は、「夫の養父:山田太郎 夫の養母:花子」といった記載になります。
⑭届出人署名押印
この欄は、夫婦がそれぞれ自分自身で署名押印する必要があります。署名する際の名字は、婚姻中のものとなります。ただし、離婚が調停や裁判によるものである場合には、調停や裁判を申し立てた者だけの署名押印で足ります。
⑮平日昼間の連絡先電話番号
こちらは、基本的に離婚届の記載内容に不備があった場合、役所が当事者に連絡を取るために必要となる情報です。必ず連絡のとれる電話番号を明記するようにしてください。もし連絡が取れない場合には、不備があるため離婚届の受理がなされず、協議離婚の場合にはいつまでも離婚が成立しないことになってしまいます。
⑯※捨て印を押しておくと安心
離婚届を役所が受け取り、内容を審査している途中で軽微な不備がみつかった場合、捨て印を押しておくことで役所の職員が不備を訂正することができます。軽微な書き漏れや書き損じのためにわざわざ役所に出向く手間が省けますので押しておいた方が良いでしょう。
なお、離婚届には、捨て印を押す欄が設けられているのが一般的ですが、もし入手した離婚届にその欄がない場合は、欄外の空白箇所に押す形でも構いません。
⑰証人
協議離婚の場合は、成人(20歳以上)2名の証人が必要です。証人には、署名・捺印・生年月日・住所・本籍地を自著してもらう必要があります(調停や裁判での離婚の場合はこの欄は記載不要)。
なお、証人二人が夫婦や兄弟などの関係で名字が同じであっても、それぞれ別々の印鑑で押印しなくてはなりません。自分たちの親兄弟、親戚、友人、知人に証人を頼むのが一般的ですが、成人していれば、離婚する夫婦の子供に証人になってもらうこともできます。頼める証人がいない場合は、証人代行サービス業者や弁護士に依頼する方法もあります。
離婚届の証人は子供・両親もOK!証人になれる人といない場合の対策
離婚届提出の際の必要書類等一覧

| 離婚届の提出に必要な書類・持参する物一覧 | |
|---|---|
| 全ての種類の離婚に共通して必要なもの |
|
| 協議離婚 |
|
| 調停離婚 |
|
| 審判離婚 |
|
| 判決離婚 |
|
| 和解離婚 |
|
| 認諾離婚 |
|
離婚届を提出する人、提出先、提出方法

離婚届を提出する人
協議離婚の離婚届は、夫婦のどちらが提出しても構いません。裁判離婚(調停離婚・審判離婚・判決離婚等)の場合は、申立人が離婚届を提出する必要があります。
ただし、使者(第三者)に離婚届を提出してもらうこともできます。その場合、委任状は不要ですが、使者の身分確認のために、運転免許証やパスポートなどの身分証の提示を求められます。
離婚届の提出先
離婚届の提出先は、届出人の本籍地または所在地の市区町村役場です。所在地は、住民票上の住所地のほか、別居等で一時的に滞在している住所地も含みます。
離婚届の提出方法
役場の窓口、または、郵送で提出することもできます。
窓口での提出は、平日の役場の開庁時間以外でも、夜間・休日窓口や宿直室に提出することができます。
ただし、休日・夜間の提出の場合は、その場で離婚届の記載漏れや不備をチェックしてくれる職員がいません。後日不備が発覚した場合、平日の日中に改めて役場に出向いて修正する必要があります。郵送の場合も同様です。二度手間とならないよう離婚届は慎重に記載するようにしましょう。
離婚届は休日や夜間でも取得・提出できる!注意点も合わせて解説
離婚届は郵送で提出OK。郵送前に決めておくべきことと3つの注意点
なお、調停離婚は調停成立の日、審判・裁判離婚では確定日から10日以内に離婚届を提出しなくてはなりません。提出期限を過ぎても離婚届は受理してもらえますが、正当な理由がないのに期限をオーバーした場合には、5万円以下の過料が科せられることもあります(戸籍法135条)。
離婚届の提出前に決めておいた方が良いこと

離婚前に必ず決めておかなくてはならないという法的なきまりはありませんが、以下の項目については、離婚届を提出する前に、夫婦でしっかりと話し合って決めておいた方が得策です。
- 慰謝料
- 財産分与
- 養育費
- 夫婦間でのお金の貸し借り
- 年金分割
- 面会交流
離婚して夫婦の縁が切れてしまうと、相手と極力連絡を取りたくないという考えに至りがちです。とくに、お金が絡んだ話となると、支払う側の方が、無視するなどの対応をとることも少なくありません。
そのため、離婚届を提出する前段階で、上記項目について離婚協議書という書面にし、できれば公正証書を作成しておいた方が良いでしょう。
離婚協議書はあくまでも個人間の契約書ですので、その契約書をもって何かしら法的な執行をすることはできません。つまり、一方が契約内容を履行しない場合は、訴訟を提起して勝訴判決を得たうえで、強制執行しなくてはならないのです。
一方、離婚協議書をもとに作成した、「強制執行認諾文言」のある公正証書があれば、訴訟の手間を省くことができます。例えば、相手が養育費や慰謝料の支払いをしない場合には、訴訟をせずとも、その公正証書をもって、銀行預貯金や給与の差し押さえができるようになります。
離婚届が受理されないケース

協議離婚において、夫婦の一方が勝手に離婚届を提出する恐れがある場合に、もう一方が市区町村役場において「離婚届の不受理申出」の手続きをしていれば、その申し出をした側が取り下げない限り離婚届は受理されません。
役場の職員は、離婚届の記載等に不備がないかを形式的に審査するのみで、本当に離婚当事者の双方が離婚意思を有しているのかといった事実確認をする実質的な権限はありません。
そこで、離婚を希望する当事者が相手方の同意なしに勝手に離婚届を役所に提出し、離婚が成立してしまうことを防ぐための制度が、「離婚届の不受理申出」という制度です。
離婚届の不受理申出で無断届出を阻止!申請や取下げ方法がわかる
相手が申出を取り下げてくれない場合、離婚したい側は、調停離婚、裁判離婚等の裁判所を介した離婚を成立させるしかありません。
なお、離婚届の署名・捺印欄に、勝手に記入押印することは、私文書偽造罪・偽造私文書行使罪・電磁的公正証書原本不実記録罪などの犯罪になることもありますので絶対にやめましょう。
まとめ
今回は、離婚届の書き方をメインに解説させていただきました。
離婚が成立した場合には、離婚届を一定の市区町村役場に提出する必要があります。
しかし離婚届を書く際には、意外と記入すべき項目が多いため、戸惑ってしまうことがよくあるものです。
離婚届を書く際には、記入すべき項目に関して何を記載すべきかを理解し、正しく記入することが大切です。
今回ご覧いただいたように、離婚届の作成は、意外と難しい作業なのです。
今回ご紹介した知識をもとに、少しでもスムーズに離婚届を書いていただければ幸いです。
もし離婚届の書き方に関して疑問などお有りの場合には、お気軽に当事務所へご相談ください。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|