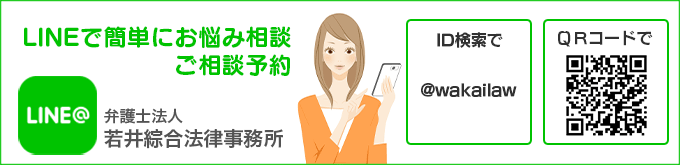離婚の際に気になるのが養育費、慰謝料、財産分与などのお金のことではないでしょうか?
離婚後の生活のことを考えると、「少しでも多く手に入れて生活を楽にしたい。」と考える方も少なくありません。
そこで、今回は、上記3つのうちの「財産分与」に焦点を置き、財産分与の相場などについて、離婚の財産分与に詳しい弁護士が解説してまいります。
ぜひ、最後までお読みいただき、財産分与する際の参考としていただければ幸いです。
誰でも気軽に弁護士に相談できます
財産分与の相場は?
結論から申し上げると、財産分与に相場はありません。なぜなら、財産分与とは結婚後に夫婦が協力して築いた財産を離婚時にそれぞれの貢献度に応じて公平に分け合う制度ですが、夫婦によって築き上げた財産の額は異なるからです。
もっとも、一般的には、婚姻期間が長ければ長いほど財産分与される金額は大きくなるという傾向はあります。その理由は、上記の通り、財産分与の対象が「婚姻後に夫婦が協力して築いた財産(共有財産、実質的共有財産)」だからです。
つまり、一般的に、婚姻関係が長くなればなるほど「婚姻後に夫婦が協力して築いた財産」は増えます。したがって、その分、財産分与される金額も増える、というわけです。
司法統計の「第27表 「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件数-財産分与の支払額別婚姻期間別-全家庭裁判所」によると、婚姻期間が1年以上5年未満で、調停や調停に代わる審判で財産分与について取り決めのあった夫婦の場合、財産分与の金額が100万円以下だった夫婦(件数)は全体の5割以上で、600万円以上は1割にも満たない数でした。
| 財産分与で取り決めされた金額 | |
|---|---|
| 金額 | 件数 |
| 100万円以下 | 1552件 |
| 200万円以下 | 762件 |
| 400万円以下 | 899件 |
| 600万円以下 | 546件 |
| 1000万円以下 | 653件 |
| 2000万円以下 | 539件 |
| 2000万円を超える | 259件 |
他方で、熟年離婚(一般的には、婚姻期間が20年以上の夫婦の離婚)の場合、財産分与の金額が100万円以下だった夫婦(件数)は全体の1割以下だったのに対し、600万円以上は約4割以上の数と、婚姻期間が1年以上5年未満の夫婦とは真逆の結果となっています。
| 財産分与で取り決めされた金額(熟年離婚) | |
|---|---|
| 金額 | 件数 |
| 100万円以下 | 180件 |
| 200万円以下 | 152件 |
| 400万円以下 | 291件 |
| 600万円以下 | 231件 |
| 1000万円以下 | 345件 |
| 2000万円以下 | 333件 |
| 2000万円を超える | 175件 |
財産分与とは?
財産分与とは、結婚後に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時にそれぞれの貢献度に応じて公平に分け合う制度です。
財産分与の種類
財産分与には、次に挙げる3つの種類(側面)があります。
- 清算的財産分与
- 慰謝料的財産分与
- 扶養的財産分与
①清算的財産分与
清算的財産分与とは、夫婦が離婚する場合、婚姻期間中に夫婦が形成した共有財産を清算することです。
財産分与の割合は財産形成の寄与度に応じることになりますが、夫婦の一方が財産の形成に多大な貢献をしたなどの特段の事情がない限り、寄与度は2分の1とされ(いわゆる「2分の1ルール」)、ほぼすべてのケースで2分の1ルールが採用されています。
なお、以下で解説する慰謝料的財産分与、扶養的財産分与という種類もありますが、離婚に伴う財産分与でメインとなるのがこの清算的財産分与になります。離婚における財産分与は原則として清算的財産分与であると言えます。
②慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、不倫やDVなど婚姻関係を破綻させた主な原因を作った側の配偶者が、相手側に慰謝料の意味を含めて多めに財産分与をすることです。
慰謝料とは、相手が被った精神的苦痛に対して支払われる金銭のことですので、本来であれば不法行為に基づく離婚慰謝料(民法第709条、710条)で議論されるべき問題です。
しかし、条文上、財産分与は、「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める」とされています(民法第768条3項)。
したがって、財産分与において慰謝料を考慮して分与額を決めることもあります。
慰謝料と財産分与は両方請求できる|但し慰謝料的財産分与の例外あり
③扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚によって夫婦の一方の生活が困窮する場合に、収入の多い方から、収入が少ない方が経済的に自立するまでの一定期間、財産分与の名目で生活の援助をすることです。
例えば、夫婦の一方が婚姻後、家事や育児に専念するために仕事を辞めたという方もいらっしゃるでしょう。そのような夫婦が離婚した場合、仕事を辞めた方の配偶者は、もう一方の配偶者からの扶養(婚姻費用の分担等)を受けられなくなるため、扶養的財産分与が認められることもあります。
もっとも、前述の通り、財産分与は清算的財産分与が原則であるため、裁判実務において扶養的財産分与が認められるケースは極めて稀です。
財産分与の対象となる財産は?
財産分与の一番の目的は、夫婦が協力して築いた財産を清算し分配すること(清算的財産分与)です。
したがって、財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻後から離婚(又は別居)までに夫婦が協力して築いたと認められる財産(共有財産、実質的共有財産)です。
他方で、夫婦の一方が婚姻前から有してた財産、あるいは婚姻後に取得した財産であっても夫婦が単独で得た財産(特有財産)は財産分与の対象ではありません。
- 不動産
- 車
- 家電、家具、骨とう品など金銭的価値の高い物
- 預貯金
- 各種保険の解約に伴う解約返戻金
- 株式
- 退職金(対象となるかどうかは、将来受け取れる蓋然性が高いかどうかによります)
- 厚生年金(国民年金は対象外です)
- 借金(ただし、内容によります) など
- 婚姻前に購入した車(ただし、購入時にローンを組み、婚姻後は共有財産の預金からローンが引き落とされていた場合は、引き落とされた額分は共有財産となります)。
- 婚姻前に購入した家電、家具、金銭的価値の高い物
- 婚姻前に築いていた預貯金
- 親から贈与、相続した不動産、車 など
まとめ
財産分与によって夫婦の一方は、相手方に対して財産の分配(分与)を請求できます。統計上は、夫が財産の支払義務者になることが多いようです。
財産分与される金額は、一般的に婚姻期間に比例して増額します。
もっとも、実際に受け取る金額は、婚姻期間や夫婦の財産の状況はもちろん、夫婦の財産形成に対する寄与度、落ち度などを勘案して個別に決まります。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|