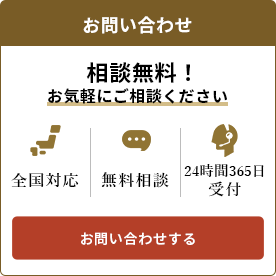風営法違反で逮捕され、「執行猶予は付くのか」「刑務所に入らずに済むのか」と不安を抱えている方へ。
現実は厳しく、風営法違反で執行猶予が付くのは起訴事件全体のわずか数%に過ぎません。大半は罰金刑で終わりますが、拘禁刑が言い渡された場合は実刑となるケースがほとんどです。
それでも、初犯で深い反省と具体的な再犯防止策を示せば、執行猶予を得られる可能性はあります。実際に、こうした情状が評価されて執行猶予となった判例も存在します。
本記事では、風営法違反に詳しい弁護士が検察統計年報(令和6年版)の最新データをもとに、風営法違反における執行猶予の獲得率、量刑の傾向、執行猶予を得るための条件や対策を実際の判例とともに解説します。
もし風営法違反でお困りの場合、または身近な方が逮捕されてしまった場合は、当事務所では全国どこからでも24時間365日無料相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。早期の対応が結果を左右します。
※2025年6月1日の刑法改正により、従来の「懲役刑」と「禁錮刑」は「拘禁刑」に一本化されました。本記事では最新の法令に基づき「拘禁刑」と表記していますが、統計データや判例については当時の表記(懲役・禁錮)を使用している箇所があります。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
目次
風営法違反で執行猶予がつく割合は?
風営法違反事件で執行猶予が付く割合は、起訴された事件全体のわずか数%に過ぎません。風営法違反の量刑は罰金刑が大半であり、執行猶予付きの判決を得ることは極めて難しい状況にあります。
検察統計年報(令和6年版/2024年度)に基づき、この厳しい現実を数字で見ていきましょう。
検察が処理した風営法違反の事件の総数は2,072件で、そのうち起訴されたのは718件でした。したがって、起訴率は約34.6%となります。
そして、ここで注目すべきは、起訴された事件の大多数が「略式命令請求」の手続で処理されている点です。718件のうち582件(約81%)が略式命令請求であり、これは簡易な裁判で罰金刑や科料を科すものです。略式命令請求は有罪の罰金刑となる手続であり、拘禁刑(懲役・禁錮)や執行猶予が付くことは構造上ありません。執行猶予判決の可能性があるのは、公開の法廷で審理される「公判請求」となった136件のみです。
公判請求されたケースのうち、実際に執行猶予が付くのは例年2割程度といわれています。したがって、風営法違反で起訴された事件全体から見ると、執行猶予が付されるのはわずか数%に過ぎないのです。
風営法違反で執行猶予がついた場合の量刑と執行猶予期間は?
風営法違反で執行猶予が付されるのは、「3年以下の拘禁刑(懲役・禁錮)」が言い渡された場合に限られます(刑法第25条)。実際に執行猶予が付いた事案は、比較的短い懲役期間となる傾向があります。
検察統計年報(令和6年版/2024年度)に基づき、風営法違反で執行猶予が付いた事件の量刑相場と執行猶予期間を以下にまとめます。
| 懲役期間 | 該当件数 |
| 懲役6月以下 | 6件 |
| 懲役1年以上 | 11件 |
| 懲役2年以下 | 2件 |
| 合計 | 19件 |
※統計データは令和6年版のため「懲役」表記ですが、2025年6月以降の判決では「拘禁刑」となります。
| 執行猶予期間 | 該当件数 |
| 執行猶予2年以上 | 3件 |
| 執行猶予3年以上 | 15件 |
| 執行猶予4年以上 | 1件 |
| 合計 | 19件 |
上記の統計から、風営法違反で執行猶予が付いた事案は、「懲役1年以下」の判決が大半を占めており、同時に「執行猶予3年以上」が最も多く設定されていることがわかります。これは、裁判所が悪質性を認めつつも、被告人の更生可能性を重視し、一定期間の監視下に置くことで刑の執行を猶予する判断を多くしていることを示しています。
風営法違反で執行猶予がつく条件
風営法違反で執行猶予が付くためには、法律上の要件を満たすだけでなく、被告人の反省や更生の意思が裁判所に認められる必要があります。
刑法第25条に定められた法定要件に加え、前科や情状などの事情が総合的に考慮されます。
以下では、執行猶予が認められる主な条件を3つの観点から解説します。
- ① 刑が執行猶予の対象範囲内であること
- ② 前科の条件を満たしていること
- ③ 情状酌量すべきものがあること
これら3つの条件を満たして初めて、裁判所が執行猶予を付す可能性が生じます。
以下で、それぞれの要件について詳しく見ていきましょう。
①刑が執行猶予の対象範囲内であること
執行猶予を付すためには、刑法第25条に定められた法定の条件を満たしている必要があります。まず、言い渡される刑罰が「3年以下の拘禁刑(懲役・禁錮)、または50万円以下の罰金」でなければなりません。なお、罰金刑に対しても法律上は執行猶予を付すことができますが、実務上はごく稀にしか適用されません。
風営法違反の罪のうち、無許可営業罪や名義貸しの罪の法定刑は、改正により無許可営業罪で「5年以下の拘禁刑」または「1,000万円以下の罰金(法人の場合は最大3億円)」に引き上げられています。このため、無許可営業で起訴された場合、刑の減軽がなければ、裁判所が刑法上の執行猶予の上限(3年以下)を超える刑を言い渡す可能性があり、執行猶予の獲得が難しくなっている点には注意が必要です。
②前科の条件を満たしていること
執行猶予の法定条件には、被告人の前科の有無と内容が大きく関わります。刑法第25条に基づき、執行猶予が付くケースは主に以下の2パターンに分けられます。
- 前科なし:過去に拘禁刑(懲役・禁錮)以上の刑に処せられたことがない者
- 前科あり:過去に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の執行を終えた日などから5年以内に、再度拘禁刑以上の刑に処せられていない者
罰金刑のみの前科であれば上記の条件を満たし、執行猶予の対象となります。また、以前に執行猶予付き判決を受けた者であっても、執行猶予期間中に新たな罪を犯さず、情状に特に酌量すべきものがある場合は、再度執行猶予が付く可能性もあります。
③情状酌量すべきものがあること
過去に拘禁刑に処せられ、刑の全部の執行を猶予された者が、2年以下の拘禁刑の言い渡しを受け、「情状に特に酌量すべきものがあるとき」も、執行猶予を付すことができます。裁判官が執行猶予の判断で重視するのが、再犯の恐れが低いかという点です。
風営法違反の場合、実質的な情状とは、違反の悪質性の程度(無許可期間、組織性、利益の規模)、深い反省の態度、そして最も重要な具体的な再犯防止策(店舗の閉鎖、事業からの離脱、コンプライアンス体制の構築など)の有無です。これらの情状証拠を弁護士を通じて裁判所に提出し、被告人が社会内で十分更生できると認められたときに、初めて執行猶予が選択されます。
風営法違反で執行猶予をつけるためのポイント
風営法違反事件で公判請求され、法定の執行猶予条件を満たしたとしても、必ず執行猶予が付くわけではありません。最終的な判決は、裁判官が情状を総合的に考慮し、裁量によって決定されます。
ここでいう情状とは、被告人の前科・前歴の有無、犯行の動機や態様の悪質性、そして最も重要な事件後の反省の度合いと再犯防止への具体的努力などを指します。
以下では、執行猶予を獲得するために特に重要となるポイントを4つに分けて解説します。
- ① 贖罪寄付や反省文の作成によって反省の意思を示す
- ② 再犯防止に向けた具体的な取り組みを行う
- ③ 更生できる環境を整え、身元引受人を確保する
- ④ 情状証人による証言で社会的信頼を補強する
これらの要素を的確に整えることで、裁判官に「社会内で更生できる」と判断され、執行猶予の獲得につながる可能性が高まります。
なお、起訴される前の段階で適切な弁護活動を行えば、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。詳しくは「風営法違反で不起訴となった3つの事例」をご覧ください。
①贖罪寄付や反省文の作成によって反省の意思を示す
風営法違反は、一般的に「被害者のいない犯罪」と見なされることが多く、傷害罪のように被害者個人との示談交渉を行うことができません。そのため、被害者への直接的な弁償の代わりに、社会に対する償いの意思を具体的に示すことが、執行猶予獲得の重要なポイントとなります。
この手段として有効なのが「贖罪寄付」です。贖罪寄付とは、風営法違反事件に対する反省と謝罪の気持ちを示すために、公的な団体に金銭を寄付することです。弁護士を通じて適切な寄付先や金額についてアドバイスを受け、執行猶予獲得に向けた効果的な贖罪寄付を行いましょう。あわせて、反省文は自分の言葉で作成し、なぜ風営法違反に至ったのかという経緯への深い反省と今後の具体的な決意を明記することが大切です。
②再犯防止に向けた具体的な取り組みを行う
裁判官が執行猶予の判断で最も重視するのは、被告人が二度と風営法違反を繰り返さないという再犯の恐れの低さです。そのため、具体的な再犯防止策を策定し、それを実行していることを明確に示す必要があります。
例えば、無許可営業で起訴された事業主であれば、問題となった店舗を閉鎖し、事業からの完全な離脱を証明することが求められます。従業員による違反であれば、風営法の正確な理解と法的知識の習得、法令遵守体制の構築、そしてコンプライアンス研修の受講などが有効な対策となります。弁護士は、風営法に関する専門的なアドバイスを提供し、事件の原因を分析した上で、実効性のある再発防止策を策定します。具体的な対策を実行し、その計画書を証拠として提出することで、裁判官に対し更生への強い意欲を示し、執行猶予獲得につなげることが可能です。
③更生できる環境を整え、身元引受人を確保する
被告人が刑務所に入らず、社会内で更生できるかどうかを裁判官が判断する際、更生環境の整備は不可欠な要素です。この環境を整えるために最も重要なのが、身元引受人(監督者)の確保です。身元引受人は、家族(配偶者、両親など)や職場の上司など、被告人を継続的に監督・指導できる信頼できる人物が適任です。
同居家族による監督強化や、勤務先による継続雇用の確保は、風営法違反事件の執行猶予獲得に有利に働きます。弁護士は、監督者となる方と面談を行い、被告人を管理・監督する具体的な誓約書の作成をサポートします。また、社会復帰への具体的な道筋、例えば問題のある人間関係との絶縁や、必要に応じた専門的な更生プログラムへの参加なども検討すべきです。裁判官に「社会内で立ち直れる体制が整っている」と納得してもらえるよう、更生環境を整備しましょう。
④情状証人による証言で社会的信頼を補強する
情状証人による証言は、裁判官の心証形成に大きな影響を与え、執行猶予獲得の可能性を高めます。情状証人は、被告人の人柄、事件後の反省の様子、そして今後の更生への取り組みを法廷で直接証言し、監督を誓約する証人です。身元引受人となる家族が適していますが、経営者・店長として風営法違反を犯した場合は、取引先、顧問税理士、あるいは同業者団体の関係者などからの証言も有効です。これらの証人は、被告人の社会的な信頼性や、今後の法令遵守への取り組み、そして社会復帰への具体的な協力を証言します。
風営法違反で執行猶予判決となった判例
ここでは、実際に風営法違反で執行猶予判決が言い渡された裁判例を紹介します。実際の事例を見ることで、どのような事情や弁護活動が執行猶予の判断に影響するのかが具体的に理解できます。
いずれのケースも、違反内容や悪質性の程度、反省の有無、再犯防止策の取り組みなど、さまざまな情状を踏まえて裁判所が総合的に判断しています。
これらの判例を通じて、執行猶予を得るために重要となる要素を確認していきましょう。
風俗店経営者が未成年者に接待をさせていた事例
【事案の概要】
被告人は、共同経営者と共に、市内で実質的に経営していた深夜酒類提供飲食店で、公安委員会から風俗営業の許可を得ずに、深夜に女性従業員(当時17歳の未成年者を含む)に客の隣に座らせて談笑させるなどの接待行為を行いました。さらに被告人は、元県警事務職員に対し、摘発を免れるための対策を講じて捜索をやり過ごすことができた謝礼として現金30万円を供与した(贈賄)罪にも問われました。
【裁判所の判断】
裁判所は、以下の点を認定しました。
- 風営法違反の悪質性:開店当初から約5か月にわたり未成年者のみを雇用して接待営業を行っており、善良な風俗や年少者の健全な育成に与えた悪影響は軽視できない。
- 贈賄の悪質性:公務員の職務の公正およびこれに対する国民の信頼を損なうものであり、賄賂の提供について共同経営者らと相談するなど主導的な役割を果たした。
一方で、被告人が反省の態度を示していることや、前科がなく、家族が今後の立ち直りの支援を約束していることから、被告人に対して懲役1年6月、罰金50万円、執行猶予3年の判決が言い渡されました(大分地方裁判所平成29年3月13日判決)。
暴力団幹部がキャバクラの無許可営業をしていた事例
【事案の概要】
被告人は、福岡市内でキャバクラ店「A」を実質的に経営する傍ら、暴力団幹部組員という立場にありました。被告人は公安委員会の風俗営業の許可を受けないまま、約3年にわたり無許可営業を継続しました。さらに、その営業により得た巨額の売上金(合計約2億9,000万円)について、従業員名義の銀行口座にクレジットカード売上金を入金させる手口で犯罪収益の取得に関する事実を仮装した(組織的犯罪処罰法違反)罪にも問われました。
【裁判所の判断】
裁判所は、以下のように判示し、被告人に懲役1年6月、罰金100万円、執行猶予3年を言い渡しました。
- 被告人は暴力団幹部であり、適法に営業許可を得る可能性が全くない中で、多額の売上金を暴力団の資金源としていた点が極めて悪質である。
- 経営者として主体的に犯行に関与し、巨額の犯罪収益を仮装した責任は軽視できない。
一方で、被告人が事実関係を概ね認め、反省の態度を示し、懲役刑を科されるのが今回が初めてであるという情状が考慮され、執行猶予が認められました。なお、犯罪収益については、現金など約390万円の没収に加え、約2億8,638万円の追徴金が命じられています(福岡地方裁判所令和4年5月9日判決)。
名義借りによる無許可営業でキャバクラを経営した事例
【事案の概要】
被告人は、東京都新宿区内で「C」と「D」というキャバクラ店2店舗を実質的に経営していました。被告人は、いずれの店舗についても風俗営業の許可を得ることなく、他者の名義を借りるという手口を用いて、それぞれ約11ヶ月間および約1年2ヶ月間にわたり無許可で営業を継続していました。
【裁判所の判断】
裁判所は、以下のように判示し、被告人に懲役6月、罰金100万円、執行猶予3年を言い渡しました。被告人の行為について、相当期間にわたる無許可営業であり、他者の名義を借りて大きな利益を上げていたとして、「大胆、悪質な犯行」であると厳しく指摘しました。一方で、被告人に前科がないこと、および反省の態度を示していることを情状として考慮して、執行猶予が付されました。なお、4,034万円が追徴されています(東京地方裁判所令和3年9月8日判決)。
風営法違反で執行猶予を目指す方は弁護士にご相談ください
風営法違反での逮捕・起訴は、事業だけでなく、あなた自身の人生にも大きな影響を及ぼします。執行猶予を獲得できるかどうかは、逮捕直後からの対応で決まるといっても過言ではありません。
当事務所では、風営法違反をはじめとする刑事事件の豊富な解決実績があり、執行猶予獲得や不起訴処分の実績も多数あります。逮捕直後の接見や取調べ対応へのアドバイス、検察官への意見書提出による不起訴・執行猶予の獲得支援、再犯防止策の構築と情状証人の準備、保釈請求や公判における弁護活動まで、状況に応じた最適なサポートを提供します。
全国どこからでも、風営法事件に詳しい弁護士が24時間365日無料相談を受け付けています。逮捕直後でも深夜でも対応可能です。一人で悩まず、今すぐご相談ください。早期の相談が、あなたの未来を守ります。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|