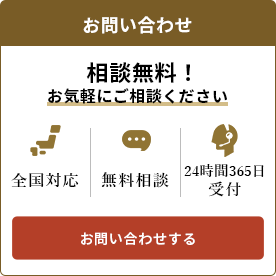「通報されたかもしれない」「警察が来たらどうすればいいのか」――
風営法違反の通報に関する不安を抱えながら営業を続けている経営者は少なくありません。
風営法違反で通報された場合、どのように警察が動くのか、どのような対応を取るべきか――多くの経営者が正確な情報を求めています。
通報は予告なく発生します。
地域住民からの苦情、競合店からの情報提供、元従業員による告発、来店客からの被害届など、通報経路は多岐にわたります。
通報後、警察は内偵捜査として私服警察官による来店調査を行い、営業実態を確認します。
対応を誤った場合、逮捕・勾留による最大23日間の身柄拘束、営業停止処分、そして報道による信用失墜といった深刻な事態に発展するおそれがあります。
ただし、通報直後に冷静に対応し、弁護士の助言を得られれば、刑事処分や行政処分を回避できたり、軽く済ませられる場合もあります。
本記事は、多数の風営法違反事件で経営者を弁護してきた弁護士が、現場対応の実務経験をもとに執筆しています。
以下の内容を通じて、通報後に取るべき正しい対応方法を具体的に解説します。
- 通報後の警察の動き(内偵捜査→立ち入り調査→逮捕の流れ)
- 通報時に絶対に避けるべき対応
- 刑事処分・行政処分を回避するための初動対応
- 実際に通報から摘発に至った事例と教訓
- 通報を予防するための日常的な対策
通報への不安を抱えたまま営業を続けるのではなく、正しい知識に基づいた対応を取ることが重要です。
本記事が、あなたの店舗を守るための具体的な指針となれば幸いです。
若井綜合法律事務所では、風営法違反の通報や摘発に関するご相談を、全国どこからでも24時間365日無料でお受けしています。
なお、風営法違反でどのような行為が逮捕につながるかをより詳しく知りたい方は、風営法違反は逮捕される?よくある違反行為と罰則を弁護士が解説も合わせてご覧ください。
目次
風営法違反で通報される可能性のある12の行為
風営法に違反する行為は、警察の定期的な取り締まりだけでなく、競合店や元従業員、地域住民、あるいは来店客からの通報によって発覚することも少なくありません。
とくに風俗営業や深夜営業の業態では、無許可営業や接待行為、未成年者の雇用などが摘発のきっかけとなるケースが多く見られます。
ここでは、実際に通報・摘発につながりやすい代表的な違反行為を12項目に整理します。
- ① 風営法の許可・届出なしでの営業
- ② 営業許可証の掲示義務違反
- ③ 名義貸し・名義借り
- ④ 路上での客引き・客待ち行為
- ⑤ 未成年者による接待業務や深夜労働
- ⑥ 未成年者の入店
- ⑦ 20歳未満の客への酒類・たばこ提供
- ⑧ 禁止区域での営業
- ⑨ 営業時間違反
- ⑩ 料金・サービス表示義務違反
- ⑪ 広告・宣伝違反
- ⑫ 構造設備基準違反
①風営法の許可・届出なしでの営業
風俗関連の営業を開始する際は、その業態に応じて都道府県公安委員会の許可または届出が義務付けられています(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律〔以下、風営法〕)。
たとえば、キャバクラやホストクラブのような「風俗営業」には許可が、深夜営業のバーや居酒屋のような「深夜酒類提供飲食店営業」には届出が必要です。
許可なく営業したり、届け出た内容と異なる営業をすると無許可営業とみなされ、風営法違反となります。とくに、摘発リスクが高いとされるガールズバーでの接待行為やメンズエステでの性的サービスは、無許可営業の代表例です。
これらの違反は、競合店からの通報、客や元従業員からの密告、さらには警察官の巡回や口コミサイトでの書き込みをきっかけに発覚することが多いです。
②営業許可証の掲示義務違反
風俗営業を行う店舗には、営業許可証を店舗内の見やすい場所に掲示することが風営法で義務付けられています(風営法第6条)。
この「見やすい場所」とは、客が店内に入ってすぐに確認できるような場所を指し、レジ横の壁面やカウンター付近などが一般的です。掲示する許可証は原本である必要があり、コピーや「許可証あり」の掲示は認められていません。もし許可証を掲示していなかったり、わかりにくい場所に掲示していたりすると、風営法違反となります。
営業許可証の掲示義務違反は、店舗を訪れた客からの指摘や、競合店による調査、あるいは行政の定期調査によって通報・発覚するケースが多いでしょう。
③名義貸し・名義借り
「名義貸し」とは、風営法の許可を受けた人が、自分の名義を他人に貸して風俗営業を行わせる行為を指します。一方、「名義借り」は、自ら許可を取得できない人が他人の名義を使って営業する行為です。
たとえば、風営法上の欠格事由(過去の違反歴など)があるため許可が取れない経営者が、知人や従業員の名義を借りて風俗営業をするケースなどが典型例です。名義貸しや名義借りは風営法に違反し、無許可営業に該当する行為とみなされます。
このような名義貸しや名義借りは、一見すると見つかりにくいように思えますが、元従業員による内部告発や、税務署との情報連携によって発覚することがあります。
④路上での客引き・客待ち行為
風営法では「客引き」が禁止されています(風営法第22条第1項第1号、第2号)。
「客引き」とは、相手方を特定して営業所の客となるように勧誘することを指します。具体的には、特定の通行人に対し、営業の客となるよう勧誘したり、立ちふさがったり、つきまとったりする行為がこれにあたります。
とくに、キャバクラやホストクラブなどの風俗営業では、時間帯に関係なく客引きが禁止されていますが、ガールズバーや深夜営業の居酒屋など、深夜酒類提供飲食店営業を行う店舗では、午前0時以降の客引きが規制対象となります。
客引きは通行人の目に留まりやすいため、通行人からの110番通報や、近隣住民からの騒音苦情などをきっかけに警察に摘発される可能性が高い行為です。
⑤未成年者による接待業務と深夜労働
営業所で18歳未満の従業員に「接待」業務をさせることは禁止されています(風営法第22条第1項第3号)。
「接待」とは、客の隣に座って歓談したり、お酌をしたりするなど、特定の客をもてなす行為を指します。また、接待の有無に関わらず、18歳未満を午後10時〜翌午前6時に「客と接する業務」に従事させることも禁止です(同第4号)。
これらの違反が発覚するきっかけとしては、同業者からの通報や、給料や待遇に不満を持った元従業員による内部告発が挙げられます。
⑥未成年者を入店させる行為
風俗営業(例:キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ店)では18歳未満の客の立ち入りが禁止です(風営法第22条第1項第5号)。また、深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業のバーやガールズバーなど)では、午後10時以降の未成年者の立ち入りが禁じられています。
このような規制は、青少年の健全な育成を保護することを目的としています。風俗営業者は、18歳未満の者がお店に立ち入ってはならない旨を営業所の入り口に表示する義務があり(同法第18条)、万が一、未成年者が立ち入っているのを認知した場合には、すみやかに退出するよう必要な措置を講じる必要があります(風営法施行規則第38条第7号)。
このような違反が発覚するきっかけは、主に客からの目撃情報や、近隣住民からの情報提供、さらには警察官の巡回パトロールによる立ち入り調査などがあります。
⑦20歳未満の客に酒類やたばこを提供
20歳未満の客に対する酒類・たばこの提供は禁止です(風営法第22条第1項第6号)。したがって、18歳や19歳の客も規制対象となります。
この「提供」とは、酒類を飲用に、たばこを喫煙の用に適する状態に置くことで、営業者が未成年者に販売したり贈与したりする場合に限られません。未成年者が持参した酒類又はたばこについて、燗をしたり、グラス・灰皿等の器具を使用させてその用に供する状態に置けば、「提供」に該当します。
これは、未成年者の健康と健全な成長を守るための重要な規制です。年齢不明の客には身分証で年齢確認を行う義務があります。もし年齢確認を怠り、20歳未満の客に酒類やたばこを提供した場合、「知らなかった」という言い訳は通用しません。
この違反は、客自身からの通報や、警察官が客を装って行う内偵調査によって発覚することがあります。
⑧禁止区域での営業
風営法や各都道府県の条例では、風俗営業を行うことができない禁止区域が定められています。これは、住宅街や学校、病院など、青少年の育成や地域の風紀に影響を及ぼすおそれのある場所に風俗店が乱立するのを防ぐ目的があります。
禁止区域の具体範囲は都道府県条例で定められ、性風俗関連特殊営業では条例で定める範囲(例:敷地の周囲200m以内など)が対象となります。
メンズエステやガールズバーなどの営業が、こうした禁止区域で無許可で行われる事例が後を絶ちません。違反が発覚するきっかけとしては、口コミサイトへの投稿や、店舗を不審に思った客からの情報提供などがあります。
⑨営業時間違反
風俗営業の営業時間は原則「午前6時〜午前0時」で、深夜(午前0時〜6時)の営業は原則禁止。
たとえば、キャバクラやホストクラブといった風俗営業を行う店舗は、原則として午前6時から午前0時までの営業が義務付けられており、一部地域を除き延長は認められていません。深夜酒類提供飲食店営業を行う店舗も、営業時間が条例で規制されています。
もし、これらの規定時間を超えて営業を行った場合、営業時間違反として摘発の対象となります。
この違反は、とくに深夜帯の営業に伴う騒音問題などから、近隣住民による苦情や通報をきっかけに発覚するケースが非常に多いです。
営業時間の詳細については風営法の営業時間違反は何時から?時間外営業の罰則を解説で業態ごとに詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。
⑩料金・サービス表示義務違反
営業に係る料金は、営業所で客に見やすいように表示する義務があります(風営法第17条、施行規則第8条)。
例えば、ホストクラブやキャバクラなどのお店は、料金の呼び名に関わらず、お店を利用して客が接待を受けて遊興・飲食する行為について、その対価または負担として客が支払うべき料金等を表示しなければなりません。また、多くの都道府県条例で客が支払うべき一切の料金の表示が義務付けられているため、注意が必要です。
この義務には、看板やメニュー表に明記するだけでなく、誇大な表現や客に誤解を与えるような表示をしないことも含まれます。
料金の不明瞭さから、いわゆる「ぼったくり」が発生するリスクが高まり、客からの被害届や口コミサイトでの悪評につながります。これらの通報や情報が、摘発のきっかけとなることがあります。
⑪広告・宣伝違反
清浄な風俗環境を害するおそれのある方法での広告・宣伝は規制対象(風営法第16条)。
これには、過度に客の遊興心や射幸心を煽る表現、従業員間の過度な競争意識を生じさせ違法な営業を助長するような歓楽的・享楽的雰囲気を過度に醸し出す広告表現が含まれます。
例えば、「年間売上〇億円突破」や「指名数No.1」など接客従業員の営業成績を直接に示す広告や、「総支配人・覇者・神・レジェンド」など営業成績が上位であることを推認させる広告は、屋外の看板だけでなく、SNSやウェブサイト上での表現も規制対象です。
近年では、SNS投稿を見た市民からの通報や、警察によるインターネットパトロールによって、違法な広告・宣伝が発覚し、摘発されるケースが増えています。
⑫構造設備基準違反
営業所の構造・設備には、客室の面積、見通し確保、照度など業種ごとの詳細基準があります。
たとえば、客室の床面積や、見通しを妨げる設備の有無、照明の照度などが厳しく規定されています。キャバクラの客室に鍵付きのドアを設置したり、風俗環境を害する写真や装飾を施したりする行為などが違反にあたります。
これらの基準違反は、店を訪れた客からの情報提供や、従業員からの内部告発によって警察に通報され、摘発につながることがあります。
風営法違反で通報された場合のリスク
風営法違反は刑事事件化や営業停止に発展し、経営へ深刻な影響を及ぼす可能性があります。警察による内偵捜査や立ち入り調査を経て違反が確認されれば、逮捕・起訴といった刑事手続きに発展する場合も少なくありません。ここでは、風営法違反によって想定される主なリスクを4つの観点から整理します。
- ① 刑事処分
- ② 行政処分
- ③ 社会的制裁
- ④ 経済的損失
①刑事処分
風営法違反で通報され、その違反事実が警察の内偵捜査によって確認された場合、逮捕される可能性が生じます。
逮捕(最長72時間)+勾留10日+延長10日で、最大23日間身柄拘束が継続し得ます。長期の身体拘束は、事業の運営や日常生活に甚大な支障をきたします。
また、2025年改正風営法により、重大違反の法定刑が引き上げ(個人:最大5年の拘禁刑または1,000万円以下、法人:3億円以下の罰金)となる場合があります。検察官に起訴され、有罪判決が確定すれば前科となり、今後の社会生活に深刻な影響を及ぼします。
②行政処分
通報により違反事実が確認されると、都道府県の公安委員会が行政処分を検討します。最も重い「許可取消処分」は、取消し後5年間は再申請不可で事実上の廃業につながります。
次に重いのが「営業停止処分」で、内容に応じて40日以上最大6ヶ月間の停止が命じられます。
比較的軽微な違反に対しては、改善を促す「指示処分」や「指導」が行われますが、これに従わない場合や改善が認められない場合は、より重い処分へと発展します。
一度行政処分を受けると、その店舗は要注意として継続的に監視され、今後の違反に対してさらに厳しい処分が下される傾向があります。
③社会的制裁
風営法違反による通報・摘発は、事業の社会的信用を失墜させる深刻な問題を引き起こします。
摘発されると報道により店名・経営者名が公になり、情報がネット上に半永久的に残ります。これにより、既存顧客の信頼を失い顧客離れが加速するだけでなく、従業員の離職も相次ぐことになります。
一度失った信用を回復するには、数年以上の長期間と多大な労力が必要となり、営業再開後も厳しい経営環境が続きます。
④経済的損失
通報により立ち入り調査や悪評の拡散によって客足が急減し、売上が大幅に落ち込みます。
この段階で、刑事・行政手続きに対応するための弁護士費用や緊急対応費用として多額の出費が必要となります。さらに営業停止処分が下されると、収入が止まっても家賃・人件費・設備維持費などの固定費は発生し続けます。
有罪となれば個人で最大1,000万円、法人で最大3億円の罰金リスクがあり、許可取消しの場合は5年間の機会損失も生じます。
これらの経済的損失は、違反による短期的な利益を遥かに上回るものです。
風営法違反で通報された後の流れ
風営法違反で通報された場合、警察の捜査から検察の判断に至るまで、次のような流れで手続きが進みます。
- 通報受理から内偵捜査まで
- 立ち入り調査の実施
- 逮捕・呼び出し・勾留
- 起訴・不起訴と刑事処分
①通報受理から内偵捜査まで
風営法違反の通報を受けた警察は、まず通報内容の信憑性を慎重に検討します。内容が具体的で信憑性が高い場合、私服警察官による内偵捜査が開始されます。
内偵捜査は、主に私服警察官が一般客を装って店舗に立ち入り、営業許可証の掲示状況、未成年者の出入り、料金表示、接待行為の有無など、実際の営業実態を密かに確認するものです。
内偵捜査の警察官は身分を隠しているため、店舗側がそれを見分けることは非常に困難です。そのため、いつ警察が来ても問題ないように、日頃から法令遵守を徹底することが最も重要となります。
②立ち入り調査の実施
内偵捜査によって風営法違反の疑いが強まると、警察はより本格的な立ち入り調査を実施します。この調査は、通報内容の裏付けを直接取り、営業実態を詳細に確認するために行われるものです。
警察による立ち入り調査というと、捜索・差押え(いわゆるガサ入れ)をイメージする方もいますが、立ち入り調査は営業状況の確認が目的であり、捜索・差押えとは異なります。しかし、調査で重大な違反が確認された場合には、その場で現行犯逮捕されることもあります(例:客引きの現認、無許可の接待行為の現認、立入拒否時の現行犯など)。
③逮捕・呼び出し・勾留
内偵捜査や立ち入り調査によって風営法違反の事実が明らかになった場合、現行犯逮捕または通常逮捕される可能性があります。
ただし、全ての違反が逮捕につながるわけではなく、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断された場合は、逮捕されずに在宅事件として捜査が進められます。この場合、警察からの呼び出しを受けて出頭し、任意で取り調べを受けることになります。
逮捕された場合、警察での取り調べ後に検察官へ送致され、勾留が認められると、最長で23日間もの長期間にわたり身柄を拘束される可能性があります。
④起訴・不起訴と刑事処分
検察官は、警察の捜査結果をもとに、被疑者を起訴するかどうかを最終的に決定します。略式起訴で罰金に留まる例もある一方、悪質・再犯等では公判請求され拘禁刑となる場合もあります。
起訴されて有罪判決が確定すれば前科となり、将来の風俗営業許可の取得にも深刻な影響を及ぼすことになります。
風営法違反で通報されたときの対応手順
各ステップで冷静かつ適切に行動することが、処分の長期化・深刻化を防ぐ鍵です。警察や行政の対応は段階的に進むため、以下では通報直後から再発防止までの対応手順を、実務上の流れに沿って解説します。
- 責任者に対応を一本化する
- 身分証の提示を求め、提示義務書類のみ示す
- 監視映像・出勤簿などの記録を保存する
- 弁護士に即時連絡し、取調べ等への同席を依頼する
- 従業員・顧客への案内を統一し、過剰な発言を控える
- 是正措置を実施し、再発防止計画を策定する
①責任者に対応を一本化する
通報を受けた店長やオーナーは、まず冷静さを保つことが最も重要です。慌てた言動や独断的な判断は、事態を不利にしかねません。
行政や警察が到着する前に、営業許可証や従業員名簿など、提示義務のある必要書類を手元に揃え、基本体制を整えます。「警察・行政への対応は責任者が行う」と周知し、窓口を一本化します。
初動段階で責任者への窓口を一本化し、統一的な姿勢を示すことで、不要な混乱を防ぎ、後の法的・行政的対応に備えることができます。
②身分証の提示を求め、提示義務書類のみ示す
警察官や行政職員が来店した際には、まずは「身分証明書」や「立ち入り証」の提示を求め、担当者の氏名などを記録します。対応窓口は必ず店長やオーナーに一本化してください。
立ち入り調査では、許可証や従業員名簿など提示義務のある書類については提出する必要がありますが、会計帳簿や経理書類など経営資料の提出要求は、拒否できる場合があります。また、客への質問も原則として拒否できます。
供述調書の作成を求められた場合は、黙秘権や署名・押印の拒否権を把握し、不利な供述を避ける姿勢を貫くことが不可欠です。場当たり的な発言はせず、常に法的視点を意識した冷静な対応を心がけてください。
なお、適法に営業していても冤罪とされる可能性があります。詳しくは風営法違反の冤罪が起きやすい8つのケースと対処法をご参照ください。
③監視映像・出勤簿などの記録を保存する
通報後は、店舗にとって有利な証拠を迅速に確保・保全することが不可欠です。
監視カメラ映像や通話記録は上書きされないよう保存し、従業員の出勤簿や名簿なども整理し、提示できるよう備えます。
ここで重要なのは、不利な証拠であっても毀棄・隠匿しないこと(証拠隠滅は別の犯罪リスク)。
証拠を隠滅したとみなされると、証拠隠滅罪の疑いで逮捕リスクが格段に高まるため、絶対に避けてください。
証拠や記録を正しく保全・管理することで、後の弁護士による防御や行政との交渉において、事実に即した主張を行うための強力な根拠となります。記録の正確な管理は、誤解や冤罪を防ぐ積極的な手段です。
④弁護士に即時連絡し、取調べ等への同席を依頼する
風営法に精通した弁護士への相談は、通報直後から最優先で取り組むべき対応です。
警察からの呼び出しや取調べが行われる際には、必ず弁護士に同席してもらい、不利な供述を避けるための助言を受けます。供述調書は署名・押印の前に弁護士と内容を必ず確認し、相違点は署名前に訂正を求めます。
弁護士は、行政処分や刑事責任を最小限に抑えるための戦略を立て、店舗の法的な対応方針を決定する上で不可欠な存在です。早期に連携することで、事態の長期化やリスクの拡大を未然に防ぐことが可能になります。
⑤従業員・顧客への案内を統一し、過剰な発言を控える
通報や調査によって従業員が動揺しないよう、責任者以外は対応しない方針を改めて周知し、不安を取り除くための丁寧な説明が求められます。
責任者が冷静に状況をコントロールすることで、従業員に安心感を与え、落ち着いた行動を促すことが大切です。顧客対応は事実ベースで簡潔に、過剰な情報発信は避けます。また、SNSや口コミなどで事実と異なる情報(風評)が広がる恐れがあるため、弁護士と協議の上、必要に応じて削除依頼や法的措置を検討します。
風評被害の拡大を防ぎ、店舗の信用を維持するための体制を速やかに構築することが重要です。
⑥是正措置を実施し、再発防止計画を策定する
行政処分や摘発のリスクを真摯に受け止め、違反が認められる場合は一時的な営業休止を含む是正措置を速やかに実施します。
その後は、法令遵守のための是正措置(例:営業時間短縮、設備改善、スタッフ教育の強化)を速やかに実施し、再発防止の体制を整えます。そして、弁護士や行政と協議し、改善の姿勢を明確に示した上で営業再開の可否を判断することが望ましい流れです。
真摯な反省と適切な再発防止策は、行政処分の軽減や、失った社会的な信頼の回復に繋がる可能性があり、店舗を長期的に守るために不可欠な対応となります。
風営法違反の通報(住民苦情・相談を含む)により摘発された事例
住民・利用客などからの通報や相談が端緒となり、内偵→立ち入り→摘発へ至るケースは少なくありません。ここでは、実際に住民や関係者からの通報が発端となって摘発された代表的な事例を紹介します。
近隣住民の苦情による無許可接待営業の摘発
この事例では、近隣住民からの苦情が発端となり、東京・池袋のガールズバー「バニーフラッシュ」の経営者らが、無許可で接待営業を行ったとして摘発されました。
ガラス張りの店内で露出度の高いバニーガールが接客する様子が、特に通学路を利用する子供の目に触れる状況が続き、地域住民の激しい苦情や取り締まりの要望が警察に寄せられました。この住民からの通報を受けて警察が内偵捜査に着手し、実際につい立のないカウンター内で女性従業員が男性客の真横で接客する「接待行為」が確認されています。
地域住民の声が、約2年4カ月で2億5000万円を売り上げていたとされる無許可営業の摘発へとつながりました。
参考:2億5000万円を売り上げた「ガールズバー」が摘発 "露出過多"バニーが通学路から丸見えで近隣住民激怒 - ライブドアニュース
匿名の通報から発覚した無許可接待営業
この事例は、埼玉県大宮区のガールズバー「LUANA」の経営者らが、無許可での接待営業で逮捕された事案です。
この店舗は、女性従業員がカウンター越しに酒を提供しながら客と談笑するサービスを提供し、特定の従業員を指名できるシステムもありました。
摘発のきっかけとなったのは、2021年10月ごろに警察に寄せられた匿名の通報でした。匿名通報を受けて県警が捜査を開始し、約2年間で約8000万円を売り上げていたとされる営業実態を確認しました。この事例は、匿名通報でも信憑性が確認されれば、組織的捜査と摘発に至ることを示しています。
参考:大宮ガールズバー、無許可で女性が接客…酒出し談笑、指名も可 女経営者ら逮捕、1年で8千万円を売り上げた|埼玉新聞|
苦情が半数以上を占めた歓楽街での客引き摘発
この事例は、埼玉県警が大規模な客引き行為の一斉取り締まりを実施し、客引きを行った男6人を現行犯逮捕した事例です。
取り締まりの背景には、県内の主要な歓楽街における客引きに関する通報や苦情の多さがあります。特に、取り締まりの対象となった大宮駅周辺など7カ所では、当時寄せられた客引きに関する通報や苦情の半数以上が発生していました。
このように、通報・苦情が集中するエリアでは重点警戒と一斉取り締まりが実施されやすいことがわかります。
参考:「キャバクラどうですか」警戒中の私服警察官に声かけ 客引き行為した疑い、男6人逮捕 大宮や川口など7カ所の歓楽街、夏休み前に県警が一斉取り締まり|埼玉新聞|
未成年アルバイトの相談による深夜接客の摘発
この事例は、愛媛県松山市でガールズバーを経営する男が、18歳未満の少女4人を午後10時以降に接客業務に就かせたとして、年少者雇用制限違反の疑いで逮捕された事案です。
この事件は、関係者から警察に寄せられた「未成年者がガールズバーで働いている」という内容の相談が発端となりました。この相談を受けて警察が捜査に着手し、男が経営するガールズバーで実際に未成年者に深夜帯に酒の提供を含む接客業務をさせていた事実を確認しました。
この事例は、従業員や関係者からの相談が、年少者雇用制限違反の摘発に直結し得ることを示しています。
参考:「未成年がガールズバーで働いている」風営法違反の疑いで40代の男逮捕 愛媛 | TBS NEWS DIG
ぼったくり通報から発覚した無許可営業と未成年雇用
この事例は、熊本市中央区の飲食店で、実質経営者の男が無許可での接待営業と18歳未満の女子高校生への接客業務をさせたとして逮捕された事案です。
この店舗については、客から「ぼったくりだ」とする複数の通報が寄せられており、警察がこの通報を受けて指導のために立ち入った際に、17歳の女子高校生が客の接待をしていることが発覚しました。複数の通報による警察の指導が、さらに重大な風営法違反(無許可営業と年少者雇用制限違反)を見つけ出す引き金となったケースです。
男は実質的な経営者であり、通報がきっかけで店の営業が短期間で停止に追い込まれています。
「ぼったくり」通報が端緒となり、無許可営業や未成年雇用など重い違反が判明する場合があります。
参考:「ぼったくり」通報相次いだ店で17歳女子高生が接待か 実質経営者の33歳男に風営法違反の疑い 熊本 - ライブドアニュース
住民の相談から発覚したマンション内での売春営業
この事例は、大阪府羽曳野市のマンションの一室で、売春防止法違反や風営法違反の容疑で男女が逮捕された事案です。
この裏風俗的な営業が発覚したきっかけは、別棟の同じ部屋番号の住民からの相談でした。住民から警察に「男性がよく間違えて訪ねてくる」という相談が寄せられ、これが捜査の糸口となりました。
普通の住宅街にあるマンションの一室で秘密裏に行われていた売春営業が、住民の通報・相談というごく日常的な事象から発覚しています。
この事例は、目立ちにくい場所での違法営業でも、住民の相談が捜査を動かし摘発に繋がることを示しています(参考:産経新聞 令和7年3月10日配信)。
風営法違反の通報を防ぐための日常的な対策
日々の法令遵守体制と現場運用の徹底が、通報・摘発の最大の予防策です。
まず、法令遵守の基本体制の確立が必須です。
具体的には、来店客や警察・行政からの立ち入りがあった際に最も確認される従業者名簿を常に最新かつ正確な状態に保つ必要があります。特に、従業員の採用時には年齢確認や在留資格の確認を厳格に行い、18歳未満・20歳未満の者への深夜労働や酒類提供を厳しく禁じるためのマニュアルを徹底しましょう。営業許可証の掲示や、店舗の照度、区画に関する構造基準が違反状態になっていないかも日頃から確認し、無用な指摘を受ける原因を取り除いてください。
次に、従業員への継続的な教育が重要です。風営法で禁止されている行為(客引き、無許可の接待行為、未成年者への酒類提供など)について、具体例を交えた研修を定期的に実施し、スタッフ全員が法令を正しく理解し、意識を高めることが重要です。店舗内での違反行為や顧客からのトラブルが発生した場合の報告体制を明確にし、迅速な是正措置が取れるようにしておくべきです。
さらに、顧客トラブルと住民苦情の予防も重要です。
料金体系を透明化し、明確な表示と丁寧な説明を徹底することで、「ぼったくり」などによる顧客からの通報リスクを軽減できます。近隣住民からの苦情を防ぐため、騒音対策の徹底や、店舗周辺での客引き行為の禁止を厳守し、地域社会との良好な関係を築く努力を継続的に行うことが、結果的に警察の警戒対象となることを避ける最大の防御策となります。
これらの予防策を継続的に実施することで、通報や行政処分、刑事罰のリスクを大幅に減らし、安定した事業運営を実現することができます。
風営法違反の通報に関するご相談について
通報を受けた、あるいは通報の可能性がある状況では、警察の動きが見えない段階でも内偵捜査が進んでいる場合があります。
弁護士が早期に関与することで、逮捕や営業停止といった深刻な事態を回避できる可能性が高まります。
若井綜合法律事務所では、風営法違反の通報・摘発事案において、刑事事件と行政処分の両面から対応してきた実績があります。
経営者や店舗責任者の方が置かれた状況を丁寧に伺い、捜査対応や営業継続のための具体的な戦略をご提案します。
風営法に精通した弁護士が、あなたの店舗と従業員を守るために全力でサポートします。
ご相談は全国どこからでも、24時間365日お受けしています。
警察からの連絡や立ち入りがある前に、できるだけ早い段階でご相談ください。
初期対応の質が、その後の展開を大きく左右します。まずはお気軽にお問い合わせください。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|