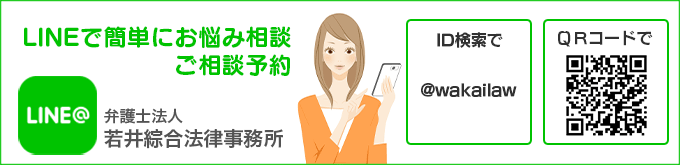配偶者に勝手に離婚届を提出されそうな場合に、それを阻止するための対策が「離婚届不受理申出(りこんとどけふじゅりもうしで)」の制度です。
とはいえ、
- 離婚届不受理申出とは?制度の内容がよくわからない…
- 不受理申出をしたら相手にバレるのでは…
- 申請方法や取り下げ方法がわからない…
とお悩みの方や、立場を変えて、
と悩まれている方もいることでしょう。
そこでこの記事では、離婚問題に強い弁護士がこれらの悩みを解消していきます。
記事を最後まで読むことで、勝手に離婚届が提出されることを防げるようになりますし、逆に、離婚届不受理申出を出された側の対処法についても知ることができます。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|
目次
離婚届不受理申出とは?

離婚届不受理申出とは、配偶者の一方が、もう一方の意思に反して離婚届を提出する場合に備えて、役場に対してその離婚届を受理しないよう申出ができる制度です。この申出をしておくことで、申出をした本人以外の者が離婚届を提出しても受理されませんので、知らぬ間に離婚が成立していたという事態を防ぐことができるメリットがあります。
本来、協議離婚が成立するためには①当事者の離婚に関する合意②離婚届の提出、この2つの要件を満たさなくてはなりません。しかし実務上は、夫婦の一方の配偶者の同意がない場合(①の要件を満たさない場合)でも、離婚届がなされれば離婚は成立してしまいます。なぜなら、離婚届を受けた役所は提出された書類を審査しますが、あくまでも形式的に審査するだけで、本当に当事者が離婚についての意思が合致しているかどうかまでは確認しないからです。
こういった行為は、私文書偽造罪、偽造私文書行使罪、電磁的公正証書原本不実記録罪などの違法行為ですが、そのことと、離婚届が役所に受理されてしまうことは別問題です。
「①当事者の離婚に関する合意」の条件が欠けている以上、後からこの離婚を取り消すことはできますが、手続きが煩雑ですし、戸籍に離婚したことが記録が残ります(これも後で元に戻せますが非常に面倒です)。そういった事態を回避するためにも、夫婦の一方が無断で離婚届を出す可能性が少しでもある場合は、離婚届の不受理申出をしておくに越したことはありません。
離婚届を勝手に出すとどうなる?犯罪になる?弁護士が解説します
離婚不受理申出をすると相手にバレる?

離婚届不受理申出をしただけでは、相手配偶者にバレることはありません。不受理申出を受け付けた役所が相手配偶者に通知することはないからです。ただし、不受理申出がされている状況で相手配偶者が離婚届を提出しにいくと、役所から不受理申出がされていることを理由に離婚届の受理を拒否されますのでそれでバレます。
ちなみに、離婚届不受理申出がされている状況で相手が離婚届を提出しようとすると、不受理申出をした側に対して「離婚届の提出がされそうになりました」と役所から連絡がもらえます。これにより、相手配偶者が早期に離婚をしたいと考えていることが発覚します。
離婚届の不受理申出の申請方法は?

申請に必要な物は、①不受理申出書、②印鑑(認印可。ただしゴム印は不可)、③身分証(マイナンバーカード、免許証、パスポート等)となります。
不受理申出書は各都道府県の市区町村役場の窓口で貰えます。役場によってはホームページからダウンロードすることもできます。「離婚届不受理申出書 ダウンロード 〇〇(申請する市区町村名)」とネット検索してサイトからダウンロード可能か確認してみましょう。なお、札幌市や大阪市などでは役場ホームページから離婚届不受理申出書のダウンロードが可能ですが、その離婚届不受理申出書が全国共通で使えるとは限りません。もしそれをご利用になられる場合は、ご自身が不受理申出をする予定の役場に電話をして、他の市区町村役場のサイトからダウンロードしたものでも受理してもらえるかの事前確認が必要です。
申請場所は、申請する人の本籍地か、住所地(住民票上の住所だけでなく、一時滞在している場所を管轄する役所でも構いません)の役場です。
原則として、郵送や代理人による申請はできませんが、病気等の理由により申請者本人が役場に足を運べない場合は、離婚届の不受理申出書を公正証書にすることで例外的に郵送や代理での申請も可能となります。
なお、市区町村役場によっては、夜間・休日窓口や宿直室で不受理申出書を受け取ってくれますが、あくまでも「預かり」という形です。翌開庁日に担当窓口の職員が内容を確認して不備がなければ、申出書を提出した日に遡って、不受理申出の効力が生じます。
離婚届の不受理申出の取り下げについて

離婚届の不受理申出は、申出をした本人が取り下げるまで有効です。
そのため、後に夫婦間で協議離婚の話がまとまって、離婚届を提出するだけの段階になれば、不受理申出の取下げをしなくてはなりません。
必要な物は、①不受理申出の取下げ書、②印鑑、③身分証です。
取下げ書は、役所の窓口または、ここから不受理申出の取り下げ書をダウンロードできます。
届出の場所や提出方法については、離婚届の不受理申出の場合と同じです。
離婚届不受理申出をされたら離婚できない?

これまでは、離婚届不受理申出をする側の立場に沿って解説してきましたが、ここでは立場を変えて、離婚届けを提出したい側の視点で考えてみます。
離婚したい側の配偶者は、相手に離婚届不受理申出をされた場合であっても離婚できないわけではありません。その後協議で合意すれば離婚できますし、不受理申出がされていても、離婚調停の申立てや離婚裁判の提起はできますので、その結果離婚が成立することもあるからです。
たとえ不受理申出をした側がまだ離婚をしたくないと望んでいた場合でも、不貞行為や悪意の遺棄など、法定離婚事由に該当する離婚事由が不受理申出をした側にあれば、裁判で離婚請求が認められることもあります。
まとめ
夫婦の相手方が自分に内緒で離婚届を出してしまった場合、大変なことになりかねません。
虚偽の離婚届が役所によって間違って受理された場合や、夫婦の一方が記載済みの離婚届を相手に預けていたものを勝手に役所に提出してしまった場合、その夫婦は離婚したものとして扱われることになってしまうからです。
そのような場合に離婚を取り消すためには、家庭裁判所において調停や裁判などを行わなくてはならなくなります。
それでは手間暇がかかり、精神的にも大変な思いをすることになってしまいます。
夫婦の関係に、もしそのような危険性がある場合には、今回ご紹介した「離婚届の不受理申出」という制度の利用を検討する必要があります。
不受理申出が間に合わずに離婚が成立してしまいお困りの方や、その他、離婚問題でお悩みの方は、当法律事務所までお気軽にご相談ください。きっとお力になれると思います。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|