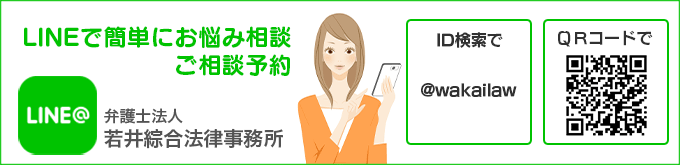- 「離婚する場合、どのような費用がかかるのだろう…」
- 「離婚に向けて準備しておくべきお金(貯金)はいくらくらいだろう…」
- 「離婚するにあたって、相手にどのようなお金を請求できるのだろう…」
このようにお考えではないでしょうか。
何事もお金のことを考えることなしに行動することがままならないのが世の中です。ふと、「離婚どうしよう」と考えたときにも、一番気になるのはその“費用”についてではないでしょうか。
そこでこの記事では、離婚問題に強い弁護士が、
- 離婚の準備で必要となるお金
- 離婚するにあたってかかる費用
- 離婚の際に相手に請求できるお金
- 離婚後に受けることができる給付金や税金の減免措置
などについてわかりやすく解説していきます。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|
目次
離婚の準備段階で必要なお金
離婚の準備段階で必要なお金は次のとおりです。
スキルアップのための費用
離婚の準備で真っ先に取り組まなければいけないことが離婚後の収入の確保です。
あとで紹介するように、確かに、離婚すると養育費や児童手当、児童扶養手当などを受け取ることができますが、それだけで生活していけるわけではありません。養育費については約束どおりきちんと払ってもらえるかもわかりません。そのため、離婚する前から、離婚後自力で稼いでいける力を身につけておくことが大切です。
今現在、正社員として働いており、離婚後も変わらず働いていくことができる場合は別ですが、無職の場合はもちろん、パートやアルバイトで収入が不安定な場合は、相手に離婚を切り出す前に自力で稼いでいける職に就く準備をしておく必要があります。
希望する職種によっては資格や免許の取得が必要となる場合もあり、そのために学校に通ったり、講座を受講する場合は費用がかかります。
別居の費用
離婚する前に別居する場合は別居の費用がかかります。
今の家から出ていく場合は引っ越し費用がかかります。別居先が民間のアパートの場合は家賃のほか、敷金・礼金などの初期費用がかかることもあります。
相手より収入が低い場合、子どもと一緒に別居する場合は相手に婚姻費用を請求できますが、婚姻費用だけで生活していけません。別居する前に、家具・雑貨などの購入費用や新生活に慣れるまでの当面の生活費も貯めておく必要があります。
離婚を見据えて別居する場合は、別居の前からご自分の仕事や子どもの生活の計画をきちんと立てた上で別居するのが基本です。
専門家の費用
続いて専門家の費用です。
離婚の準備段階では証拠集めも重要です。相手が不貞していないか怪しい場合は、相手に離婚(別居)を切り出す前に不貞の証拠を集めておく必要があります。不貞の証拠はご自分で集めることも不可能ではないですが、相手にバレずに使える証拠を集めるには探偵に依頼した方が確実です。
また、相手との交渉などを弁護士に任せる場合は弁護士費用がかかります。離婚の準備段階では着手金を用意する必要があるでしょう。依頼する法律事務所により異なりますが、着手金は「10万円~30万円(税別)」が相場で、一括払いを求められることが一般的です。
離婚するにあたってかかる費用
続いて、相手に離婚を切り出した後にかかる費用についてみていきましょう。
円満離婚のケースでかかる費用
お互いの話し合いで離婚の合意に達して円満に離婚する協議離婚の場合には、離婚届を役所に届け出るだけですので特に費用はかかりません。
もっとも、前述の通り、離婚条件等につき相手との交渉を弁護士に依頼した場合は弁護士費用がかかります。
離婚準備の段階で着手金を払っている場合は、別途、「報酬金、日当費、実費」などの費用を負担する必要があり、着手金とこれらの費用を合算すると、協議離婚を弁護士に依頼した場合の費用相場は20万円~60万円程度となります。
ただし、上記相場は、離婚の成否のみを争っている場合の費用です。慰謝料・養育費・財産分与・親権なども争点となっている場合には、成功報酬が別途かかります。離婚の弁護士費用について詳しく知りたい方は、離婚の弁護士費用はいくら?相場と安くするためのポイントを解説を参考にすると良いでしょう。
なお、相手方と離婚協議を行った場合には、話し合って決めた内容・合意条件について「離婚協議書」や「公正証書」を作成することが一般的です。口約束だと後で「言った・言わない」の争いになることが多いためです。この離婚協議書、公正証書の原案の作成を弁護士に依頼した場合には5万円~10万円程度の費用がかかります。
また、公正証書を作成する場合は公証人手数料を公証役場に払います。費用は公正証書に盛り込む内容にもよりますが、おおむね「2万円~6万円」の範囲でおさまることが多いです。
調停や訴訟で離婚する場合の費用
協議離婚できず、調停を申し立てる場合は収入印紙代と郵便切手代がかかります。収入印紙代は申立件数1件につき「1,200円」です。離婚調停のみ申し立てる場合は1,200円で済みますが、婚姻費用の未払いに関する調停を申し立てる場合は2,400円がかかります。
郵便切手代はおおむね「1,000円~1,500円」の範囲でおさまることが多いですが、具体的な金額は申立先の裁判所により異なりますので、あらかじめ確認しておく必要があります。
なお、離婚調停を弁護士に依頼した場合の費用相場は40万円~70万円です。ただし、この相場はあくまでも離婚の成否のみを争っている場合の費用です。養育費、慰謝料、財産分与等についても争点となっている場合には、この額より大幅に増額する可能性があることは協議離婚の場合と同様です。
調停が不成立に終わり、離婚裁判を提起する場合も収入印紙代と郵便切手代がかかります。
離婚のみ請求する場合の基本の収入印紙代は「13,000円」ですが、あわせて慰謝料を請求する場合は慰謝料の収入印紙代と比べて多い方が基本の収入印紙代となります。
また、慰謝料のほか、養育費や財産分与などもあわせて請求する場合は「1,200円(養育費は子ども一人分につき1,200円)」が加算されます。
郵便切手代はおおむね「5,000円~6,000円」の範囲にでおさまることが多いですが、具体的な金額は申立先の裁判所により異なりますので、あらかじめ確認しておく必要があります。
なお、離婚裁判を弁護士に依頼した場合の費用相場も、離婚調停と同じ40万円~70万円程度です。ただし、離婚の成否以外に、養育費、慰謝料、財産分与についても争点となっている場合には、この額より大幅に増額する可能性があることはこれまでと同様です。
離婚の際に相手に請求できるお金
離婚の際に相手に請求できるお金は次のとおりです。なお、離婚するからといって必ず請求できるわけではなく、請求できるかどうかは個々のケースにより異なりますので注意が必要です。
未払いの婚姻費用
まず、未払いの婚姻費用です。
婚姻費用とは婚姻期間中に発生する生活費です。法律上の夫婦関係にある以上は、夫婦は互いに婚姻費用を分担する義務を負います。離婚に先立ち別居している場合でも、夫婦関係が続いている限り、夫婦は婚姻費用を負担する必要があります。
別居する(した)場合、収入が少ない方、あるいは収入が多くても子どもと一緒に生活している方が他方に婚姻費用の支払いを求めることができます。この婚姻費用に未払がある場合は、未払い分を離婚時に払うよう請求するか、財産分与で他の財産と清算することができます。
なお、未払いの婚姻費用を請求できるのは、過去に婚姻費用の支払いの意思表示をしていた場合に限ります。また、請求できる金額はあくまで請求時から離婚時までです。婚姻費用を請求せずに生活してきた場合、婚姻費用がなくても生活できるお金があったと考えられてしまうためです。
離婚に先立って別居するときは、なるべくはやい段階で婚姻費用を請求しておきましょう。
養育費
次に、養育費です。
養育費は子どもと離れて暮らす親(非監護親)が子どもと一緒に暮らす親(監護親)に払います。年収の多い少ないは関係ありません。非監護親より監護親の方が年収が高くても払う必要があります。
子どもが未成熟子の間は養育費の支払義務は続きます。未成熟子とは、精神的・経済的に親から自立できない子どものことです。したがって、子どもが大学生や大学院生でも養育費を払わなければならない場合がありますし、反対に、高校を卒業して就職した子どもの養育費は払わなくてよいということになります。
養育費の金額は裁判所が公表している算定表が基準となりますが、これにとらわれることなく親同士で自由に金額を設定できます。ただし、あまりに高額な金額を設定すると、未払いや減額の対象となってしまいますので注意が必要です。
離婚しても法律上の親子関係が絶たれるわけではありませんから、養育費の支払義務は続きます。離婚したから、非監護親が面会交流に応じないからというのは、養育費の支払いを拒否する理由にはなりません。また、再婚も基本的には同様です。
離婚慰謝料
次に、離婚慰謝料です。
離婚慰謝料とは、不貞やDVなど、相手の有責行為によって離婚することになったことにより受けた精神的苦痛に対する賠償金です。
離婚するから、相手が気に食わないからといって必ず請求できるものではありません。相手の一方的な非によって離婚せざるをえなくなったといえる事情が必要です。また、有責行為当時、すでに婚姻関係が破綻していたときは慰謝料請求が認められないこともあります。
離婚慰謝料は「50万円~300万円」が相場ですが、あくまで目安で、話し合いでは夫婦で自由に金額を設定できます。
財産分与
次に、財産分与です。
財産分与とは、夫婦共有名義の財産、あるいは婚姻後に夫婦で協力して築いたといえる財産(共有財産)を離婚時に清算するものです。
預貯金のほか、現金・へそくり、退職金、家、車、生命保険・学資保険の解約返戻金、家具・家電など、共有財産といえるものは財産分与の対象となります。また、プラスの財産のほか、生活費のための借金や車・家のローンなどのマイナスの財産も共有財産といえる限り、財産分与の対象となります。
一方、結婚前から所有していた財産、結婚後に相続、贈与など相手とは無関係に取得した財産は特有財産といい、財産分与の対象にはなりません。
財産分与ではお金の支払いを求めることができるのはもちろん、車や家などの現物の給付を求めたり、家の利用権の設定を求めることもできます。
離婚時の財産分与とは?少しでも多くもらうための4つのポイント
年金分割
次に、年金分割です。
年金分割は厚生年金保険料の納付実績を夫婦で分け合うものです。夫と妻で納付実績に差があるまま離婚すると、将来受け取る年金に差が生まれることから、離婚時に納付実績を分け合うこととしたのが年金分割です。
年金分割ではあくまで「厚生年金」保険料の「納付実績」を分け合うものです。「国民年金」については、将来、同額の年金が支給されるため国民年金保険料の納付実績は年金分割の対象ではありません。また、将来受け取る年金自体を分け合うものでもありません。離婚後の保険料の納付状況によっては、夫婦の間で支給される年金額に差が生まれることも想定されます。
年金分割には合意分割と3号分割があります。合意分割するには、まずは年金分割することと、納付実績を分ける割合(最大2分の1)について夫婦で話し合って合意する必要があります。合意できない場合は調停を申し立てて調停での合意を目指します。一方、3号分割は夫婦の話し合いは不要で、年金分割される側が離婚後に手続きをとれば足ります。
離婚後に受け取ることができる給付金や税金の減免措置
最後に、離婚後に受け取ることができる給付金や税金の減免措置についてご紹介していきます。
給付金・支援金
給付金は次のとおりです。
児童手当
まず、児童手当です。
児童手当は現在、0歳~15歳に到達した日以後の最初の3月31日までの間にある子をもつ親(所得制限のない親)に対して、支給されます。
金額は、
- 0歳~3歳未満:月15,000円
- 3歳~小学卒業:第1子/第2子月10,000円 第3子以降月15,000円
- 中学入学~卒業:月10,000円
です。
6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)の年3回にわけて支給されます。
一定の手続きをとれば離婚前(別居中)でも児童手当の受給者を変更して児童手当を受け取ることができます。
児童扶養手当
次に、児童扶養手当です。
児童扶養手当は、0歳~18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの間にある子をもつ母子家庭あるいは父子家庭の親(所得制限のない親)に対して、支給されます。支給を受けるには役所に申請をして受給認定を受ける必要があります。
金額は、子ども1人の場合、親の所得に応じて「1万1060円~43,070円」の間で決められます。子どもが2人いる場合は上記の金額に「5,090円~10,160円」が、子どもが3人以上いる場合は子ども1人につき「3,050円~6,090円」が加算されます。
親の所得には同居している人(祖父母など)の所得も含まれることに注意が必要です。その人たちの生計でも子どもを養っていると考えられてしまうからです。
5月(3月~4月分)、7月(5月~6月分)、9月(7月~8月分)、11月(9月~10月分)、1月(11月~12月分)、3月(1月~2月分)の年6回にわけて支給されます。
DVを受けているなどの特殊な場合は、離婚前から受け取ることができます。
ひとり親家庭医療費助成
次に、ひとり親家庭医療費助成です。
ひとり親家庭医療費助成は、ひとり親家庭の親や子ども(0歳~18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの間にある子)の医療費を自治体が負担する制度です。
たとえば、通院については月500円まで、入院までは自己負担なしとし、それ以外の費用は自治体が負担するというものです。助成の内容は自治体ごとに異なりますので、離婚後にお住いになる自治体のホームページなどで内容を確認しておきましょう。
所得制限が設けられており、所得を超えるとこの制度を使うことはできません。
参考:ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)東京都福祉保健局
こども医療費制度
次に、こども医療費制度です。
所得制限にひっかかり、ひとり親家庭医療費助成を使うことができない場合はこちらの制度を使うことになります。ひとり親家庭医療費助成と異なり、親の医療費は自治体が負担してくれないことに注意が必要です。
参考:千代田区ホームページ - こども・高校生等医療費助成制度(乳幼児~高校生等)
ひとり親家庭住宅助成
次に、ひとり親家庭住宅助成です。
ひとり親家庭住宅助成は、月一定額以上の家賃を払っているひとり親家庭に対して、自治体が一定金額を助成してくれる制度です。
自治体によって制度を設けているところ、設けていないところがありますので、離婚後にお住いになる自治体のホームページなどで確認しておきましょう。
民間の家賃が高く感じる場合は公営住宅への入居も検討してみましょう。
参考:【ひとり親】【0~20歳】ひとり親家庭のための手当・助成|武蔵野市公式ホームページ
税金の減免措置
税金の減免措置は次のとおりです。
寡婦控除
まず、寡婦控除です。
控除とは差し引くという意味で、所得税の計算において所得金額から寡婦控除額の27万円を差し引くことで、所得税の計算対象となる課税所得金額が安くなり、所得税を安く抑えることにつながります。
寡婦控除は所得金額が500万円以下で、かつ、夫と死別した後再婚していない、あるいは夫と離婚し、離婚後再婚していない扶養親族(子どもなど)をもつ女性が受けることができます。
ひとり親控除
次に、ひとり親控除です。
ひとり親控除は所得金額が500万円以下で、現在婚姻していない、もしくは同様の事情にあると認められる人がおらず、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいるひとり親が受けることができます。控除額は35万円です。
寡婦控除を受けることができる女性はひとり親控除を受けることはできません。
国民健康保険・国民年金保険料の減額・免除
次に、国民健康保険・国民年金保険料の減額・免除です。
離婚するまで配偶者の健康保険の被扶養者で、離婚後は親などの健康保険の被扶養者にならない、あるいは自身で健康保険に加入しないという場合は毎月国民健康保険料、国民年金保険料を払っていく必要があります。
ただ、健康保険に加入していたときと異なり、全額自己負担となりますので、離婚後の収入によっては大きな負担となることが考えられます。保険料を払っていけそうにない場合は、減額か免除の申請をしておきましょう。
保育料の減額・免除
次に、保育料の減額・免除です。
税金とは異なりますが、保育料は住民税(前年度の所得)によって決まりますので、0歳~2歳(3歳以降は保険料は無料)のお子さんをもつひとり親の方で、保険料の支払いが負担に感じる場合は減額・免除の申請をしておくとよいでしょう。
まとめ
離婚するには様々なお金がかかります。まずはどんなお金がいくらかかりそうなのか見積もった上で、相手に離婚を切り出す前に離婚資金を貯めておく必要があります。
離婚では、養育費などのお金を請求することができますが、それだけでは十分とはいえません。児童手当など離婚後に受け取ることができるお金や各種の支援・減免制度を活用しながら、お金をやりくりしていくことが大切です。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|