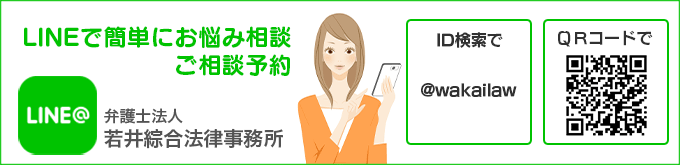このようにお考えではないでしょうか。
夫(妻)からモラハラを受けている方は、離婚せずに自分ひとりが我慢すれば家庭環境を問題なく収められると考えがちです。しかし、大好きな両親の一方が他方を精神的に虐待する様子を見て辛い思いをしない子供はいません。両親間のモラハラ行為に日常的に触れながら育った場合、以下で挙げるような悪影響を受ける可能性があります。
- 人間関係を上下関係で認識してしまう
- 合理性ではなく人の顔色を伺って物事を判断するようになる
- 子どもが人間関係に常に不安を持つようになる
- 子どもの心身に対して見えないダメージを与えてしまう
- 将来子どももモラハラを行うような大人に成長してしまう
この記事では、モラハラ離婚問題に強い弁護士が、
- モラハラが子供に与える影響
- 子どもにモラハラの悪影響が現れていないかチェック項目
などについてわかりやすく解説していきます。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|
モラハラが子どもに与える悪影響
人間関係を上下関係で認識してしまう
基本的に人間関係には上下関係というものはなく、すべての人は人格的に対等です。職場という特殊な環境においても、当事者の合意した範囲内で一定の者の指示に従うことが約束されているにすぎませんので、職場を離れれば管理・被管理という関係は消滅します。
しかし、モラハラが行われている家庭においてはあらゆる形で上下関係があるかのような人間関係が構築されている可能性が高いです。例えばあなたの家庭では以下のような熾烈な上下関係が作り上げられていませんか。
- 妻<夫
- 子ども<親
- 弟・妹<兄・姉
それらの上下関係が複合的に絡み合っていることもあります。つまり、夫が妻に対してモラハラを行い、妻は子どもに対してモラハラを行う、そして子どもらは年長者が年少者に対してモラハラを行うといった具合です。
このような人間関係のもとで弱い立場にある子どもはモラハラ被害を受けないようにするため「上に立たなければならない」とか「自分より下の人間を作らなければならない」と考えるようになってしまいます。
その結果「いま自分は人間関係のピラミッドのどこに位置しているのか」ということばかり気にして生活するようになります。そのような歪んだ認知を抱いた子どもは相手を踏み台にしたり、他人を蹴落としたりを平気で行えるような人間になってしまいます。
合理性ではなく人の顔色を伺って物事を判断するようになる
ある結果が起こった場合、「何が原因だろう」と考えられる人が合理的な人です。理由を考えられることで根拠のないことには騙されず、正しい選択肢を選ぶことができるのです。
モラハラの場合、一見加害者には合理的な言い分があるように思えますが、結局は被害者に対する個人攻撃である場合がほとんどです。同じことをしたとしても「あなたの場合は許されない」「他の人であれば許される」というように人を見てルールが変わってしまいます。結局は加害者が気にくわない場合には許されず、気に入る場合には許されるという気分で決めているに過ぎないのです。
そこでモラハラに日常的に触れている子どもは、一定の事柄を決断するのに人の顔色を伺って決断するようになります。物事が許されるか否かは「上位の人」が気分で決めることが刷り込まれているのでそれに反しないようにしようと努力します。
その結果、幼少期に「合理的にものごとを考える」という訓練がおろそかになります。合理的に考えることが苦手な人間に育ってしまうことは子どもにとっても大きなデメリットでしょう。
子どもが人間関係に常に不安を持つようになる
モラハラに接して育った子どもにとって人間関係とは相手の顔色を伺って判断していく作業です。つまり「上位の者」の気分次第で関係性は大きな影響を受けてしまいます。人間関係が信頼や誠意、愛情などとの結びつきが弱く、相手の気分に左右されるため非常に不安定なものとなります。
そのような子どもにとって人間関係が非常に脆弱な根拠に基づいて構築されているため、些細なことで自分が人間関係のピラミッドから転落していまう、上位の者から蔑(さげす)まれるのではいかと感じます。他人の気分ほど自分がコントロールできないものはありません。したがって、常に人間関係に不安を覚え、慢性的なストレスを感じながら生活しなければならない可能性もあるのです。
子どもの心身に対して見えないダメージを与えてしまう
モラハラに関しては子ども自身が直接のターゲットになっていなくてもそれを目の当たりにすることでも負のダメージが生じ得ます。頻繁に他者に対する嫌がらせや暴言を目撃することでも大きなストレスを感じます。人間は本来グループで生活していく社会的な生き物ですので被害者の感情についても強く共感を抱いてしまうのです。
そのような負の感情が生じた際にコルチゾールなどのストレスホルモンが分泌されます。ストレスホルモンは闘争本能ややる気を生じさせるなど短期間であれば有益ですが日常的に分泌されると体内の炎症を加速させ、脳にも影響すると言われています。
その結果、感情のコントロールが上手にできずメンタルが不安定になったり、記憶力が低下したり、適切な意思決定ができないという弊害が生じます。家庭環境のストレスからうつ病や適応障害などの精神的な病気を発症する可能性もあります。
将来子どももモラハラを行うような大人に成長してしまう
常日頃から家庭内でモラハラを目の当たりにしている子どもは、将来子ども自身もモラハラ行為を行うようになる可能性があります。
ここまで説明したように、モラハラが行われている家庭環境は子どもにとっても複数の悪影響を及ぼします。そのような環境で育った子どもはメンタルが不安定で感情のコントロールが上手にできない大人に育つ可能性があります。
そして、両親間でモラハラが行われている状況が刷り込まれている結果、「夫婦というのはこういうものだ」「こういう場合はこういう言動をしても良いのだ」という歪んだ認知が矯正されないまま成人してしまうのです。
その結果、幼少期に自分が受けていたり目の当たりにしたりしていたモラハラ行為を自分のパートナーや身近な人に行ってしまうのです。
子どもにモラハラの悪影響が現れていないかチェック項目
モラハラ夫に対して異常に恐怖心を抱いている
不安定な上下関係や親の顔色を受けがって生活しなければならない環境は子どもにとって苦痛です。そこで、子どもがモラハラを行っている親に対して異常な恐怖心を抱いていないか否かをチェックしましょう。
恐怖心の兆候として、以下のような要素が考えられます。
- 親を極端に避けて生活している
- 片方の親に対しては異様に取り繕い自分の成果を強調する
- モラハラを行う親の意向に沿う言動ばかりしている
子どもに恐怖心が見て取れるような場合には家庭環境の刷新を検討しなければなりません。
すでにモラハラ夫と似たような言動をとるようになっている
日常的に親のモラハラを見て育った子ども、加害者と同じ言動により被害者にモラハラを行うようになる可能性があります。子どもがそのような行動に出るのはモラハラを受けている親を軽んじているというよりは、自分が被害を受けないための一種の「防衛行為」であると考えられます。
非常に硬直的な考え方ですが、「被害を受けないためには加害者になるしかない」「人間関係のピラミッドの上位に行かなければならない」などと感じた結果、モラハラ加害者と同じ言動をするようになる可能性があります。
幼少期にはモラハラの被害者であったといえる子どもが自己を守るために成長とともに家庭内でも加害者となってしまうのは、非常に悲しいモラハラの構造でしょう。
過程ではなく結果ばかり重視している
子どもであっても結果を追及することは良いことです。しかし、子どものうちから自分の功績ばかりを親に強調する姿勢は要注意です。自分の功績を親に認めてもらうことで「自分は人間関係の上位にいる」ということを必死にアピールしている可能性があります。
幼少期には、スポーツであり遊び・ゲームであってもその「過程」を楽しんだり試行錯誤したりする経験が非常に重要です。子どものうちから良い成績を取ったり相手を打ち負かしたりしたことばかりを強調する「硬直的なマインドセット」はモラハラによる家庭環境が原因である可能性もあります。
モラハラの悪影響から子供を守るためにすべきこと
警察や各種相談窓口にモラハラの相談をしておく
配偶者が子どもに対して怒鳴ったり、精神的な虐待を繰り返したりしている場合には、警察や相談機関に相談しておくことが重要です。
相談内容は調書や相談記録として書類が残り、このような相談実績は、後の離婚手続きの中で有効な証拠となりえます。
関係各所に相談できる環境を整えておくことで、別居後のトラブルも未然に防止できる可能性が高まります。
例えば、モラハラの場合には、別居後に配偶者が転居先に押しかけたり、子どもを連れ去ろうとしたりするケースもあるため、警察などに迅速に対応してもらう必要が出てきます。
警察に相談するときは、お近くの警察署へ行くか、警察相談専用電話#9110にダイヤルすることができます。警察署によっては専門の担当者が対応してくれる場合があります。
できるだけ早めに子どもを連れて別居する
何よりも優先すべきは子どもの心身の安全です。
配偶者が日常的にモラハラ行為を行い、子どもにも悪影響があると判断した場合には、できるだけ早く子どもを連れて別居する必要があります。
まずは、ストレス源である配偶者から子どもを物理的に引き離すことが重要なのです。
ここで、配偶者に無断で子どもを連れて家を出てしまうと、後々離婚手続きの際に不利になるのではないか、と不安な方もいるかもしれません。
しかし、配偶者のモラハラ被害から子どもを守るために別居した場合には、十分に正当な理由のある別居となるため安心してください。
また、別居期間中に必要となる生活費や子どもの養育費は、婚姻費用として相手方配偶者に分担を請求することができます。
親権を取得して、適切な内容で離婚する
離婚する際には子どもの親権者を定める必要があります。そのため親権を取得して引き続き子どもを養育できるようにする必要があります。
また、モラハラが原因で離婚する際には、慰謝料や養育費を適切に請求することが、今後子どもを養育していくためには重要なポイントとなります。
したがって、モラハラの悪影響から子どもを守るためには、法律の専門家である弁護士に相談して手続きを依頼することが賢明でしょう。
まとめ
今回は家庭内のモラハラが子どもに与える悪影響について解説しました。
モラハラの被害は決してあなただけにとどまるものではありません。将来のある子どものことを考えて、モラハラが日常的に行われている環境は是正される必要があります。モラハラについて一人で悩まれている方は、一度モラハラや離婚に詳しい弁護士に悩みを相談してみましょう。適切な法的アドバイスを受けることができるでしょう。
モラハラ離婚を弁護士に相談するメリットや依頼する費用について
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|