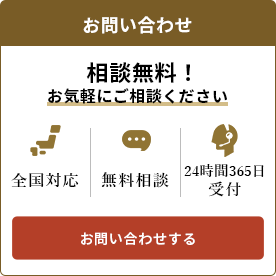「その場にいただけなのに、自分も罪に問われるのか」
「慰謝料はどうやって分担するの?」
「他のメンバーと足並みが揃わない」
集団での暴行事件に関わってしまった方の多くが、このような不安を抱えています。
集団暴行罪は、数人が団体または多人数の威力を示して共同で暴行を加えた場合に成立する犯罪です。
単に複数人で暴行するだけでは足りず、集団としての威力(威圧感や恐怖感)を示すことが要件とされています。実際に手を出していなくても、その場にいて集団の威力を示していた場合には、共同正犯とみなされることがあります。
集団暴行罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金で、暴力行為等処罰に関する法律(暴処法)に規定されており、刑法208条の暴行罪(2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)よりも重く処罰されます。
被害者に怪我を負わせた場合は傷害罪として、さらに重い処罰の対象となります。
この記事では、暴行事件に強い弁護士が、集団暴行罪の成立要件、判例、そして事件後に取るべき対応について解説します。
早期の対応が処分を左右することも多いため、全国どこからでも無料相談を受け付けています。まずは一人で悩まずにご相談ください。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
目次
集団暴行罪とは?
集団暴行罪は、数人が共同して暴行を行った場合に成立する犯罪です。ここでは、集団暴行罪の定義と法定刑、そして具体的にどのような場合に成立するのかを解説します。
集団暴行罪の定義と法定刑
集団暴行罪とは、数人が共同して暴行を加えた場合に成立する犯罪です。単に複数人で暴行するだけでは足りず、団体または多人数の威力を示して数人共同して暴行することが要件とされています。
これは刑法ではなく、特別法である「暴力行為等処罰に関する法律(暴処法)」の第1条に規定されています。集団暴行罪は、単独犯の刑法上の暴行罪(刑法208条)の加重類型という位置づけになります。
暴行罪の法定刑が「2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」であるのに対し、集団暴行罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」と定められており、拘禁刑の上限が長くなっている点から、暴行罪よりも重く処罰されます。
なお、2025年6月1日の刑法改正施行により、従来の「懲役」「禁錮」は「拘禁刑」に統一されました。本記事では現行法に基づき「拘禁刑」という表現を用いています。
集団での暴行は、単独での暴行に比べて、被害者に与える恐怖や精神的・肉体的な被害が甚大になりやすく、集団の威力によって凶悪性が増すため、これを特に重く処罰し、犯罪の抑止を図る目的から、暴行罪とは別に重い法定刑が設けられているのです。
この暴処法は、元々は暴力団による組織的な暴力行為や、戦後の学生運動・労働運動における集団的な暴力を取り締まるために制定されました。しかし、現代においては、暴行罪よりも重い刑罰が科される集団暴行罪が、学校での集団いじめや、複数の人間が関与した喧嘩など、日常に近い場面での共同暴行にも広く適用されるようになっています。
そのため、多数人で暴行事件を起こした場合には、自身が意図せずとも、集団暴行罪という重い罪に問われる可能性があることに注意が必要です。
具体的にどのような場合に集団暴行罪が成立するのか?
集団暴行罪は、以下のような場面で成立する可能性があります。
クラスメイト数人で共謀し、特定の生徒を体育館裏に呼び出して、複数人で取り囲みながら殴る蹴るの暴行を加えた場合。実際に暴行したのが一部のメンバーでも、その場にいた全員が集団暴行罪に問われる可能性があります。【ケース2】複数人での喧嘩
飲み会の帰りに、自分のグループ数人と相手のグループ数人が口論となり、双方が暴行に及んだ場合。喧嘩両成敗とはならず、双方に集団暴行罪が成立する可能性があります。【ケース3】見張り役や煽り役
友人数人が暴行を加えている間、自分は直接手を出さずに見張りをしていたり、「やっちまえ」と煽っていたりした場合。共謀共同正犯として集団暴行罪に問われる可能性があります。
集団暴行罪の成立要件は?
集団暴行罪は、刑法の暴行罪とは異なり、「数人が団体または多衆の威力を示して共同で暴行すること」によって成立します。単なる複数犯ではなく、集団としての威圧や組織的行動が伴う点が特徴です。構成要件を理解することは、どのような場合にこの罪に問われるのかを判断する上で非常に重要です。ここでは、成立に必要な4つの要件を整理して解説します。
- ① 暴行の実行行為があったこと
- ② 数人が共同して暴行を行ったこと
- ③ 集団としての威力を示していたこと
- ④ 他の者と共同で暴行しているという認識があったこと
①暴行したこと
集団暴行罪が成立するための第一の要件は、暴行の実行行為があったことです。ここでの「暴行」とは、刑法上の暴行罪における定義と同じく、「人の身体に向けられた不法な有形力の行使」を指します。有形力の行使とは、身体への直接的な接触に限りません。例えば、殴る、蹴るといった行為が典型ですが、他にも、物を投げつける、刃物を振り回して相手を威嚇する、大声で耳元に怒鳴りつける、あるいは身体を掴んで引っ張るなど、人の身体に対して何らかの物理的な影響を与える行為全てが含まれます。傷害(怪我)を負わせるに至らなかったとしても、他人の身体に向けられた有形力の行使があれば、暴行罪、そして集団暴行罪の構成要件を満たします。
②集団で行うこと
集団暴行罪の成立には、「数人共同して」暴行を行うことが必要です。
この「数人」とは2人以上を指します。ただし、単に2人以上で暴行するだけでは足りず、「団体若しくは多衆の威力を示して」かつ「数人共同して」暴行を行うことが構成要件とされています。
しかし、集団暴行罪に該当しない場合でも、実際に暴行を行った者は刑法上の暴行罪に問われることになります。さらに、暴行に加わらなかった他のメンバーであっても、暴行を実行した者と事前に意思の連絡(共謀)があり、その計画に基づいた役割を果たしていたと認められれば、共謀共同正犯として、暴行を加えた者と同等の暴行罪の責任を問われる可能性があります。
③集団の威力を示すこと
集団暴行罪の適用には、単に複数人で暴行するだけでなく、その集団の威力を被害者や周囲に示す行為等が伴っていることが必要です。
これは、集団で暴行することによって、単独犯よりも被害者に強い恐怖や威圧感を与えるという、本罪の違法性を裏付ける要素となります。具体的には、被害者を複数人で取り囲む行為や、集団の力を背景とした威圧的な発言をする、さらには特定の組織名を名乗ることで威嚇する、といった行為が集団の威力を示すものとして評価されます。
集団暴行罪は、このように集団であることを背景にした威圧を伴うことで、通常の暴行罪よりも重く処罰される特別な類型として位置づけられています。
④他の者と共同して暴行を行うことの認識
集団暴行罪を成立させるためには、暴行を実行した各人が、「他の者と共同して暴行を行っている」という認識を持っていることが必要です。これは、犯行グループの間で、共同して暴行を実行しようという意思の連絡(共謀)があったことを意味します。
事前に綿密な計画を立てていなくても、その場で「一緒にあいつに暴行を加えてやろう」という暗黙の了解や共通の意思が形成されていれば、この要件を満たします。
この認識は、暴行に加わった者たちが、自らの行為が単独ではなく集団的な暴行の一部であると認識し、その結果について共同で責任を負う意思があったことを示すための重要な要件となります。
集団暴行罪についてのよくある質問
集団暴行罪は、関与の仕方や人数構成、被害の程度などによって判断が大きく変わるため、「どのような場合に罪に問われるのか」「どの程度の刑罰になるのか」といった疑問を持つ方が少なくありません。ここでは、特に相談の多い4つのポイントを取り上げ、実務上の判断基準をわかりやすく解説します。
暴行を加えなかった人は罪に問われない?
集団暴行罪の成立要件は「威力を示して数人共同して暴行を行うこと」ですが、実際に被害者の身体に手を下したのが一部の人間だけであっても、同罪または暴行罪の共同正犯に問われる可能性は極めて高いです。
たとえば、複数人で被害者を取り囲む中で、暴行を加えたのが2名で、他のメンバーがただその場に立って見ていただけのケースを考えます。暴行を行っていない者も、心理的または物理的に暴行実行者を支援したと評価される場合があります。その場にいることで集団の威力を示し、精神的に支援し、犯行を容易にしたと評価されます。
刑法における共謀共同正犯の理論により、「一部実行、全部責任」の原則が適用され、暴行実行犯と同じ集団暴行罪の刑事責任を負うことになります。物理的に暴行していなくても、共謀関係にあったり、見張り役や煽り役などの役割を担っていたりすれば、「無関係だ」と言い逃れをするのは難しいでしょう。
暴行の程度が人によって異なる場合も量刑は同じ?
暴行の程度は個別の行為者の量刑に影響を与えます。
暴行の程度や関与の度合いが異なっても、成立する罪名は原則として集団暴行罪の共同正犯として同じですが、裁判所が最終的に決定する量刑(刑の重さ)は、被告人ごとに異なります。
裁判所は、それぞれの被告人の刑事責任を個別に判断するため、以下の要素などを総合的に考慮します。
- 犯行における主導的な役割を果たしたかどうか
- 暴行に加わった回数や程度
- 犯行の動機
- 反省の意思の有無
- 被害者との示談状況 など
例えば、グループのリーダーとして暴行を主導したり、執拗に暴行を繰り返したりした者は、他のメンバーよりも重い量刑が科される傾向にあります。自身の関与が軽微であることを立証し、量刑を軽減するためには、弁護士による適切な防御活動が不可欠です。
慰謝料や示談金はどうやって分担する?
集団暴行事件では、慰謝料や示談金を共犯者全員で分担して支払うことが一般的です。
ただし、負担割合はケースによって異なります。全員が均等に分担する場合もあれば、主犯格や暴行の程度が重い者が多く負担する場合もあります。また、一部のメンバーが先に全額を立て替えて、後で他のメンバーに請求するケースも少なくありません。
示談金の相場は、被害の程度や被害者の処罰感情によって大きく変わります。暴行のみで怪我がない場合は数万円〜数十万円、傷害の場合は数十万円〜数百万円となることが一般的です。
適正な金額や各メンバーの負担割合、支払い方法については、弁護士に相談することで、トラブルを避けながら円滑に交渉を進めることができます。
集団暴行の結果、被害者に死傷の結果が生じた場合の罪は?
集団での暴行の結果、被害者が怪我(傷害)を負ってしまった場合、集団暴行罪ではなく、より重い傷害罪(刑法204条)が適用されます。傷害罪の法定刑は「15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。
また、暴行の意思しかなかったにもかかわらず、その結果として被害者が死亡してしまった場合は傷害致死罪(刑法205条)が成立し、法定刑は「3年以上の拘禁刑」とさらに重くなります。
集団暴行事件において、傷害や死亡の結果について、その場にいた暴行関与者全員が予見可能だったと判断される場合、たとえ直接手を下していなくても、傷害罪または傷害致死罪の共同正犯として、極めて重い刑事責任を負うことになります。結果の重大性に応じて、刑罰も格段に重くなるため、迅速な対応が求められます。
集団暴行罪の判例
集団暴行罪の適用範囲や罪数処理、罰条の適用方法は判例によって具体化されています。以下では、①暴行罪での起訴にもかかわらず暴処法1条(集団暴行罪)の適用を認めた最高裁決定と、②被害者ごとに集団暴行罪が独立して成立するとした高裁判決を取り上げ、実務上の示唆(罪数評価、罰条変更の可否、量刑判断への影響)を整理します。
①暴行罪で起訴されたが集団暴行罪が認定された事例
この判例は、被告人が共謀者らと共同して4名に暴行を加え、うち3名に傷害を負わせたという事案についてのものです。
検察は傷害罪と暴行罪で起訴しましたが、第一審は傷害罪のみを適用しました。これに対し、控訴審は、怪我を負わなかった1名に対する暴行行為について、単なる暴行罪ではなく暴力行為等処罰に関する法律(暴処法)第1条、すなわち集団暴行罪を適用すべきであったとして、第一審判決を破棄しました。
最高裁判所は、控訴審の判断を支持し、以下2つの重要な判断を示しました。
まず、罪数に関して、数人共同して複数人に暴行を加え、一部に傷害が生じた場合、怪我を負った者の数だけの傷害罪と、暴行に留まった者の数だけの暴処法第1条の罪(集団暴行罪)が成立し、これらは併合罪として処断されるべきであるとしました。これは、単独犯の暴行罪(刑法208条)ではなく、集団犯の重い罪である暴処法第1条を適用することで、集団的暴行の凶悪性を正当に評価したものです。
また、罰条の適用に関して、裁判所は、訴因(公訴事実)が十分に明確であり、被告人の防御に実質的な不利益が生じない限りは、罰条変更の手続を経る必要なく、起訴状に記載されていない罰条(本件では刑法208条から暴処法1条)を適用できるという新たな見解が示されました。これにより、刑事手続における訴因の明確性と被告人の防御権の保障が確保されている限り、柔軟な法令適用が可能であることが示されました(最高裁判所昭和53年2月16日決定)。
②集団暴行罪は被害者毎に成立するとされた裁判例
この裁判例は、複数の被告人が共謀し、同一場所・同一機会に、複数の教員(被害者)に対して暴行を加え、傷害を負わせたという事案を巡るものです。
被告人は集団暴行罪で起訴されましたが、被告人側は、後に起訴された事実は先行の起訴事実と「唯被害者を異にしているに過ぎず、一個同一の事件」であるとして、後の起訴について公訴棄却(裁判を打ち切る)の判決をすべきであったと主張しました。
しかし、裁判所は、被告人側の主張を明確に退け、以下の原則を示して控訴を棄却しました。
- 人の身体は、包括して一個の法益と観察すべきではなく、各個独立の法益であること
- 集団暴行罪は、たとえ「同一被告人により同一場所で同一機会に多数の被害者に対して実行され、かつ行為の態様を同じくする場合」であっても、被害者ごとにその成立を認めるべきであること
したがって、本件のように一連の集団暴行行為で複数の被害者がいた場合、その被害者の数だけ集団暴行罪が成立し、これらは併合罪の関係に立つと判断されました。
この判決は、個々の被害者の身体の安全という法益が独立している以上、その法益侵害の回数だけ罪が成立するという、刑法の大原則を特別法である暴処法にも適用したという点で重要です(高松高等裁判所昭和39年4月30日判決)。
集団暴行事件を起こしてしまった場合の対応
集団暴行事件を起こしてしまった場合、被害者への謝罪や示談交渉の有無、弁護士への相談のタイミングによって、今後の刑事処分が大きく変わります。事件後の対応を誤ると、関与の程度にかかわらず重い処罰を受けるおそれがあります。ここでは、取るべき初動対応を2つのポイントに分けて解説します。
- ① 一人でもいいので被害者との示談交渉を進める
- ② 弁護士に早期に相談し、適切な弁護方針を立てる
①一人でもいいので示談交渉をする
集団暴行事件を起こしてしまった場合、刑事処分を左右する要素が被害者との示談成立です。
示談が成立すれば、被害届の取り下げや処罰感情の緩和につながり、不起訴処分の可能性が高まるほか、起訴された場合でも減刑や執行猶予を得る上で極めて有利な情状となります。
集団暴行事件では、複数の共犯者全員で示談金の負担割合(等分、主犯格が多く負担など)について話し合う必要がありますが、加害者同士で意見が対立し、足並みが揃わないことも少なくありません。しかし、示談はあくまで当事者間の和解契約であるため、他の共犯者の意思に関わらず、自分一人だけでも示談交渉を進めることが可能です。
共犯者が全員で示談できなくても、自分だけでも示談を成立させることで、その法的効力は自身に及び、自身の刑事処分を軽くするという大きなメリットを享受できます。状況が複雑化する前に、弁護士を通じて単独での示談成立を目指すことが重要です。
②弁護士に相談する
集団暴行事件に関与した場合、「自分は少ししか手を出していない」と思っていても、集団暴行罪や暴行・傷害罪の共同正犯により、主犯格と同じ重い責任を負うリスクがあります。
そのため、速やかに弁護士に相談・依頼することが不可欠です。
弁護士は、まずあなたから詳細な事情を聞き取り、あなたが負うべき責任の範囲を法的に明確化します。「そもそも暴行を行うという共謀関係がなかった」ことや、「共謀があったとしても、結果として生じた重い傷害結果にまで共謀はなかった」として、共同正犯の成立や責任範囲を争います。
また、犯行途中にその場を離れた等の事実がある場合は、共謀からの離脱にあたることを主張し、離脱後の行為に対する責任を免れるよう尽力します。加えて、弁護士は示談交渉の専門家として、被害者の感情に配慮しつつ、適正な示談金額での交渉を円滑に進め、最終的にはあなたの関与の度合いに応じた有利な情状弁護を行うことで、刑事処分を最小限に抑えるよう全力を尽くします。
集団暴行罪に問われた方・ご家族の方は、早めに弁護士へご相談を
集団暴行事件では、「自分は暴行していない」「少し関わっただけ」と思っていても、共謀関係が認められれば主犯格と同じ刑事責任を負う可能性があります。
事件後の供述内容や被害者との示談状況によって、処分が大きく変わるケースも少なくありません。
弁護士法人若井綜合法律事務所では、刑事事件に精通した弁護士が一人ひとりの状況を丁寧にお聞きし、最も有利な解決を目指してサポートします。
被害者との示談交渉、勾留の回避、起訴前の不起訴処分獲得など、状況に応じた対応を迅速に行います。
ご家族が逮捕された場合も、早期の接見・助言により、事態の悪化を防ぐことが可能です。
弁護士に相談することで、今後の見通しや取るべき行動が明確になり、不安を軽減できます。
全国どこからでも無料相談を受け付けています。
突然の逮捕や取調べで不安を感じている方は、一人で悩まずにできるだけ早くご相談ください。
早期の対応が、あなたやご家族を守るための確かな一歩となります。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|