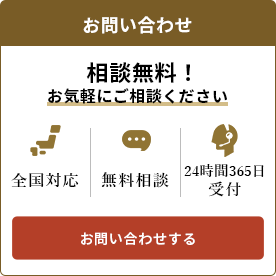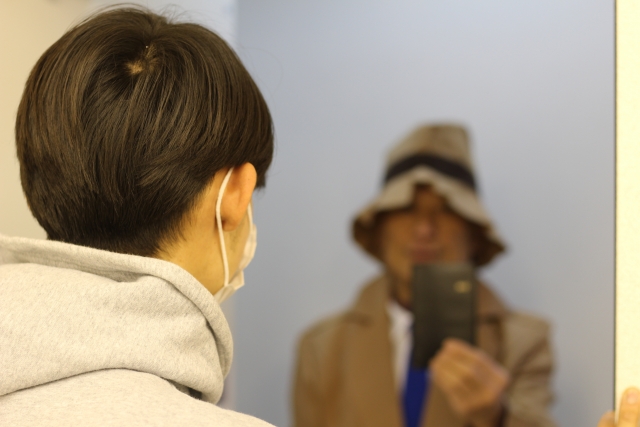
犯罪に手を染めてしまい、テレビドラマのワンシーンのように、警察が突然自宅に逮捕状を持って訪問してくるのではと不安な毎日を過ごしている方もいることでしょう。
脅かすわけではないですが、まさに”その時”が刻一刻と迫ってきているかもしれません。
不安に駆られたアナタは、「逮捕状を突き付けられるのが怖い。なんとか回避できないか」そう考えているのではないでしょうか。
そこでここでは、刑事事件に強い弁護士が、以下の2点を含む、逮捕状について知っておくべき情報をわかりやすく解説していきます。
- ①逮捕状の請求が却下されたり取り下げられることはあるのか
- ②逮捕状が発布されていることを知ることはできるのか
法律に詳しくなくてもわかるように書かれていますし、4分ほどで読み終えますので、ぜひご一読ください。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
目次
逮捕状について
逮捕状とは
逮捕状とは、通常逮捕の場合は逮捕の際、緊急逮捕の場合は逮捕した後速やかに必要とされる令状のことをいいます。
逮捕は人の意思に反してその自由を奪う「人権を制約する行為」でることから、刑事手続きについては特に適正な手続きを保障するよう憲法31条で要請されています。
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
そして、適正な手続きを保障するために「令状主義(捜査機関が逮捕などの強制処分をするには、裁判官の発布する令状を必要とする原則)」が採用されており、逮捕の際に必要とされる令状が「逮捕状」となります。
逮捕状は誰が出すの?
逮捕状は捜査機関(警察、検察官)が裁判官に「逮捕状を発布してください」と請求(逮捕状請求書等を提出)し、裁判官が逮捕状発布の要件を満たすと判断した場合にはじめて裁判官の名で発布されます。
逮捕は人の自由を制限する強制処分ですから、捜査機関の裁量で自由に行えるとなるとその権限が濫用され、ときに誤認逮捕などの違法逮捕に繋がる危険があります。
そこで、こうした危険の歯止めとするため、人を逮捕するには逮捕状が必要とされ、さらに逮捕状の発布には裁判官による司法審査が必要とされているのです。
逮捕状は誰が請求できるの?
裁判官に逮捕状を請求できる人は⑴通常逮捕の場合と⑵緊急逮捕の場合とで若干異なります。
⑴通常逮捕の場合
請求できる人は検察官、司法警察員です。
司法警察員とは警察官のうち巡査部長以上の階級にある警察官をいいます。そして、逮捕状を請求できる人は司法警察員の中でも、公安委員会が指定する警部以上の人に限ります。
⑵緊急逮捕の場合
通常逮捕と異なり、請求できる人は検察官、司法警察員のほか、検察事務官、司法巡査(階級が巡査の警察官)も可能です。
なお、一般の刑事事件や警察が独自で捜査を行う事件については警察官、検察が独自で行う事件(大規模経済、汚職事件など)については検察官が請求するのが実情のようです。
逮捕状の見本
逮捕状には主に以下の事項が記載されています。
- 被疑者に関する事項(氏名・年齢・住所・職業)
- 被疑事実に関する事項(罪名、被疑事実の要旨)
- 裁判官の許可に関する事項(許可年月日、裁判所、裁判官名・押印)
- その他(被疑者を引致すべき場所、逮捕状の有効期限、逮捕後の手続きに関する日時)
なお、テレビでよくご覧になるのが、逮捕(逮捕状執行)の際、被疑者が捜査員から「被疑事実の要旨」を告げられる場面です。これは法律上要求される逮捕前の逮捕状呈示の一環として行われているものです。
以下は逮捕状の見本です。
| 逮 捕 状(通常逮捕) | |||||||||
| 被疑者 | 氏名 | 鈴木 太郎 | |||||||
| 年齢 | 36歳 | ||||||||
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋 田中アパート205号室 | ||||||||
| 職業 | 無職 | ||||||||
| 罪名 | 窃盗 | ||||||||
| 被疑事実の要旨 | 別紙逮捕状請求書記載のとおり | ||||||||
| 引致すべき場所 | 警視庁神田警察署または逮捕地を管轄する警察署 | ||||||||
| 有効期間 | 令和5年1月23日まで | ||||||||
| 有効期間経過後は、この令状により逮捕に着手することができない。この場合には、これを当裁判所に返還しなければならない。 有効期間内であっても、逮捕の必要がなくなったときは、直ちにこれを当裁判所に返還しなければならない。 |
|||||||||
| 上記の被疑事実により、被疑者を逮捕することを許可する。 令和5年1月16日 東京簡易裁判所 裁判官 甲野 一郎 |
|||||||||
| 請求者の官公職氏名 | 神田警察署 司法警察員警部 田中 敏夫 | ||||||||
| 逮捕者の官公職氏名 | 神田警察署 司法警察員警部補 山田 孝利 | ||||||||
| 逮捕の年月日時 及 び 場 所 |
令和5年1月17日午後4時17分 東京都千代田区神田錦町3丁目3番2号神田警察署で逮捕 |
||||||||
| 引致の年月日時 | 令和5年1月17日午後4時18分 | ||||||||
| 記 名 押 印 | 警視庁神田警察署 司法警察員警部補 天野 和幸 ㊞ | ||||||||
| 送致する手続をした 年 月 日 時 |
令和5年1月18日午後0時54分 | ||||||||
| 記 名 押 印 | 警視庁神田警察署 司法警察員警部補 伊東 隆 ㊞ | ||||||||
| 送致を受けた年月日時 | 令和5年1月18日午後1時43分 | ||||||||
| 記 名 押 印 | 東京地方裁判所 検察事務官 井上 誠也 ㊞ | ||||||||
逮捕状の有効期限は?
逮捕状には有効期限があります。
逮捕状の有効期間は、原則として逮捕状が発布された日の翌日から起算して7日です。
有効期間が経過した後はその逮捕状で逮捕を執行することができず、再度、請求→裁判官の許可という手続きを経て新たな逮捕状を取得する必要があります。
これは、期間の経過とともに逮捕の必要性が消滅することもありうることから、期間を設け、期間経過の都度、裁判官の司法審査を受けさせて違法逮捕を防止する趣旨です。
もっとも、裁判官が相当と認めるとき(逃亡を繰り返して捜査機関が逮捕できなかった場合など)は7日を超えた期間を設定されることもあります。
逮捕状はいつ、誰に、どうやって請求するの?
逮捕状は裁判官に請求します。
請求の際に逮捕状請求書と逮捕の理由(※)と逮捕の必要性(※)を裏付ける証拠(書面)を提出します。
また、裁判官が必要と認めるときは、捜査員が直接裁判官に事情を話したり、書類等を提示することもあります。
※逮捕の理由
通常逮捕=罪を犯したと疑うに足りる相当な理由
緊急逮捕=罪を犯したと疑うに足りる充分な理由
※逮捕の必要
罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ
逮捕状請求が却下されたり、請求そのものを取り下げることはあるの?
逮捕状発布の要件(逮捕の理由+逮捕の必要性)を満たさない場合は却下されます。もっとも、却下される数は極めて少ないです。
裁判所が公表している、令和元年度の司法統計によると、令和元年度に請求された逮捕状の数は8万5658本で、うち、許可された数は8万2884本(全体の約96.8%)、却下された数は88本(全体の約0.01%)ということでした。ちなみに、請求を取り下げることもできますが、取り下げた数は1227本(全体の約1.4%)だったということです。
却下率が低いのは、請求を受けた裁判官ですら捜査の内情に明るくないことから、逮捕段階では捜査機関の判断を尊重せざるを得ない上、請求手続きに弁護人が関与することもできないことなどが影響しているものと考えられます。
逮捕状が出ると逮捕状は必ず執行されるの?
逮捕状を呈示して逮捕することを逮捕状の執行といいます。
通常逮捕の場合、逮捕状は必ず執行されるわけではありません(緊急逮捕の場合は必ず執行しなければなりません)。
そもそも逮捕状が発布されたからといって、裁判官が捜査機関に逮捕することを命じたわけではありません(逮捕状は裁判官の許可状であって命令状ではありません)。
つまり、発布された逮捕状を執行するか否かは捜査機関の判断に委ねられているのです。
逮捕状は発布されたものの、捜査機関の判断で逮捕状を執行(逮捕)しない、ということはあり得ます。
逮捕状はどうやって執行するの?
法律上必要とされている手続は、逮捕前に被疑者に逮捕状を呈示すること、です。
被疑者に逮捕状に記載されたどの内容を、どの程度呈示するかは法律で決められていません。
したがって、具体的な逮捕状の呈示方法はケースバイケースで、現場の捜査員の判断に委ねられます(通常は、捜査員から逮捕状が発布されていることと被疑事実の要旨を告げられます)。
また、逮捕状は逮捕前に呈示することが原則ですが、やむを得ない場合は、一定の条件の下逮捕後の呈示であっても違法とはいえないとした裁判例があります(東京高裁昭和60年3月19日)。
逮捕状の緊急執行とは?
緊急執行とは、逮捕状は発布されているものの、たまたま捜査員が逮捕状を所持していないばかりに直ちに逮捕状を執行することができない場合において、被疑者に対し、逮捕状が発布されていること及び被疑事実の要旨を告げた上で、逮捕状なしに逮捕することをいいます。
指名手配されている逃亡中の被疑者を捜査員が偶然発見した、などという場合に取られる手法です。
逮捕状は発布されていますから、逮捕後に逮捕状が呈示されます。
なお、緊急執行と緊急逮捕とを混合しがちですが、両者は意味が全く異なります。
つまり、緊急逮捕は逮捕状を所持していないものの、一定の条件を満たした場合に逮捕状なく逮捕できるというものです。
逮捕後、すみゃかに捜査機関が裁判官に逮捕状発布の請求をして逮捕状を得た後、逮捕した被疑者に呈示します。
逮捕状が出ているか知ることはできるの?
残念ながら知ることができません。
つまり、捜査機関から「逮捕状が発布されました」などという連絡が来ることは絶対にありえませんし、問い合わせても絶対に答えてくれません。
そもそも、捜査機関は被疑者に逮捕の必要性がある、つまり罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれを防止する必要があると判断したからこそ逮捕状の請求をしているはずです。
その捜査機関がわざわざ被疑者に罪証隠滅、逃亡のおそれを作り出すきっかけを与えるはずはないからです。
もっとも、刑事事件の経験のある弁護士であれば、逮捕状を請求されるか、発布されるか、執行されるかについて、ある程度予測することができます。逮捕に不安のある方は、はやめに弁護士に相談しましょう。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|