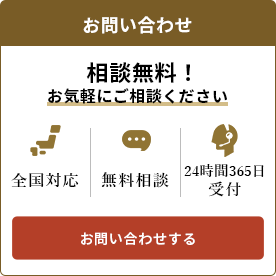正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自分又は他人の権利を守るため、やむを得ずに行った防衛行為のことです。
刑法第36条1項では、反撃行為が正当防衛にあたる場合は、たとえその行為が形式的には違法であっても実質的にみれば違法ではなく、犯罪は成立しないため、反撃行為をした者を処罰しないと規定しています。急迫不正な侵害に対して反射的に自分又は他人の権利を守る行為は、人の本能に基づく行為であって、法律で違法として制限されるべきいわれはないためです。
もっとも、防衛の程度を超えた場合、すなわち「やむを得ずに行った防衛行為」と言えない場合には「過剰防衛」として罪に問われることもあります。また、正当防衛の成立要件は厳格であるため、自分では正当防衛だと考えてとった防衛行為が正当防衛として認められず、暴行や傷害、殺人などの罪で刑事責任に問われる可能性もあります。
そうなると、「どこからどこまでの行為が正当防衛になるのだろう」と思われる方も多いでしょう。
そこでこの記事では、刑事事件に強い弁護士が、
- 正当防衛の成立要件
- 正当防衛の成否が争われた判例
- 正当防衛と過剰防衛の違い
などについてわかりやすく解説していきます。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
正当防衛の成立要件
正当防衛は、刑法第36条1項を根拠条文とします。
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
そして、正当防衛の成立要件は次のとおりです。
- ①急迫不正の侵害があること
- ②自己又は他人の権利を守るために防衛行為に出たこと
- ③防衛の意思があること
- ④防衛行為の必要性・相当性があること
以下、それぞれの要件につき詳しく解説していきます。
①急迫不正の侵害があること
急迫とは、自分の目の前で球が入ったピストルを向けられているなど、今まさに守られるべき法益(このケースの場合、命)が侵害されようとしているか、あるいは、その状況が目前に差し迫っていることをいいます。
したがって、過去に相手から暴力を振るわれたため仕返しにと暴力を振るうような過去の侵害に対する防衛行為や、相手から殺害予告を受けていたため、先手を打って相手を殺害するような将来の侵害に対する防衛行為(先制攻撃)は正当防衛にはあたりません。
次に、不正とは、違法と同じ意味です。したがって、相手の正当防衛に対する防衛行為は正当防衛にはあたりません。違法性は客観的に違法であればよく、相手に責任能力が備わっているかや故意・過失があるかどうかは問わずに正当防衛が成立する可能性があります。
次に、侵害とは、法益に対する実害又はその危険を生じさせる行為をいいます。目の前で球が入ったピストルを向けられるのは、死という実害の危険を生じさせる行為であることからまさに侵害にあたります。
侵害は故意によるもの過失によるもの、作為(何かすること)によるもの不作為(何もしないこと)によるものとを問いません。したがって、敷地に立ち入った不審者が敷地から立ち退かない(不作為による侵害を受けた)ことから、実力で敷地外に引きずり出した際に不審者に怪我を負わせたとしても正当防衛が成立し、傷害罪は成立しない可能性があります。
②自己又は他人の権利を防衛するために防衛行為に出たこと
防衛行為は自己又は他人の権利を防衛するために行わなければいけません。
権利とは法益、つまり、守られるべき利益のことです。前述のとおり、殺人の場面では命(生命)が法益にあたります。
防衛行為は侵害から法益を守る行為です。目の前で球の入ったピストルを向けられたため、ピストルを振り落とそうと近くに落ちていた棒で相手の手や腕を叩く行為は防衛行為にあたります。
このように防衛行為は侵害者に対して向けられたものでなければなりません。そのため、たとえば、刃物で切りつけられそうになったため、その場から逃げようと無関係な第三者を押し倒して怪我を負わせた場合のように、まったく無関係の第三者に向けられ行為は防衛行為にはあたらず正当防衛は成立しません(後述する、「緊急避難」が成立する余地はあります)。
③防衛の意思があること
上記の通り、防衛行為は自己又は他人の権利を防衛するために行わなければいけません。そこで、正当防衛が成立するには防衛の意思が必要か否かが問題となります。
この点、判例(最判昭和46年11月16日など)は防衛の意思を必要としています。
防衛の意思を不要とした場合、たとえば、甲が乙を殺す意図で乙に向かってピストルを発砲したところ、その際乙も甲を殺す意図でピストルを甲に向けていたが、一瞬早く甲の球が乙にあたったため、甲が自己の命を防衛したというような偶然防衛の場合に、甲に正当防衛の成立を認めることになってしまいます。やはり、本来なら違法なはずの行為を合法とするには、それを正当化するだけの心理的な契機が必要と考えられているのです。
④防衛行為の必要性・相当性があること
やむを得ずに出た行為とは、具体的状況下において、その防衛行為が侵害を排除し、又は法益を防衛するために必要かつ相当なものであったことをいいます。これを防衛行為の必要性・相当性ともいいます。
防衛行為の必要性があったといえるためには、防衛行為を行う前に、逃げることや警察に通報するなどの他の適切な手段が存在したかどうかが重要です。もし他の選択肢があり、それが効果的に自己や他人を守ることができた場合、防衛行為の必要性は否定される可能性があります。
防衛行為の相当性があったといえるためには、防衛行為が、防衛のために必要最小限限度の行為であると客観的に認められる必要があります。たとえば、相手の手足を粘着テープで固定して動けなくしたにも拘わらず、殴る蹴るの暴行を加える行為は、必要最小限度の行為とは認められないでしょう。万引き犯(財産への侵害)に対して暴力を振るって大怪我をさせたようなケースも、必要最小限度の防衛行為とは認められない可能性があるでしょう。
もっとも、このような必要最小限度については、結果としての相当性ではなく、「行為としての相当性」が問題となります。この「行為としての相当性」については、侵害現場で選択することができた防衛手段のうち、確実に防衛効果が期待できる手段であって侵害性が最も軽微な手段が、必要最小限であるといえるでしょう。
したがって正当防衛の結果、偶然他人の死亡や傷害結果が生じたからと言って当然に相当性が否定されるわけではないのです。
相当性を判断する際には、以下のような事情を考慮して必要最小限か否かを検討することになります。
- 武器対等の原則(素手か武器使用か)
- 身体的な条件(年齢、性別、力の差など)
- 侵害行為の態様
- 防衛行為の態様
- 代替手段の有無 など
正当防衛についての注意点
正当防衛を認めてもらうのは難しい
正当防衛が認められるハードルは決して低くはありません。本人が正当防衛であると主張したからといって必ずしも主張が認められるというものではありません。
正当防衛となるかどうかという判断は非常に相対的であり、「この場合には絶対に正当防衛になる」と言うことはできません。
正当防衛を主張する場合であっても、相手が死亡・負傷するような重大な事案の場合には、逮捕・勾留される可能性が高いと言えます。不起訴処分とならず、刑事裁判に移行する可能性も十分にあります。
捜査機関が正当防衛を認めない場合には、裁判で正当防衛の成立を主張していくことになりますが、立証のハードルは決して低くはありません。
安易に正当防衛を主張すると不利になることも
正当防衛の成立には要件があり、事実関係から正当性が否定されるケースも多数あります。
事件で逮捕された人が安易に正当防衛を主張すると不利になる可能性もあります。
捜査機関に「事件を反省していない」「責任を逃れようとしている」などと受け取られ、余計に重い処分になってしまうリスクも想定できます。
そのため、正当防衛状況下にあったという場合には、必ず弁護士に相談して、事件当時の詳しい説明を伝えるようにしてください。弁護士に相談することで、正当防衛の成否を判断したうえで、適切な弁護活動を行ってもらうことが期待できます。
正当防衛の成立が争われた判例
ここで、正当防衛の成立が争われた判例をご紹介します。
正当防衛が成立して傷害罪が無罪となった判例
この事案は、被告人が被害者Aに対して背後からハンマーで頭部を数回殴打して全治2週間の傷害を負わせた事案です。
検察官は被告人の行為は傷害罪にあたるとして懲役1年6月を求刑しました。
しかし、裁判所はこの事件について、「被告人に対する急迫不正の侵害の存在は認められ,被告人がAの頭部を本件ハンマーで殴打したのはそれに対する防衛行為であったというべきである(なお,防衛の意思を否定する事情はなく,これも認められる。)」と判示し、被告人に無罪を言い渡しました(札幌地方裁判所平成30年12月3日判決)。
- 被告人が殴打する前に、Aが被告人の襟首を掴み腕や腹、胸を殴り、太ももや股間等に膝蹴りをする暴行を加えていたこと
- Aが手を離すと被告人はその場にうずくまったこと
- 被告人に対して「今日はもう許さん」「ぼこぼこにする」と言ったこと
上記のような点から、裁判所は、被告人に対する急迫不正の侵害が続いていることを認定しています。
正当防衛が成立して傷害致死罪が無罪となった判例
この事例は、被告人が波止場において被害者B(当時56歳)に対して顔面を手拳で殴打する暴行などをくわえて転倒させその左後頭部を地面に打ち付けさせ、左後頭部打撲等の傷害を負わせて外傷性脳障害によりBが死亡してしまった傷害致死事件です。
この事例については、裁判所は、「被害者の本件攻撃は突然かつ執拗で、強いものであった可能性があり、これに対する被告人の本件対抗行為がそれほど強度なものではなかった可能性も排斥できず、・・・被告人が、年齢、体格及び経歴等の点で被害者よりも一方的に有利な状況であったと認めるに足る事情もなく、被告人の攻撃は1回にとどまり、凶器等を用いることなく素手で本件対抗行為に及んでいることも考慮すれば、被告人の本件対抗行為が本件攻撃に対する防衛行為として許された程度を超えていたと評価することはできない」と判示して、正当防衛が成立するとの合理的な疑いが残るため無罪の判決が言い渡されています(長崎地方裁判所令和3年7月8日判決)。
以上のように正当防衛が成立するという合理的な疑いが残るような場合には、「疑わしきは被告人の利益」という刑事裁判の大原則によって、無罪判決が言い渡されることになるのです。
正当防衛が成立して殺人罪が無罪となった判例
この事案は、手に嚙みついた被害者Aを失神させようと「バックチョーク」をかけたところ、相手が死亡したという事案です。
バックチョークとは、ブラジリアン柔術の絞め技で、相手の気道を塞がず、肘を支点として腕を相手の頸部に巻き付け、頸動脈を閉塞して相手を気絶させる技のことです。
検察官は、被告人が被害者を頸部圧迫により死亡させたとして殺人罪で起訴しました。
この事件で裁判所は、以下のとおり被告人の正当防衛を認定しました。
「バックチョークは,ブラジリアン柔術の技の中でも最も基本的で,相手を傷付けない安全な技であるとされており,バックチョークそれ自体は,相手を死亡させる危険性の高い行為とまではいえない。・・・Aによって自分の右手を噛まれているという急迫不正の侵害に対し,自己の身体を防衛するため,やむを得ず実行に及んだものと認められる。また,被告人が,Aの口から右手が抜けた後,更に左腕でAの頸部を絞め付けたことも,Aに,なおも暴れるような素振りがあったことや,絞め付けた時間が5秒程度という極めて短い時間であったことなどからすると,Aによる急迫不正の侵害に対し,その前の行為と時間的・場所的に極めて接着してなされた一連一体の行為であると評価するべきであり,全体として正当防衛が成立すると認められる(被告人とAとの関係を考慮すると,一度Aの異常な行動がやんだ後に,被告人がAに積極的に加害の意思をもって暴力を振るうとも考え難い。)」(大阪高等裁判所平成30年10月31日判決)。
被告人には無罪の判決が言い渡されています。
侵害の急迫性を欠くとして正当防衛の成立が否定された判例
以下の判例は、自招侵害と正当防衛に関する判例です。自招侵害とは、正当防衛に名を借りて相手に侵害を加えたり、故意または過失により相手を挑発するなどして、防衛者が自ら不正の侵害を招いて正当防衛の状況を作り出すことをいいます。
この事例は、政治集団A派の被告人が、B派の来襲を受けてこれを撃退した後、再度の襲撃を予期して鉄パイプ類を準備し、現実に起こった第二次襲撃の際、B派数名に共同して暴行した事件です。
判決は、B派の襲撃がほとんど確実に予期されたとしても、正当防衛の「侵害の急迫性」の要件を欠くものではない、としながらも、単に予期された侵害を避けなかったというにとどまらず、その機会を利用し積極的に相手に対して加害行為をする意思で侵害に臨んだときは、もはや侵害の急迫性の要件は満たさないとし、正当防衛の成立を認めませんでした(最高裁昭和52年7月21日判決)。
正当防衛の成立が否定されて殺人罪で処罰された事例
この事案は、同じマンションの入居者である被害者Aの足音やテレビの音が大きいという近隣トラブルから殺人事件に発展した事案です。
Aと口論になった末、被告人がAの腹部や胸部をペティナイフで数回突き刺したことで、Aが刺創による大動脈損傷が原因で失血死しました。
Aは、被告人が先行して本件ナイフを持って飛び掛かってきたことから、自分の身を守るために被告人を押さえつける行動をとりました。
裁判所は、「本件ナイフをAの左側胸部に向けて突き刺した行為も防衛行為として正当化することはできない」と判断しています。
また、「先行する事情に誤認はない状況で、怒りの感情に任せ、一方的に凶器を用いた攻撃行為に及んだとみることができるのであって、正当防衛が認められるような状況にあったと「誤想」していたとは認められず、誤想過剰防衛も成立しない」としています(大阪地方裁判所令和5年7月19日判決)。
被告人には殺人罪が適用され、懲役15年が言い渡されています。
正当防衛の成立が否定されて殺人未遂罪で処罰された事例
この事案は、被告人が殺意をもって被害者をカッターナイフで切りつけたものの、左胸部挫創等の傷害を負わせたにとどまり、死亡させるに至らなかったという殺人未遂の事案です。
「近付いてくる被害者の動き等を全く見ていなかったというのであればともかく,実際には被害者が近付いてくる様子を見て分かっていたはずであるから,こうした状況でカッターナイフで切りつける行為の危険性を当然認識していたといえる。被告人が殺意をもって切りつけ行為に及んだことは明らかである。転倒した被害者に追撃行為に出た事実からも,被告人が最初の切りつけ行為の時点から攻撃を加えようとしていた」と認定しています。
そのうえで、「被告人は,被害者と口論となった後,一旦は被害者らと逆方向に向かって離れたものの,自ら被害者らのいる方に再び戻り,これに気付いて向かって来た被害者に至近距離から切りつけて重傷を負わせ,追撃もしている。このようにして凶器を用いた被告人の加害行為が,常識的に見て刑法36条の趣旨に照らし許容される防衛行為とは到底認められず,正当防衛は成立しない」と判示しています(札幌地方裁判所平成29年3月16日判決)。
被告人は殺人未遂罪とされ、懲役6年が言い渡されています。
正当防衛と緊急避難・過剰防衛との違い
最後に正当防衛と緊急避難・過剰防衛との違いを解説します。
正当防衛と緊急避難の違い
緊急避難とは、現在の危難を避けるためにやむを得ずした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り処罰されない、という制度です(刑法第37条)。
(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
正当防衛との違いは、正当防衛が「違法な侵害」に対抗する手段として例外的に認められているのに対して、緊急避難は「適法な相手を侵害する」ことも害の均衡という制限の中で正当化されているという点です。したがって、緊急避難では差し迫った危難を回避するために、無関係な第三者の権利を侵害することも認められているのです。
例えば、暴漢に刃物で襲われそうになったので、逃げるために近くにいた第三者を突き飛ばして逃げたという場合、その第三者が転倒して負傷したとしても、自分が刺されて負傷することを回避できている(害の均衡が保たれている)ので緊急避難が成立することになります。
なお、刑法では、正当防衛でも緊急避難でも「やむを得ずにした」という言葉が使われていますが、両者ではその意味が異なることに注意が必要です。すなわち、正当防衛の場面では「不正」の侵害から自己又は他人の法益を守ることを前提としますから、緊急避難と比べて防衛行為の相当性の要件が認められるハードルは低いです。これに対して、緊急避難の場面では「正」の侵害から自己又は他人の法益を守ることを前提としますから、正当防衛に比べて防衛行為の相当性の要件が認められるハードルは高くなります。
緊急避難とは?正当防衛との違いは?3つの成立要件と判例を解説
正当防衛と過剰防衛との違い
過剰防衛とは、急迫不正の侵害から自己又は他人の権利を守るために防衛行為に出たものの、その防衛の程度を超えた防衛のことをいいます(刑法第36条2項)。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
防衛の程度を超えたとは、
- 「殺すぞ」などと言いながら、手を振り上げて襲いかかってくる相手の腹部を刃物を突き刺した場合
- 相手が殴りかかってきたため暴行を加えて反撃し、相手が殴るのを辞めたため、さらに暴行を加えた場合
- 路上痴漢に襲われたため、目潰しのために催涙スプレーを噴射し、犯人の動きが止まった後にさらに噴射し続けて失明させた場合
- トラブルとなった相手が胸倉を掴んできたため、相手に殴る蹴るの暴行を加えてボコボコにした場合
などのように、防衛行為がやむを得ずにしたとはいえないこと、すなわち防衛行為の相当性を逸脱していることをいいます。
正当防衛との違いは、正当防衛が「やむを得ずに防衛行為に出たこと」の要件を満たすため違法性が阻却されて犯罪の成立が否定されるのに対し、過剰防衛はその要件を満たさないことから行為自体は違法と評価され、犯罪が成立ます。
もっとも、正当防衛ではないにしにしても、正当防衛と同様の状況下で防衛行為に出た点では同じで、恐怖・狼狽・興奮・驚愕により行き過ぎた行為に出ることは無理からぬ面もあります。そこで、過剰防衛にあたる場合は、状況により、裁判官の裁量で刑の減軽又は免除の措置を受けることがあります。
よくある質問
殴られたので殴り返したら正当防衛になる?
殴られたため自分の身を守るために殴り返したのであれば正当防衛が成立する可能性はあります。
しかし、例えば、相手が殴ってきたのが単発で、その後継続して殴られる可能性が低い場合や、殴った相手が立ち去ろうしているところを積極的に殴り返す行為は、もはや「自己の権利を防衛するためやむを得ずした行為」とは言い難いでしょう。相手の攻撃に対し執拗に殴り続けるなどの反撃行為に出た場合も同様です。したがって、これらのケースでは正当防衛が否定される可能性があります。
また、殴られたのでカッとなって殴り返したようなケースでは「防衛の意思」が欠けるため正当防衛が否定される可能性があるでしょう。
また、相手を挑発して殴らせるなど、ことさら相手からの侵害に臨み・待ち受けて自分から実質的に「急迫不正の侵害」を招致した場合(自招侵害のケース)には、「急迫性」が欠けると判断される可能性があります。この場合には、そもそも正当防衛規定が適用されませんので、暴行罪や傷害罪が適用されることになります。
日本の正当防衛の基準はおかしい?厳しい?
ここで先に相手が攻撃してきたため反撃したのに、「過剰防衛として犯罪が成立するのはおかしい。日本の正当防衛の基準が厳しすぎるのではないか。」と感じておられる方も多いのではないでしょうか。
たしかに、日本の正当防衛の成立基準が厳しいことは、一部の人々から批判を浴びることもあります。個人の安全や財産を守るために、より広い範囲での防衛行為を望む声も存在します。
しかしそもそも正当防衛とは、緊急事態を理由として例外的に自力救済(実力行使)を認めるという制度です。
法治国家では「自力救済の禁止」が原則となっており、自らの法益を守ろうとする者は「公的機関(警察や裁判所)の保護」により救済されるべきであると考えられています。しかし、そのような保護を待っていたのでは目的を達成することができないような場合に限り「例外的な実力行使」を認めているのが正当防衛です。
そのような例外として正当防衛の要件を考える場合、急迫不正の侵害行為に対する反撃行為については、自己または他人の権利を防衛する手段として「必要最小限度のもの(相当性)」が要求されることになるのです。なぜなら、過剰な反撃や防衛行為が容認されると、個人の判断に基づいた私的な力行使が横行し、社会の安定や秩序が損なわれる可能性があるからです。
以上のことから、正当防衛の基準の厳格さは、法の支配を堅持し、個人の利益と公共の利益をバランスよく保護するために必要であると考えることができるでしょう。
まとめ
以上、この記事では、正当防衛の成立要件や過剰防衛になる場合などについて詳しく説明してきました。
本人が正当防衛であったと考えていても、刑事事件として立件されてしまうと、逮捕や起訴されてしまう可能性があります。やむを得ずに反撃したことを捜査機関に説明し、弁護士に相談したうえで弁護活動をお願いすべきでしょう。
当事務所には、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が在籍しております。親身かつ誠実に、弁護士が依頼者を全力で守りますので、正当防衛を主張したい方、逮捕の回避、不起訴の獲得を目指したい方は、当事務所の弁護士までご相談ください。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|