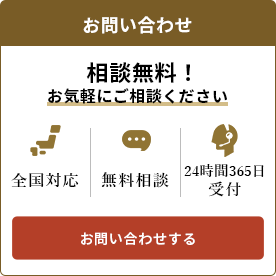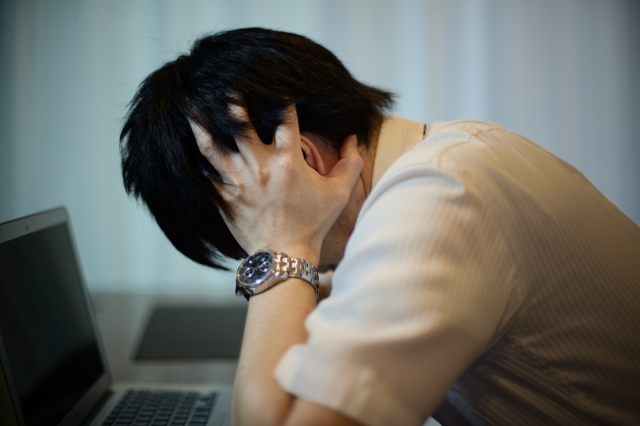
横領に関する罪には、横領罪(単純横領罪)・業務上横領罪・占有離脱物横領罪(遺失物横領罪)の3種類があります。
犯罪の時効(公訴時効)は、「犯罪行為が終了した時」から進行が開始されます。
横領罪(単純横領罪)の時効は5年、業務上横領罪の時効は7年、占有離脱物横領罪(遺失物横領罪)の時効は3年で、いずれも横領行為が終了した時点から起算されます。
この記事では、横領事件に強い弁護士が、
- 横領罪の公訴時効
- 横領罪の時効の起算点(いつから時効が進行するのか)
- 横領の民事(損害賠償)の時効
- 横領罪の時効完成を待つリスクと待たずにすべきこと
などについて詳しく解説していきます。
なお、横領事件を起こしてしまい、時効の完成まで逮捕を恐れて過ごすことが耐えられない方は、この記事をお読みいただき、全国無料相談の弁護士までご相談ください。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
目次
横領罪の公訴時効は何年?
公訴時効とは、犯罪行為を終えてから一定期間内に起訴(公訴提起)されないことによって、検察官がもつ起訴権限が消滅してしまう法制度のことです。犯罪が時効を迎えると(これを「時効の完成」といいます)、その事件について刑事罰を受ける可能性が消滅します。罪の時効期間は法定刑の重さにより異なります(刑事訴訟法第250条)。
横領に関連する3つの罪と、それぞれの時効期間は以下の通りです
- ①横領罪(単純横領罪):5年
- ②業務上横領罪:7年
- ③占有離脱物横領罪(遺失物横領罪):3年
以下で、それぞれについて詳しく解説します。
①横領罪(単純横領罪)は5年
横領罪の公訴時効は5年です。
横領罪は、自己の占有する他人の物を横領した場合に問われる罪で、刑法第252条に規定されています。この罪は「単純横領罪」とも呼ばれます。
例えば、友人から預かったお金を無断で使ったり、友達から借りているDVDを自分のものにしたり、知人から預かっている宝石を質屋に売却して得たお金を自分のものにしたりする場合が典型的な例です。
「占有」とは、委託信託関係に基づく占有である必要があります。これは、信頼関係に基づいて財物を委託されて占有している状態を指します。「他人の物」はお金だけでなく、物品も含まれます。「横領」とは、不法領得の意思を実現するすべての行為と解されています。不法領得の意思とは、他人の物の占有者が、所有者でなければできないような処分をする意思をいいます。例えば、売却、質入れ、費消、贈与、着服、抵当権の設定などの行為が該当します。
横領罪の法定刑は5年以下の懲役であり、「長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」に該当するため、公訴時効は5年となります(刑事訴訟法第250条第2項第5号)。
②業務上横領罪は7年
業務上横領罪の公訴時効は7年です。
業務上横領罪は、業務上で自己の占有する他人の物を横領した場合に問われる罪で、刑法第253条に規定されています。
例えば、新聞の集金業務を行っている者が集金したお金を自己の生活費に使った場合や、会社の会計担当者が法人口座から勝手にお金を引き出し、遊興費に使った場合が典型的な例です。
「業務」とは、人がその社会的地位に基づき反復継続して行う事務のことをいいます。
業務上横領罪の罰則は10年以下の懲役であり、「長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」に該当するため、公訴時効は7年となります(刑事訴訟法第250条第2項第4号)。
③占有離脱物横領罪(遺失物横領罪)は3年
占有離脱物横領罪(遺失物横領罪)の公訴時効は3年です。
占有離脱物横領罪は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した」場合に問われる罪で、刑法第254条に規定されています。別名、「遺失物横領罪」「拾得物横領罪」ともいいます。
「遺失物」とは、路上に落ちていた財布などのように、占有者(持ち主)の意思によらないで、その占有を離れ、まだ誰の占有にも属しない物をいいます。「漂流物」とは、占有者(持ち主)の意思によらないで、その占有を離れ、まだ誰の占有にも属しない物で、水中ないし水面上に存在した物をいいます。
遺失物も漂流物も「その他占有を離れた他人の物(占有離脱物)」の例示であることから、総称して占有離脱物横領罪と呼ばれています。
罰則は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料であり、「長期5年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」に該当するため、公訴時効は3年となります(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。
横領罪の時効はいつから進行する?
横領行為が終わった時点
時効期間が始まるスタート地点のことを時効の起算点といいます。この点、刑事訴訟法第253条第1項には、「時効は、犯罪行為が終わった時から進行する」と定められています。
横領罪には未遂規定がなく、預かった物や管理していた物を、自分のものとして扱い始めた時点で既遂となります。つまり、自分の所有物のように扱い始めた時点が「犯罪行為が終わった時」であり、時効の起算点となります。
例えば、次の時点が時効の起算点となります。
- 横領罪(単純横領罪):友人から預かったカメラを質入れした時点
- 業務上横領罪:会社の経理担当者が顧客からの入金を着服した時点
- 占有離脱物横領罪(遺失物横領罪):拾った財布を自分のものにした時点
なお、占有離脱物横領罪(遺失物横領罪)について、例えば拾った財布を最初は警察に届けるつもりで持ち帰ったが、その後「自分のものにしよう」と決めた場合、時効の起算点は持ち帰った時点ではなく、自分のものにすると決めた時点となります。つまり、持ち主に返さず、自分の所有物のように扱った時点が起算点となるのです。
複数に渡る横領行為があった場合の起算点
横領行為が複数回にわたる場合、時効の起算点は、原則として各横領行為ごとに独立して進行します。
ただし、複数回の横領が同じ目的のもとで繰り返され、「包括一罪」として扱われる場合には、最後の横領行為が行われた時点が時効の起算点となることがあります。包括一罪に該当するかどうかは、被害法益が同じであり、継続的な意思のもとで行われたかによって判断されるため、ケースごとに異なります。
例えば、会社の現金を毎月少しずつ抜き取るような手口の場合、原則として各回ごとに時効が進行します。しかし、同一の意図のもとで継続的に行われた場合は「包括一罪」としてまとめて扱われることがあり、その場合、最後に抜き取った日が時効の起算点となることがあります。
個々の横領行為が独立した犯罪として扱われるか、まとめて1つの犯罪とされるかは、事案ごとに判断されます。実際の適用は、行為の継続性や関連性など、具体的な事情を考慮して決められるため、一律の基準は存在しません。
共犯者がいる場合の起算点
横領罪に共犯者がいる場合、時効の起算点に影響を及ぼします。
共犯者のうち、最後に犯罪行為を行った者の時点を基準に時効が進行します(刑事訴訟法第253条2項)。
例えば、会社の同僚と共謀し、会社の備品を持ち出して転売していた場合、最後に備品を持ち出した時点が時効の起算点となります。
そのため、共犯者が長期間にわたって行為を続けていた場合、自分がすでに手を引いていたとしても、時効が完成しないことがあります。
横領の民事の時効は何年?
横領の民事の時効は3年または20年
結論として、横領による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者が損害および加害者を知った日から3年、または横領事件発生から20年のいずれか早い方で時効が成立します(民法第724条)。
横領罪を犯した場合、刑事責任に加えて民事責任(不法行為に基づく損害賠償責任)を問われる可能性があります。民事においても、消滅時効という制度があり、一定の期間が経過すると損害賠償請求権が消滅します。
例えば、銀行員が顧客の預金を横領した場合、7年後に公訴時効が成立し、刑事責任は問われなくなります。しかし、民事の時効が成立しない限り、損害賠償責任は引き続き負うことになります。
業務上横領の民事の時効
業務上横領については、不法行為に基づく損害賠償請求に加えて、債務不履行に基づく損害賠償請求も可能です(民法第415条1項)。業務上の横領は、企業と従業員との雇用契約に違反するため、その契約違反を理由に損害賠償を請求することができます。
債務不履行に基づく請求の時効期間は、次の2つのうち早い方です。
- 被害者が損害賠償請求権を行使できることを知った日から5年(民法第166条1項1号)
- 横領発生から10年(民法第166条1項2号)
例えば、横領が10年以上前に発生した場合、債務不履行に基づく請求は時効が成立している可能性があり、その場合は不法行為に基づく請求を検討することになります。
横領はなぜ発覚する?
横領は、発覚しにくい犯罪のように思われがちですが、さまざまな要因で明るみに出ることがあります。単純横領罪、業務上横領罪、遺失物横領罪について、それぞれ発覚の原因を解説します。
横領罪(単純横領罪)の場合は?
単純横領罪が発覚する主な原因として、以下のようなケースが考えられます。
- 預かっているものを返せなくなったとき
→単純横領罪が発覚する典型的なケースは、預かったものを返すよう求められた際に、すでに手元になくなっている場合です。例えば、友人から一時的に預かったゲーム機を勝手に売却してしまい、後日「返してほしい」と言われても返せない場合、友人が不審に思い、事実が発覚する可能性が高まります。 - 第三者の指摘により発覚
→単純横領では、持ち主本人以外の第三者によって発覚することもあります。例えば、預かった品を売却した場合、その品を購入した人物がSNSなどに投稿し、元の持ち主が偶然それを見つけるケースも考えられます。また、共通の知人から「あなたの持ち物が他人の手に渡っているのを見た」と指摘されることで、横領が発覚することもあります。 - 証拠が残りやすい状況
→預かり品の横領は、証拠が残りやすい特徴があります。特に、預かった際に契約書やメッセージのやり取りが残っていると、所有者が返却を求めた際に「確かに預けたはず」と証明しやすくなります。
業務上横領罪の場合は?
業務上横領罪では、企業や組織内での管理体制が強化されているため、発覚のリスクが高まります。
- 人事異動や退職がきっかけで発覚
→経理担当者が異動や退職をすると、新任の担当者が過去の会計データを精査することになります。その際、不自然な金銭の動きが見つかり、過去の横領が発覚することがあります。また、近年では企業のIT化・クラウド化が進み、過去の取引履歴をコンピューターが分析することで、従来よりも簡単に不正を発見できるようになっています。特に、関連会社を利用した資金の流用などもシステムによって容易に検出されるため、発覚のリスクは格段に高まっています。 - 社員による内部通報で発覚
→横領を行った本人はバレていないつもりでも、周囲の社員が不審な動きに気づいていることがあります。特に、経理業務に詳しい社員や、日頃から細かい取引をチェックしている人がいれば、異常に気づく可能性は高いです。また、社内には内部通報制度を設けている企業も多く、匿名での通報が可能な場合もあります。 - 税務調査や反面調査で発覚
→税務調査は、会社の申告内容を確認するために税務署などが行うものですが、この調査を通じて横領が発覚することがあります。特に、不正な経理処理を行っていた場合、調査官が怪しい点を見逃さず、不正が明るみに出る可能性が高くなります。さらに、税務調査の一環として取引先へ行われる反面調査も、横領発覚のきっかけになります。
遺失物横領罪の場合は?
遺失物横領は、さまざまな経緯で発覚する可能性があります。
- 防犯カメラの映像
→遺失物を拾得・着服する様子が防犯カメラに映っていた場合、映像解析やリレー捜査により身元が特定され、後日逮捕される可能性があります。 - 指紋の照合
→拾得物から指紋が採取され、過去に警察に登録された指紋と一致した場合、横領の事実が発覚することがあります。 - 質入れ・売却の履歴
→遺失物を質屋やリサイクルショップで売却すると、警察が盗品リストと照合し、買取業者から通報されることがあります。 - カード類の不正使用
→拾得したクレジットカードを無断で使用すると、カード会社や加盟店が不審に思い、警察に通報することで発覚するケースがあります。 - 職務質問での所持品検査
→職務質問を受けた際に、他人の免許証やクレジットカードなどが見つかると、被害届と照合され横領が発覚することがあります。
横領罪の時効完成を待つリスクと発覚後に直面するリスク
時効完成を待つリスク
時効の完成を待つことは、日々逮捕の不安を抱えながら生活することを意味します。横領を行った以上、逮捕されない保証はなく、明日、数週間後、あるいは数年後に突然逮捕される可能性もあります。その間、仕事や生活への影響、家族や周囲に知られる不安と向き合わなければなりません。
また、横領事件では、会社の内部監査や関係者の告発によって発覚するケースが多く、発覚後に捜査が急速に進むこともあります。万が一、警察に横領事件の被疑者として特定された場合、逃げ回っていた事実が「逃亡のおそれが高い」と判断され、逮捕される可能性が非常に高くなります。
さらに、逮捕は「逃亡のおそれ」や「罪証隠滅のおそれ」がある場合に行われますが、時効の完成を待っている状況が「罪を免れようとしている=逃亡のおそれがある」とみなされることがあります。時効を意識するあまり犯行を否認すると、罪証隠滅のおそれがあると判断されやすくなり、結果として逮捕のリスクが一層高まります。
時効を待つことは、単に時間をやり過ごすのではなく、むしろ自ら逮捕のリスクを高める行為になりかねません。
発覚後に直面する主なリスク
長期の身柄拘束
横領罪が発覚し、逮捕されると、長期間にわたって身柄を拘束される可能性があります。逮捕後の流れは以下のとおりです。
- 逮捕後48時間以内に送検(警察が事件を検察に送致)
- 検察官が24時間以内に勾留請求を判断
- 裁判官が勾留を決定した場合、最大10日間の勾留が認められる
- さらに最大10日間の勾留延長が可能
- 検察官が起訴・不起訴を決定する
勾留が決定すると、刑事処分(起訴または不起訴)が決まるまで最大23日間、留置所に拘束されることになります。この間、会社を無断欠勤することになり、業務に復帰できない状況が続くと、職場での立場が危うくなる可能性があります。
また、勾留後に起訴されると、保釈が認められない限り、裁判が終わるまで拘束が続く可能性があります。起訴後も勾留が続く場合、拘束期間が数か月以上に及ぶこともあり、社会復帰が困難になるリスクが高まります。
刑務所に収監される可能性
横領罪が刑事事件として起訴されると、高い確率で有罪となります。特に業務上横領罪では、被害額や悪質性によっては実刑判決を受け、刑務所に収監される可能性があります。
横領罪の法定刑は以下のとおりです。
- 単純横領罪(刑法252条):5年以下の懲役
- 業務上横領罪(刑法253条):10年以下の懲役
- 占有離脱物横領罪(刑法254条):1年以下の懲役
特に業務上横領罪は、企業の財産を管理する立場にある者が犯すため、刑罰が重くなる傾向があります。これは、企業や顧客の信頼を裏切る背信性が高いことや、被害額が大きくなりやすいことが理由です。 また、被害額が大きい場合や、会社に対する背信行為が悪質と判断される場合、実刑となる可能性が高まります。
また、日本の刑事裁判では、起訴されると99%以上の確率で有罪判決が下るため、前科がつくことはほぼ避けられません。 前科がつけば、社会生活のさまざまな場面で不利益を受ける可能性があります。
解雇と再就職の困難さ
横領罪が発覚すると、職場での立場が失われるだけでなく、再就職にも大きな影響を及ぼします。具体的には次のような影響が考えられます。
- 業務上横領罪が発覚した場合、懲戒解雇は避けられないと考えるべきでしょう。会社に損害を与えた以上、雇用関係を継続できないのは当然です。また、企業の信頼を損なう重大な違反行為であるため、多くの企業が厳格な処分を下します。
- 単純横領罪の場合でも、逮捕・勾留による長期欠勤や事件の報道によって、事実上の解雇につながる可能性があります。自主退職を余儀なくされるケースも少なくありません。
- 報道されると、社会的信用が失われ、再就職が困難になることもあります。特にインターネット上に名前が残ってしまうと、転職活動の際に不利になる可能性があります。
横領罪の時効の完成を待たずにすべきこと
前述したリスクを踏まないためには、はやめに以下のことを行っておく必要があります。
- ①示談交渉する
- ②自首する
- ③弁護士に相談する
①示談交渉する
まず、被害者と示談交渉することです。
横領をしてしまった場合、被害者に対する誠意ある対応が重要になります。示談交渉を行い、被害弁償を適切に進めることで、被害者の処罰感情が和らぎ、示談が成立しやすくなります。示談が成立すれば、被害者に被害届を提出しないよう求めたり、すでに提出している被害届を取り下げてもらったりすることが可能になります。
被害者が被害届を提出しなければ、捜査機関に事件が発覚するのを防ぐことができ、結果として出頭要請や取調べ、逮捕、長期間の身柄拘束、起訴による刑事裁判、懲役などの刑罰を受けるリスクを回避できます。
また、すでに被害届が提出されていても、示談が成立し、横領による損害について十分な被害弁償を行い、真摯に謝罪することで、刑事処分や裁判で有利な判断がなされる可能性が高まります。具体的には、不起訴処分となる場合や、執行猶予付きの判決が下されるケースも考えられます。
②自首する
示談による解決が難しいケースでは、自首を検討すべきです。
被害額が高額であり、一部しか弁済できない場合は、示談が成立しにくくなります。特に、大企業ではコンプライアンスの厳格化や株主への説明責任があるため、刑事告訴される可能性が高いのです。また、公務員による横領は、公的資金の不正として厳しく追及されやすく、少額でも捜査機関に被害申告されることが少なくありません。こうしたケースでは刑事事件化を避けにくいため、早期に自首することが重要です。
自首とは、犯人が自ら犯罪を捜査機関に申告し、その後の処分を求める行為です。自首が成立するためには、犯罪事実がまだ捜査機関に知られていない、または犯人が特定されていない段階で自己申告を行うことが必要です。自首をすることで、刑が軽減される可能性があります(刑法第42条1項)。
また、自首を行うことで、逮捕を回避できる可能性もあります。捜査機関は、被疑者を逮捕する際に、逃亡や証拠隠滅の恐れがあるかを判断します。自首によって「逃亡や証拠隠滅の恐れがない」と評価されれば、逮捕を免れることもあります。さらに、早期の自首は反省の意思を示すものとして評価され、その結果として有利な処分を受ける可能性が高まります。具体的には、不起訴処分となる場合や、執行猶予付きの判決が下されるケースも考えられます。
③弁護士に相談する
次に、弁護士に相談することです。
示談交渉や自首は自分で行うことも可能ですが、より円滑に進め、最大限の効果を得るためには弁護士の力が不可欠です。
横領事件では、示談交渉が重要な意味を持ちます。しかし、加害者本人が被害者に直接交渉を持ちかけても、感情的な対立から応じてもらえないことが多くあります。一方で、弁護士が間に入ることで、示談交渉に応じてもらえる可能性が高まります。横領による被害弁償の方法や示談金の提示など、弁護士が法的な観点から適切に交渉を進めることで、示談が成立しやすくなります。示談が成立すれば、被害届の取り下げや処罰感情の緩和につながり、不起訴処分の獲得や執行猶予付きの判決を得る可能性が高まります。
また、横領事件で自首をする際の対応も重要です。自首をしたからといって必ずしも逮捕を免れるわけではありません。特に、被害額が大きい場合や、勤務先が大企業や公的機関である場合は、捜査機関が厳しい姿勢を取ることが多く、逮捕されるリスクも考えられます。そのため、事前に弁護士のアドバイスを受け、逮捕の回避に向けた準備を整えておく必要があります。実際に自首をする場合も、一人で行くより弁護士に同行してもらうことで、精神的な安心感を得られるだけでなく、適切な対応をとることができます。
さらに、弁護士は示談や自首の対応だけでなく、捜査機関や裁判所とのやり取りを通じて、不起訴処分の獲得や刑の減軽、執行猶予付き判決の可能性を最大限に高めるための弁護活動を行います。横領事件では、適切な法的対応を早期に取ることが、今後の人生に大きな影響を及ぼします。そのため、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。
まとめ
横領罪には、単純横領罪・業務上横領罪・占有離脱物横領罪の3種類があり、それぞれ公訴時効の期間が異なります。時効が完成すれば刑事責任を問われることはありませんが、時効が完成する前に捜査機関に発覚すれば、逮捕や刑事裁判に発展する可能性が高くなります。また、公訴時効が成立しても、被害者から損害賠償請求(民事責任)を追及される可能性があるため、注意が必要です。
横領事件では、時効の完成を待つことには大きなリスクが伴います。逮捕や刑事裁判を回避するためには、示談交渉や被害弁償はできる限り迅速に進めることが重要です。また、示談が難しいケースでは、自首を検討することで刑の軽減や逮捕の回避につながる可能性があります。いずれの対応も、適切に進めるためには弁護士のサポートを受けることが有効です。
当事務所では、横領事件の示談交渉、逮捕の回避、不起訴処分の獲得を得意としており実績があります。親身かつ誠実に、弁護士が依頼者を全力で守りますので、横領事件を犯してしまい、いつ逮捕されるのか不安な日々を送っている方は弁護士までご相談ください。相談する勇気が解決への第一歩です。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|