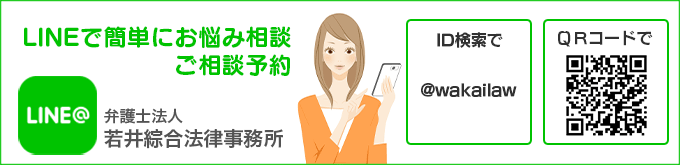「離婚調停が不成立となった場合、その後はどうなるのだろう?」
このようにお考えではないでしょうか。
この点、離婚調停の不成立後は、以下のいずれかの状態になります。
- 調停に代わる審判で審判離婚に至る
- 当事者間での再協議、再調停、離婚裁判のいずれかで離婚に至る
- 離婚が成立せず現状のままになる
この記事では、離婚問題に強い弁護士が、
- 離婚調停が不成立になる割合
- 離婚調停が不成立となった場合、その後どうなるのか
- 離婚調停が不成立となった場合の弁護士費用
- 不成立後に別居すれば離婚が認められやすくなるのか
- 不成立後に復縁することはあるのか
などについてわかりやすく解説していきます。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|
離婚調停の不成立とは?
離婚調停の不成立とは、調停委員会が「当事者間に合意が成立する見込みがない」又は「成立した合意が相当でない」と認めた場合に、調停が成立しないものとして、手続きを終了させることをいいます。
なお、相場をはるかに超えた金銭の支払いを要求するなど「合意が相当でない」場合は、あらかじめ調停委員から修正案が提示されるでしょうし、そもそも夫婦で合意しない場合が多いです。
したがって、離婚調停が不成立となるのは、多くの場合、調停委員会に「当事者間に合意が成立する見込みがない」と判断された場合です。
離婚調停が不成立となる割合
令和2年度司法統計によると、令和元年度の離婚調停で不成立となった件数は次のとおりです。
| 件数 | 割合 | |
| 調停成立 | 17,478 | 約48% |
| 調停不成立 | 9,318 | 約26% |
| 調停取り下げ | 6,758 | 約19% |
| 調停に代わる審判 | 2,433 | 約7% |
| 調停をしない | 314 | 約0.9% |
| 当然終了 | 98 | 約0.3% |
離婚調停が成立している割合が全体の約半数である一方、4件に1件の割合で離婚調停が不成立となっていることがわかります。
なお、調停不成立以外で離婚調停が終了することがあります。それが、上記表にある、
- 調停取り下げ
- 調停に代わる審判
- 調停しない
- 当然終了
の4つのケースです。
それぞれどのような終了のケースなのか、以下で確認しておきましょう。
| 調停取り下げ | 調停取り下げとは、離婚調停を申立てた申立人が申立てを取り下げることです。手続きは「調停申立て取下書」を申立て先の家庭裁判所へ提出するだけで済みます。取り下げるにあたって相手方の同意は不要で、取下書の提出により調停は終了となります。
「これ以上、話し合いを続けても埒が明かない」、「相手方が調停期日に出席しない」などという他、「調停外で合意が成立した」という場合にも申立てを取り下げます。 |
| 調停に代わる審判 | 調停に代わる審判とは、たとえば離婚することや離婚条件につき大筋で合意できているが、当事者間で僅かな意見の相違があるために調停が合意に至っていないような場合に、残りの細かい条件については裁判官の職権で一方的に条件を決めてしまう、という手続きのことです |
| 調停しない | 調停をしない場合の終了とは、たとえば、相手方が精神障害者、薬物乱用者等で調停期日における冷静な受け答えが期待できないなど、調停委員会が「性質上調停を行うのに適当でない」と認めた場合、又は調停不成立となった後ただちに離婚調停を申立てるなど「当事者が不当な目的でみだりに調停の申立てをした」と認めた場合に、調停を終了させることです。 |
| 当然終了 | 申立人又は相手方が申立て後に死亡した場合は、調停を継続する意味が失われますから、調停は当然に終了します。 |
離婚調停が不成立となる主なケース
相手が離婚調停を欠席し続ける
まず、相手が離婚調停に欠席し続ける場合です。
離婚調停は相手との合意を目指す場であって、相手が離婚調停に出席してはじめて成立するものですから、相手の欠席が続けば「当事者間に合意が成立する見込みがない」ものとして離婚調停は不成立となる可能性が高いです。
1度の欠席では、相手がその後翻意して出席する可能性もあるため、相手が何度か欠席してはじめて不成立となることが多いです。
離婚調停を欠席・呼び出し無視するとどうなる?相手が来ない場合の対応方法
相手が離婚を拒否している
次に、相手が離婚を拒否している場合です。
離婚調停が成立するには、相手が離婚に合意することが大前提となります。相手が離婚を拒否しているときは、相手の協力を得ながら離婚の話し合いを進めていくことは期待できず、「当事者間に合意が成立する見込みがない」ものとして離婚調停は不成立となる可能性が高いです。
相手が自分の有責性を認めない
次に、相手が不倫やDV・モラハラなどの有責性を認めない場合です。
相手と離婚するかどうかでもめているときは、相手に有責性があればそれを指摘することで離婚の方向へ話をもっていきやすくなりますが、相手が自分には非がないと頑なに否定するときは離婚の合意を形成することが難しく、「当事者間に合意が成立する見込みがない」ものとして離婚調停は不成立となる可能性が高いです。
親権でもめている
次に、親権でもめている場合です。
親権は数ある離婚条件の中でも唯一、離婚する前に決めなければならないものです。そのため、離婚すること自体には合意できている、親権以外の離婚条件については合意できるという場合でも、親権について合意できなければ離婚を成立させることはできませんから、離婚調停は不成立となる可能性が高いです。
親権以外の離婚条件でもめている
次に、慰謝料、財産分与などの親権以外の離婚条件でもめている場合です。
親権以外の離婚条件については必ずしも離婚する前に決めなければならないわけではありませんが、離婚当事者の双方、あるいは一方が離婚前に取り決めることを望む場合は、離婚を成立させることができませんから、離婚調停は不成立となる可能性が高いです。
離婚調停が不成立となったらその後どうなる?
それでは、離婚調停が不成立となるとその後どうなるのでしょうか。不成立後に離婚を望む場合にはどうすれば良いのでしょうか。以下で解説します。
審判移行はしないが「調停に代わる審判」がなされることがある
面会交流や婚姻費用の調停の場合は、調停が不成立になると自動的に審判(裁判官が一切の事情を考慮したうえで結論を出す手続き)に移行します。
しかし、離婚調停の場合は、不成立となっても自動的に審判に移行することはありません。
したがって、離婚調停が不成立となった後も引き続き離婚を望む場合には、後述するように、当事者間での再協議や再調停で離婚の合意に至るか、裁判で離婚についての決着をつける必要があります。
ただし、離婚調停が不成立となった場合に、「調停に代わる審判」がなされることがあります。
調停に代わる審判とは、たとえば離婚することや離婚の条件について大筋で合意できているという場合に、残りの細かい条件については裁判官が一方的に条件を決めてしまう、という手続きのことです。調停に代わる審判によって成立した離婚を審判離婚といいます。
もっとも、調停に代わる審判に対しては、夫婦の一方が、審判を告知された日から2週間以内に異議を申し立てることができます。そして、異議を申し立てられると調停に代わる審判の効力が失われてしまいます。このように、調停に代わる審判の効力は非常に弱いものです。
また、そもそも離婚の条件等につき合意できなかったため調停離婚が不成立となったわけですから、調停に代わる審判がなされても、夫婦の一方から異議の申し立てがなされる可能性が高いです。
そのため、実務では、離婚調停が不成立となった後に調停に代わる審判がなされることは稀です。
離婚調停不成立後も離婚を望む場合は、話し合い・再調停・離婚裁判
離婚調停の不成立後も離婚を望む場合には、次で示す3つの方法により、離婚に向けた対応を進めていくことになります。
- ①当事者間で再協議をする
- ②再度離婚調停を申し立てる
- ③離婚裁判を提起する
以下、①~③について解説していきます。
①当事者間で再協議をする
家庭裁判所を通さない当事者間(夫婦間)での協議は、実現可能かどうかは別として、いつでも可能です。離婚調停を申し立てる前はもちろん、調停中でも可能ですし、離婚調停が不成立となった後でも可能です。
もっとも、離婚調停が不成立となった後の話し合いは現実的には難しいことが多いことはお分かりいただけるかと思います。
話し合いが実現可能といえるのは、たとえば、離婚調停が不成立となった後に、夫婦の双方が弁護士を付けたなどごく限られた場合ですし、この場合でも、最終的に話がまとまるかどうかは不透明です。
話し合いでは離婚調停と同様、譲歩する姿勢を見せなければ結局のところ話はまとまりません。始めから譲歩しない姿勢を取る予定であれば、後述する離婚裁判を提起することを選択すべきでしょう。
また、仮に、話がまとまった場合でも、離婚調停が成立した際に作成される「調停調書」のような判決と同様の強制力のある書類は当然には作成されないことにも注意が必要です。
裁判外で話がまとまった場合は「合意書」が作成されますが、合意書はそれだけでは相手方の財産を差し押さえる強制力を有しません。
合意書に強制力を付与するには、合意書を強制執行認諾文言付き公正証書とする必要がありますが、その場合は相手方の承諾が必要ですし、公証役場に行く手間や時間・費用もかかります。
こうしたことを考えると、離婚調停の不成立後に話をまとめるのであれば、はじめから離婚調停で歩み寄りを見せて離婚調停を成立させ、調停調書を作成した方が精神的、経済的な負担の軽減という観点からもよいと考えます。
協議離婚とは|話し合いを有利に進めるための準備と後悔しない進め方
②再調停を申し立てる
離婚調停の不成立の結果に対して不服を申し立てる制度はない一方で、離婚調停が不成立となった後、再度、離婚調停を申し立てることは何ら制限されていません。
離婚調停不成立から再度の申立てまでにどのくらいの期間を空けなければいけないといった決まりもないことから、離婚調停不成立後、ただちに離婚調停を申し立てることも不可能ではありませんが、調停を開く実益がないとして裁判所に申し立てを受け付けてもらえない可能性があります。
そのため、再度、調停を開く実益があるかどうかをよく検討してから、再度、離婚調停を申し立てた方がよいでしょう。
③離婚裁判(離婚訴訟)を提起する
離婚調停が不成立となった後、話し合いができない場合は離婚裁判(離婚訴訟)を提起します。
離婚調停で、相手方と合意する見込みがなく、これ以上離婚調停を続けても無駄と判断した場合は、状況をみて申立てを取り下げて直ちに離婚裁判を提起する準備に入ることも一つの方法です。
また、家庭裁判所に離婚裁判を提起したい旨を伝えれば、家庭裁判所側から離婚調停を不成立にしてもらえることも多いです。
話し合いよりも離婚裁判を提起することの方が、離婚調停が不成立となった後の次のステップとしては最も現実的で、解決できる可能性が高いといえます。
離婚裁判は離婚調停と異なり、裁判が不成立となることはなく、裁判所が何らかの形で解決案を提示します。提示の仕方は判決と和解の2通りがありますが、多くの場合、まずは和解案を提示されます。
和解は夫婦間の合意ですので、離婚調停と変わりがないのではと思われる方がいるかもしれません。しかし、先ほども述べましたとおり、和解しなければ最終的に判決という形で結論が示されるため、合意に達しやすいという特徴があります。
また、財産分与や面会交流についてよりきめ細やかに解決案を示してくれることも和解の特徴といえます。
離婚が成立せず現状のままになる
調停不成立となり、調停に代わる審判もなされず離婚が成立しない場合は、前述の通り、夫婦のどちらかが話し合いをもちかけたり、再度の調停を申し立てたり、離婚裁判を提起しない限りは婚姻関係が継続した状態が続きます。
夫婦のどちらか一方が離婚を望んでいるときは、通常、上記のいずれかの手段をとってくることが考えられますが、それでも離婚が成立しない可能性が高いため、現状の状態が続いた状況となる場合があります。その場合というのが、離婚を望んでいる側が有責配偶者の場合です。
有責配偶者とは不貞などの有責行為をして自ら婚姻関係を破綻させた配偶者のことです。ただ、裁判所は、別居期間が長期に渡っている、有責配偶者が他方配偶者や子どもの離婚後の生活保障についてきちんと提案しているなどの事情がない限り、有責配偶者からの離婚請求は認めないとの考えをとっていますので、有責配偶者は離婚裁判を提起しようにも提起できず、現状のままの状態が続いてししまいます。
離婚調停を不成立としないために心がけるべきこと
離婚調停が不成立となった後、離婚裁判を提起できるとしても前述のとおり負担が大きいもの。できれば離婚調停で離婚のことを解決したいものです。
ここで、離婚調停を不成立としないために大切なことは、
- 主張を裏付ける証拠を事前に集めておく
- 相場を外れた過大な要求、自己の主張に固執しない
という点です。
たとえば、離婚調停で「相手方の不貞行為を理由に離婚したい」と主張しても、相手方の不貞行為を裏付ける証拠がなければ、相手方や調停委員を説得することができず、離婚について合意できずに離婚調停が不成立となってしまいかねません。
なお、証拠集めの大切さは離婚調停に限った話ではありません。離婚調停前の協議離婚はもちろん、離婚調停後の離婚訴訟でも極めて大切となってまいります。
そのため、離婚すると決めた段階で、相手方にはその意思を伏せた上で、様々な証拠を集めておくことが大切です。
また、養育費、財産分与、慰謝料などの財産が関わる場面、あるいは面会交流など子の監護に関わる場面において、過大な要求をする、あるいは条件を提示された際にご自身の主張に固執しないことも大切です。
離婚調停は、あくまで相手方との合意形成を図る手続きですから、相手方の主張にも一定の理解を示し、歩み寄りの姿勢を取ることが、離婚調停を成立させる上では大切となってまいります。
離婚調停の不成立に関するよくある質問
最後に、離婚調停の不成立に関するよくある質問にお答えします。
不成立は誰が決める?
離婚調停を不成立と決めるのは調停委員会です。
まずは、調停委員会で裁判官、調停委員が協議し、離婚調停を不成立とするかどうかの決議を行います。ここで過半数の者が、離婚調停を不成立とすることに同意した場合に、離婚調停を不成立とすることが調停委員会の意見となります。可否同数となった場合は、裁判官の意見が調停委員会の意見となります。
申立人、相手方が調停期日に出席する場合は、基本的に申立人、相手方、裁判官、調停委員、裁判所書記官が同席の上、裁判官より離婚調停を不成立とした旨の説明がなされます。
なお、申立人、相手方が調停の継続を望んだとしても、調停委員会の判断で離婚調停を不成立とされてしまうこともあります。
また、離婚調停を不成立とした調停委員会の判断に対して不服を申し立てることはできません。
不成立の場合の婚姻費用の支払い義務は?
婚姻費用の支払義務は、法律上の婚姻関係が続いている限り、すなわち、離婚が成立するまでは継続します。離婚調停が不成立となったということは離婚が成立しなかったということですから、婚姻費用の支払義務は継続します。
不成立の場合の弁護士費用は?
「着手金+報酬金」の料金体系で弁護士に離婚調停を依頼した場合、調停不成立となっても着手金は返金されません。着手金は業務処理の対価として支払う性質のものであるからです。一方、離婚成立を目指して弁護士に依頼した場合、調停が不成立である以上、報酬金は発生しません。そのため、離婚調停が不成立となった場合は、「着手金相場の20万円~30万円+日当、実費」がトータルの弁護士費用となります。
不成立後に別居すれば離婚が認められる?
別居の期間が長くなればなるほど、第三者に「夫婦関係が破綻している」と判断されやすくなりますから、再度の調停や裁判において離婚が成立する可能性は高くなります。ただし、離婚を前提に別居するには、離婚を見据えた準備をしてから別居する必要があります。
離婚調停は何回くらいで不成立となる?
先ほど述べたように、相手が離婚調停を1回欠席したからといって、離婚調停がただちに不成立となることはありません。したがって、少なくとも2~3回(2~3か月)程度はかかることを見込んでおいた方がよいでしょう。
離婚調停の不成立後に復縁することはある?
離婚調停は話し合いの場ですので、これまでため込んできた不平、不満を相手に伝えることができる絶好の機会でもあります。あなたから本音をぶつけられた相手は、あなたがどのような想いでいたのか、自分にどうして欲しいと考えていたのか調停の場ではじめて聞くことができ、それによって相手が改心すれば復縁につながる可能性があります。また、離婚調停は調停委員という第三者が夫婦の間に入りますから、感情的にならず冷静に自分の想いを伝えることができるのも復縁につながりやすい原因かもしれません。
その他、離婚調停という場ではじめて現実を直視できることも復縁につながりやすい原因の一つかもしれません。離婚調停まではお互いが感情的になり、後先考えずに離婚に一直線に走ってきたかもしれません。しかし、離婚調停では、調停委員から様々な説明やアドバイスを受け、冷静に子どものことや離婚後の生活のことなどについて考えることができます。そして、お互いに離婚が意外にも大変なこと、離婚後の生活が楽ではないこと、子どもにもいい影響を及ぼさないことに気がつくことができれば、離婚を選択しないことも十分に考えられるのです。
まとめ
離婚調停が不成立となった後は、当事者間での再協議または再調停で相手方と話し合いを続けるか離婚裁判を提起するかの方法を取ることが基本となります。このうち離婚裁判を提起するのが現実的と考えますが、裁判ゆえに一般の方にとっては負担が大きいです。
そこで、離婚裁判については弁護士に委ねた方が、ご自身の負担を軽減させながら手続きを進めることができます。お困りの場合は弁護士に相談しましょう。
当事務所では、離婚調停、離婚裁判の代理人経験が豊富な弁護士が在籍しております。親身誠実に、弁護士が依頼者を全力でサポートしますので、離婚を成立させたい方、調停や裁判を有利に進めたいかたは当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|