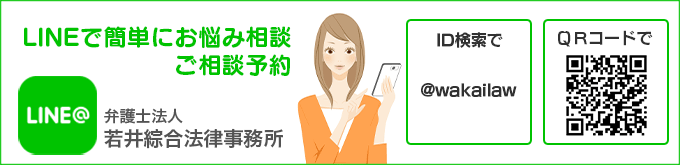- 養育費を支払ってもらえないで困っている…
- 弁護士に養育費請求を依頼するとどんなメリットがあるのだろう…
- 養育費請求を弁護士に依頼した場合の費用はいくらくらいだろう…
このようなお悩みや疑問を抱えていませんか?
この記事では、養育費問題に強い弁護士がこれらの悩みや疑問を解消していきます。
養育費請求をしたい方で、記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の弁護士までご相談ください。
誰でも気軽に弁護士に相談できます
養育費について弁護士に相談すべきケースは?
請求できる養育費の金額がわからないケース
具体的な養育費の金額については父母の話し合いで決定することができます。
しかし、相手と養育費の金額について折り合えないという場合には、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」に記載されている養育費の金額を参考に決定することもできます。
この「養育費算定表」を参考にすれば、おおよその養育費の相場をチェックすることができますが、具体的には個々の事案についてはさまざまな事情を考慮して、過去の審判例や裁判例に照らし合わせて検討する必要があります。
そのため、ご自身が相手に請求できる養育費の金額がどのくらいになるのか分からないという場合には、弁護士に相談すべきでしょう。
元配偶者と養育費について話し合えないケース
請求したい養育費の金額がはっきりしていても、元配偶者が養育費についての話し合いに応じてくれない場合には話が前に進みません。
そのような場合であっても弁護士に依頼しておくことで、適切に養育費を請求して話し合いに応じてもらえる可能性が高まります。
具体的には、相手方に対して内容証明郵便により養育費の支払を請求し、面会交流などその他事項と併せて養育費について交渉を重ねることになります。
相手も、代理人弁護士から来た通知については心理的に無下に扱うことがはばかられますし、気が進まない相手との話し合いや交渉についても弁護士に対応をお願いすることができます。
そのため、これまで話し合いに応じてこなかった相手を交渉のテーブルに着かせることが期待できます。養育費の請求について専門的な知識や経験を有する弁護士に依頼しておくことで、スムーズに相手との話し合いがまとまる可能性が高まります。
元配偶者が明確に養育費の支払いを拒絶しているケース
元配偶者が、理由をつけて「養育費は支払わない」と支払い拒絶の意思を明確にしている場合にも弁護士に依頼するのがよいでしょう。
まず、弁護士を代理人に立てて相手と交渉してもらうことで、当初は養育費の支払いを拒絶していた相手方を説得できる可能性が高まります。
そして、当事者間の話し合いでは養育費について話し合いがまとまらない場合には、裁判所を利用した手続きをとることができます。
具体的には、家庭裁判所に養育費の支払いをもとめて調停手続きや審判手続きを申し立てたり、離婚訴訟を提起したりといった方法がとれます。調停手続きや審判手続きについては、弁護士に依頼しなくても申し立てることができますが、弁護士に依頼して専門的な知識や交渉力を利用した方があなたにとって有利に進められる可能性が高まります。
また裁判手続については、証拠に基づいて事実や法的な主張を行う必要があり、手続きも複雑な場合ありますので必ず弁護士に依頼すべきです。
以上から、相手方が養育費の支払いを拒絶している場合も、弁護士に相談することがおすすめです。
元配偶者が約定どおりに養育費を支払わないケース
父母間で子どもの養育費について合意ができ取り決めをしていたとしても、相手がその約束通りに支払いをしないというケースも多く存在しています。
このようなケースでお困りの場合にも弁護士に相談することで、とるべき適切な方法やアドバイスを受けることができます。
ケースによっては相手との話し合いや交渉によって解決可能な場合もあります。また、家庭裁判所に履行勧告を求めたり強制執行を申し立てたりするサポートを受けられるので、弁護士に依頼しておくことで適切に対処できることが期待できます。
相手の給与債権を差し押さえるには、原則として調停や審判手続き、訴訟を提起して養育費について定めなければ申し立てられません。公正証書で養育費の支払いを合意していた場合にはそのような手続きを省略して強制執行ができる場合もあります。
離婚後に元配偶者と連絡がとれなくなったケース
養育費を請求したくても、離婚してから相手方とまったく連絡が取れなくなった場合には、実際に支払いを受けることができないケースもあります。相手が話し合いの途中で行方知れずになってしまう場合も多々あります。
しかし、弁護士に依頼していれば、相手方の所在や連絡先を調査できる場合があり、養育費の支払いを請求できる可能性が高まります。
養育費問題を弁護士に相談するメリット
請求すべき養育費の金額が把握できる
養育費を受け取りたいけれど、請求すべき金額がわからないという依頼者は多いです。
前述のように親権者が受け取るべき養育費については家庭裁判所が公表している「養育費算定表」を参考にすることである程度の相場を把握することはできるでしょう。
しかし、双方の収入や生活状態、家庭環境、子どもの状況などによって具体的な養育費の請求金額はケースバイケースで変動します。
そのため過去の裁判例や審判例などを参考にすると相場よりも高額な養育費を受け取れる場合もあるのです。弁護士が適切なヒアリングを行いますので、あなたの場合はどれくらいの養育費を請求するのが適正なのかを知ることができます。
相手とのめんどうなやり取りは弁護士に任せることができる
弁護士にお願いすることで、相手とのやり取りや話し合いをすべて弁護士に一任できる場合もあります。
養育費について双方が揉めている場合には、当事者同士が顔を突き合わせて話すことで無用に感情的になってしまったり、お互いが双方の不満をぶつけ合うだけに終始してしまったりするケースもあります。そのような場合にはまともに話し合いを前進させることもできません。
しかし、弁護士に依頼した場合には、相手との書面や電話を通じたやり取りや、直接会っての話し合い・交渉についても一任することができます。依頼者は弁護士からの報告を受けるだけで済み、手続き的なストレスも軽減できるため、大きなメリットであると言えるでしょう。
裁判所を利用して手続きも引き続きお願いできる
相手方との話し合いが平行線をたどりまとまらない場合には、調停や訴訟などを利用して解決を図るしかありません。
調停や訴訟においては証拠に基づいて説得的に依頼者の主張を展開していくことが重要となりますので、法律の専門家である弁護士に依頼しておくことは非常に心強いはずです。
期日には本人の出頭を求められることがありますが、弁護士も同席してくれるため適切なサポートを受けることが期待できます。
依頼者に有利な内容でまとめられる可能性が高まる
弁護士に依頼せずにご自身で手続きをする場合には、どうしても知識が不足していたり相手の圧力に動じてしまったりして、相場より低額で合意してしまったという事例が後を絶ちません。
弁護士は依頼者の経済的な利益が最大化するように適切に主張・交渉してくれますので、依頼者にとってより有利な内容でまとめられる可能性があります。
将来的に相手方が養育費の未払いをしにくい内容でまとめられる
弁護士に依頼した場合には、話し合いの内容を、離婚協議書や合意書などを公正証書の形で残しておくことが一般的でしょう。
執行認諾文言付き公正証書があれば債務名義とすることができますので、ただちに強制執行の手続きを申し立てることが可能になります。
養育費請求の弁護士費用の内訳と相場
養育費の請求を弁護士に依頼した場合にかかる弁護士費用の内訳は、大きく「法律相談料」、「着手金」、「報酬金」、「日当費」、「実費」に分けることができます。
法律相談料
法律相談料は、弁護士と法律相談をした場合にかかる費用のことです。
法律事務所に養育費の請求を依頼したいと申し込んでも、いきなりその依頼を引き受けてくれるわけではありません。
まずは、弁護士に現在か抱えている問題点、悩みなどを話し、弁護士からアドバイスや弁護士費用に関する説明を受け、その上で弁護士に依頼するかどうか決めるための手続きが初回の法律相談です。
無料の場合は1回限り、30分などと時間制限が設けられている場合が多いです。有料の場合は5,000円~が相場といえます。
着手金
着手金は、弁護士に養育費の請求を依頼した直後、つまり、弁護士(法律事務所)と委任契約を締結した直後に発生する費用です。
満足のいく養育費を請求できたか否か、弁護活動の成果が得られたか否かにかかわらず、一度支払った着手金は返金されません。また、着手金という名のとおり、基本的に着手金を支払わないと、弁護士は弁護活動を始めてくれません。
着手金は一括で支払うことが原則ですが、分割の支払い可能な法律事務所もありますので一度相談してみましょう。
養育費請求を含む離婚問題全体の解決の依頼費用の相場は25万円~30万円程度、離婚後の養育費請求の依頼費用の相場は15万円~20万円程度となります。
報酬金
報酬金は、弁護活動による成果に応じて発生する費用です。
基本的に、基礎報酬金と追加報酬金の2階建てとなっている場合が多いです。
基礎報酬金は20万円などと固定されています。
他方で、養育費の追加報酬金は獲得した養育費(経済的利益)の5年分の10%(養育費請求する場合)、あるいは減額した養育費(経済的利益)の5年分の10%とされていることが多いです。
養育費は、子供の年齢によっては、数十年に渡って相手方に請求しなければならない場合もあります。その場合、そのすべての養育費を算定の対象とされると追加報酬金があまりにも高くなりすぎるおそれがあります。したがって、「5年分」などという限定を設けて調整が図られています(法律事務所によって1年~5年といった幅があります。例えば、1年の場合には追加報酬金が20%、3年の場合には15%などの設定がされています)。
日当費
日当費は、弁護士が法律事務所外で弁護活動を行った際に発生する費用です。弁護活動の内容によるため相場はありません。
養育費の請求に関していえば、相手方との養育費に関する交渉を事務所外で行う際に日当費が発生する可能性があります。
また、交渉で話がまとまらず、調停、訴訟へと手続きが進んだ場合に、弁護士が裁判所へ出廷する際に日当費が発生します。
通常、「裁判所への出廷1回につき3万円」などと固定の金額を設定されていることが多く、活動の回数が増えれば増えるほど金額は高くなります。
報酬金と同様、日当費は契約時には予測できない金額で、弁護士の弁護活動によっては高くなる可能性があることは頭に入れておくべきです。
実費
実費とは、その名のとおり、弁護活動によって実際にかかった費用のことです。弁護活動の内容によるため相場はありません。
たとえば、養育費を確実に支払ってもらうため、離婚協議書を強制執行認諾付き公正証書という公文書にすることがあります。その場合は作成費用、事務手数料が発生します。
その他、相手方に書面を送る際にかかる郵送費、弁護士が裁判所へ出廷する際にかかる交通費などがあります。交通費については、法律事務所から裁判所までの距離が遠ければ遠いほど高くなります。少しでも弁護士費用を節約したいという方は、裁判所から近い法律事務所に所属する弁護士を選ぶことも一つの方法です。
養育費の弁護士費用を払えない場合には?
分割払い・後払いに対応した事務所に依頼する
弁護士費用を一括で支払うことが難しい場合には、分割払いや後払いなどに対応している法律事務所を探すことがおすすめです。
費用体系については各法律事務所によって異なっています。中には着手金が無料の事務所や完全成功報酬型の事務所もあります。
法テラスを利用する
法テラスには、資力が乏しく弁護士費用を負担できない人を対象に、弁護士費用を援助する民事法律扶助制度が存在しています。
法テラスを利用することで弁護士費用を立て替え払いしてもらえ、法テラスに対して月々1万円ずつ返済していくことができます。
このような制度を利用するためには収入や資産状況に一定の要件があるため、ご自身が対象となるか否かは事前に確認しておく必要があります。
自分で養育費を請求する
どうしても弁護士費用が捻出できない場合には、ご自身のみで養育費支払い請求をしていくこともできます。
そのような場合であっても弁護士事務所や弁護士会で実施している無料法律相談を適宜利用することで、弁護士に専門的な意見を聞きながら進めることができます。相手方と大きく対立していない場合や弁護士を依頼するほどこじれていない場合には弁護士を立てずにご自身で解決できる場合もあります。
しかし、双方で対立が深まった場合や事態が硬直状態となり進めることができなくなった場合には、前向きに弁護士に依頼することを検討してください。
まとめ
養育費は、お子様やご自身の生活にとって大切なお金です。月々の額は少額でも積み重なれば、大きな金額となります。養育費を支払われてない方は、まずは弁護士に相談してみましょう。
弊所では、養育費問題の解決を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力でバックアップしますので、養育費の請求や未払いなど養育費問題でお困りの方はまずは弊所の無料電話相談をご利用下さい。相談する勇気が解決へと繋がります。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|