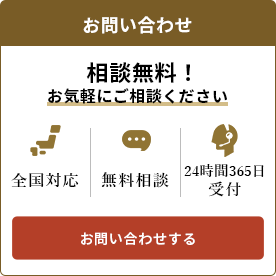- そもそも勾留ってどういう意味?
- どういった要件が揃えば勾留されるの?
- 勾留されるとどれくらいの期間、身柄拘束される?
こういった疑問をお持ちではないでしょうか?
そこでこの記事では、刑事事件に強い弁護士がこれらの疑問を解消していきます。また、勾留を回避するために何をすべきか、勾留されてしまった人が釈放されるための手段についても合わせて解説していきます。記事を読んでも問題解決しない場合は、弁護士に気軽に相談しましょう。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
目次
勾留とは

勾留とは、一定期間、身柄拘束されることです。逮捕は長くても約3日程度の身柄拘束ですが、勾留されるとそれ以上の身柄拘束となる可能性が高くなります。
勾留の種類は2つ
勾留は被疑者勾留と被告人勾留の2種類があります。
被疑者勾留
被疑者勾留とは逮捕後、起訴されるまでの間の勾留のことです。逮捕されると次の流れで進んでいきます。
- 逮捕
- 刑事施設(留置場など)に収容
- 送検
- 検察官の勾留請求
- 裁判官の勾留質問
- 勾留決定(勾留)
- 捜査
- 起訴・不起訴
前述のとおり、逮捕から勾留までの間(逮捕の効力)は約3日間です。この間、釈放されることもありますが、釈放されずに勾留決定が出ると勾留されてしまいます。勾留後は、釈放されるまで、刑事施設で生活しながら取調べ等の捜査を受け、起訴・不起訴の判断を待ちます。もっとも、勾留決定後でも、起訴・不起訴の判断がなされる前に釈放されることがあります。
被告人勾留
被告人勾留とは起訴後の勾留のことです。
被疑者勾留のまま起訴されると、前述のような手続きを経ることなく自動的に被告人勾留へと移行してしまいます。起訴されると刑事裁判を受ける必要があります。釈放されるまでは引き続き刑事施設で生活し、裁判の日になれば、施設職員の護送の下、裁判所へ出廷します。
逮捕と勾留の違い
逮捕と勾留の違いはどこにあるのでしょうか。
いずれも被疑者の逃亡・罪証隠滅を防止するために身体拘束をするという点では共通しています。
まず、「逮捕」とは勾留に先立ち比較的短時間(最大72時間)被疑者を拘束する強制処分を指します。逮捕は逮捕令状に基づいてなされる通常逮捕が原則ですが、例外として現行犯逮捕・緊急逮捕が法定されています。
これに対して、「勾留」とは逮捕に引き続き更なる身体拘束が必要な場合になされる強制処分を指します。勾留するには裁判官による勾留状の発付が必要です。
被疑者については、勾留に先立って逮捕の手続きが先行していなければなりません。このようなルールを逮捕前置主義と呼びます。このようなルールがある理由は、身体拘束の当初は事情変更が生じやすく犯罪の嫌疑や身体拘束の必要性の判断が流動的であるためです。すなわち一挙に長期間の拘束(勾留)はせずに、短期間の拘束(逮捕)を先行させることで勾留に至らない釈放の可能性を認めているのです。
勾留と拘留との違い
勾留と拘留は読み方は同じですが、意味はまったく異なります。両者の違いは、刑罰かどうかという点です。すなわち、勾留は刑罰でないのに対し、拘留は懲役、罰金などと同様に刑罰の一種です(刑法9条)。
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
勾留されても刑罰を科されるわけではありません。起訴され刑事裁判を受け、判決(または命令)で有罪認定を受けなければ刑罰を科されることはありません。
反対に、勾留されなくても(在宅のままでも)、上記の経過を経れば拘留を科される可能性はあります。もっとも、拘留が規定されている罪は少ない上に、検察が拘留の求刑をするケースはほとんどありません。
勾留の要件

勾留の要件は勾留の理由と勾留の必要性があることです。要件は被疑者勾留の場合も被告人勾留の場合も同じです。
勾留の理由があること
勾留の理由があるといえるためには「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があること」が必要です。罪を犯したと疑うに足りる相当な理由とは、確実に犯人とはいえないものの、6割~8割程度の確率で犯人といえる、ということを意味しています。
また、上の要件に加えて、次のいずれかの要件を満たすことが必要です。
- 住居不定であること
- 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること
- 逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があること
いずれの場合も今後の捜査や裁判に支障をきたすことから、勾留の理由にあげられています。
住居不定であること
逃亡生活をしている場合はもちろん、
- ネットカフェやホテルで寝泊まりしている場合
- 車上生活をしている場合
- 自宅に帰らず知人宅で寝泊まりしている場合
なども住居不定と判断される可能性があります。
罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること
殺人で使ったナイフを処分する、重要な証言をもつ被害者や参考人に暴力を振るったり、脅迫するなど、物的・人的証拠を隠滅する可能性がある、ということです。「相当な理由」があることが必要ですから、単なる抽象的な可能性では足りず、何らかの具体的事実によって裏付けられた蓋然性があることまで必要とされます。
逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があること
被疑者が現に逃亡しているか、将来起訴されることをおそれて捜査機関にとって所在不明になるおそれがある、ということです。
逃亡のおそれがあるかどうかは、
- 身上関係(家族関係、年齢、職業・職歴、資産状態など)
- 住居状態(居住形態、居住期間、転居歴など)
- 前科・前歴の有無及びその内容
- 余罪の有無
などを総合的に勘案して判断されます。
勾留の必要性があること
勾留の必要性とは、勾留の理由は認められるものの、なお、捜査して刑事処分(起訴、不起訴)を判断するため、起訴して裁判を受けさせるために身柄拘束する必要があるのか、ということです。
通常、勾留の理由が認められると勾留の必要性も認められることが多いです。
ただ、たとえば、
- 住居不定であっても、適切な身元引受人がいる場合
- 罪証隠滅のおそれは認められるものの、罰金又は不起訴が見込まれる場合
などは勾留の必要性がないと認められる場合もあります。
勾留の期間、延長・更新

勾留の期間や期間の延長・更新は被疑者勾留と被告人勾留とで異なります。
被疑者勾留の場合
被疑者勾留の勾留期間は、はじめ検察官の勾留請求日を含めて「10日」と固定した期間が決まっています。その後、検察官が期間の延長を認めた場合は、1日~10日の範囲内で期間をして裁判所に勾留期間の延長請求を行います。
裁判所は検察官から提出された書面、記録をもとに、勾留期間を延長することにつき「やむを得ない事由」があるかどうかを見極めます。そして、やむを得ない事由があると判断した場合は、1日~10日の範囲内で期間の延長を決定します。
この際、裁判所は検察官が指定した期間を参考にはしますが、それに縛られずに独自に期間を設定することができます(もっとも、実際は、検察官の指定した期間かそれ以下の期間となることがほとんどです)。
「やむを得ない事由」とは
やむを得ない事由とは、事件の困難性、あるいは、証拠収集の遅延若しくは困難等により、勾留期間を延長して更に調べるのでなければ起訴若しくは不起訴の決定をすることが困難な場合をいう、とされています。
具体的には、
- 否認事件
- 重大事件(殺人、強盗殺人、放火、特殊詐欺、ひき逃げ など)
- 関係者が多い事件
- 薬物事件
などの多くは、勾留期間を延長されると考えておいた方がよいです。
被告人勾留の場合
被告人勾留の勾留期間は、はじめ起訴された日を含めて「2か月」です。その後は、裁判所が刑事訴訟法89条1号から6号に規定される更新理由があると認めた場合には、理由を指定した上で1か月ごとに期間を更新されます。理由があると認められる限り、何度でも更新されます。ただし、2号、5号を理由とする場合の更新回数は1回です。
勾留を回避するためにやるべきこと

勾留を回避するには、まずは弁護士との接見を要請しましょう。知っている弁護士がいればその弁護士、いない場合は当番弁護士でもよいです。あるいは、逮捕されたことを知ったご家族などが接見を要請してくれるかもしれません。接見によって弁護士から勾留回避に向けてのアドバイスを受けることができます。
次に、接見した弁護士に弁護活動を依頼します。ただし、この場合は国選弁護人ではなく、私選弁護人としての活動を依頼することになります。国選弁護人は勾留された後に選任されるからです。
私選弁護人としての活動を依頼する場合は弁護士費用を負担しなければなりません。着手金(※)の額や支払い方法などを接見時に弁護士によく確認しておきましょう。
※私選弁護人が弁護活動に着手するためのお金。基本的に弁護士は着手金を支払わなければ弁護活動をはじめてくれません。
勾留後に早期釈放してもらうための方法

弁護士を選任する
勾留後に早期に釈放してもらいたい場合には弁護士に依頼してください。
ここで依頼できる弁護人の種類として、「国選弁護人」と「私選弁護人」の2種類に分けられます。
「国選弁護人」とは、「弁護士に依頼する経済的余裕がない人」に対して、一定の条件を満たす場合に弁護士費用を国が立て替えてくれるという制度です。経済的な負担がないという点は国選弁護人のメリットですが、国選弁護人は弁護人名簿に従って自動的に選任されることになるため弁護士を自由に選ぶことができません。
これに対して「私選弁護人」とは、任意の弁護士に依頼して刑事弁護人として就任してもらった弁護人です。私選弁護人は自分で弁護士費用を支払って弁護士に依頼することになりますが、信用できる刑事弁護に強い弁護士を選んでお願いすることができるというメリットがあります。
準抗告を申し立てる
起訴前は、主に、裁判官が出した勾留決定に不服を申し立てる「準抗告」という手段を使います。弁護士が準抗告申立書という書類を作成し、被疑者に逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないことを証明する書類(家族の身元引受書、上申書など)とあわせて裁判官に提出します。裁判官は検察官からも意見を聴いた上で申立てを認めるか、認めないかを判断します。
勾留取消を申し立てる
刑事弁護人を選任したあとには、勾留取り消しの申立てを行ってもらうこともできます。
裁判官による勾留決定がされて以降、被疑者の状況が変化することはよくあります。例えば、犯罪の嫌疑がなくなった場合、証拠隠滅の可能性がなくなった場合、被害者と示談が成立し被害弁償が完了したような場合には、これ以上の勾留の必要がないと判断され、勾留取消が認められる可能性も十分にあります。
不起訴処分を獲得する
勾留には「起訴前」勾留と、「起訴後」勾留があります。
起訴前勾留は最大で20日間の身体拘束です。一方で起訴後勾留は判決が下されるまで拘束が続くことになります。
つまり不起訴処分となった場合には、最大20日間の起訴前勾留だけで釈放されることになります。
したがって、早期に釈放され社会に戻るためには不起訴処分を獲得することがもっとも重要となるのです。
保釈請求をする
起訴後は、保釈請求して保釈(起訴後の釈放)を求めます。弁護人が保釈請求書を作成し、身元引受書や上申書などの書類とあわせて裁判所に提出します。裁判所は検察官からも意見を聴いた上で請求を認めるか認めないかを判断します。
保釈請求が許可されるには、証拠隠滅のおそれがないこと、常習性がないこと、お礼参りのおそれがないこと、氏名・住所が明らかであることなどの条件をクリアする必要があります。
請求が許可された場合は、裁判所に保釈保証金を納付した後に釈放されます。保釈金の額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならないと法律で定められています(刑事訴訟法93条2項)。
釈放とは?保釈との違いや認めてもらうための条件を分りやすく解説
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|