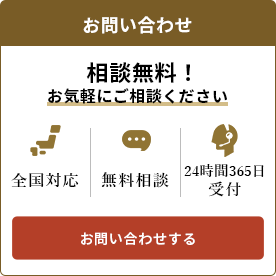- 釈放とはどういう意味?保釈とどう違うの?
- 早期釈放のためにはなにをすればいいの?
この記事では、こ刑事事件に強い弁護士がこれらの疑問や悩みを解消していきます。
逮捕されて身柄拘束をされている大切な方を一刻も早く収容施設から出してあげたい方は最後まで記事を読んでみて下さい。記事を読んでも問題解決しない場合は弁護士までご相談ください。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
目次
釈放とは~保釈との違い

釈放とは、逮捕や勾留によって留置場や拘置所に、懲役や禁錮などの刑罰の執行などによって刑務所などに収容されたものの、身柄拘束を解かれることをいいます。
保釈も釈放の一部ですが、釈放されるタイミングが起訴後、判決が確定するまでの間という点で、他の釈放と異なります。
仮釈放とは?3つの条件と期間、許可のために身元引受人が出来ること
以下では、釈放されるタイミングなどについて詳しく解説します。
釈放のタイミングと条件

釈放されるタイミングは、
- 逮捕後勾留までの間
- 勾留後起訴されるまでの間
- 起訴後判決までの間
- 判決後裁判が確定するまでの間
にわけることができます。
逮捕後勾留までの間
逮捕後勾留までには、
- 警察官の弁解録取
- 送致(送検)
- 検察官の弁解録取
- 勾留請求
- 裁判官の勾留質問
- 勾留許可決定
という流れで進んでいきます。
もっとも、①、③、⑤の後に釈放される可能性があります。また、⑥により勾留されても、弁護人が裁判所に対して不服を申し立て(準抗告)、その不服が認められると釈放されます。
この段階で釈放されることが多いのは次のようなケースです。
- 犯罪自体が軽微
- 定職に就いている
- 家族などの適切な身元引受人がいる
- 被害者と接触するおそれがない
- 罪を認めている
- 被害者と示談交渉中である
勾留後起訴されるまでの間
勾留されるとはじめ10日間、その後、最大で10日間、身柄拘束される可能性があります。もっとも、その間、前述のとおり、弁護人の不服申し立て(準抗告)が認められることで釈放される可能性はあります。準抗告のほかにも、
- 勾留取消請求(逃亡や証拠隠滅の恐れがなくなり勾留の必要性がなくなった時に裁判所に対して勾留の取り消しを求める請求)
- 勾留の執行停止の申立て(被疑者・被告人が病気などの治療を受ける必要がある場合や学校の入学試験を受けたいなどの場合に、裁判所の職権で一時的に釈放するよう申し立てること)
によって釈放されることもあります。
また、検察官の判断で釈放されることもあります。検察官の判断で釈放されるのは、検察官が必ず不起訴とする、あるいは不起訴とする可能性が高いケースです。たとえば、次のようなケースです。
- 親告罪で被害者等の告訴権者が告訴を取り消した場合(必ず不起訴となります)
- 被害者と示談が成立した
- 勾留期限までに捜査機関が起訴するに足りる証拠を集めることができなかった
起訴後判決までの間
起訴後の釈放を保釈といいます。保釈されるのは弁護人による保釈請求が許可され、裁判所に保釈保証金を納付することが条件です。保釈の許可条件などについては、後記で詳しく解説します。
なお、検察官が行う起訴には、「公判請求」という公開の法廷で審理を求める起訴のほか、「略式起訴(略式命令請求)」という裁判をせずに書面での審理のみで罰金もしくは科料の刑罰の言い渡しを裁判所に求める起訴があります。略式起訴をされると通常はその日のうちに裁判所から罰金や科料を支払うよう命令が出され、支払いをすると即日釈放されます。
判決後裁判が確定するまでの間
判決時に勾留されている(身柄拘束されている)場合でも、以下のケースでは釈放されます。
- 全部執行猶予付きの判決を受けた
- 罰金・科料のみの判決を受けた
- 無罪判決を受けた
また、実刑判決を受け、引き続き身柄拘束された場合でも、裁判が確定するまでの間は保釈請求することができます。そして、保釈請求が許可され、裁判所に保釈保証金を納付すれば釈放されます。
保釈のタイミング・流れ・条件

保釈とは、起訴された後の釈放のことです。保釈までは、起訴された後に、
- 裁判所に保釈請求書等を提出する
- 裁判官が検討する
- 裁判官が保釈許可決定を出す
- 裁判所に保釈保証金を納付する
というのが基本的な流れとなります。
①裁判所に保釈請求書等を提出する
保釈請求に向けた活動を行うのは、被疑者・被告人についた私選・国選の弁護人です。弁護人は保釈請求しようと考えた段階で保釈請求に向けた活動を始めます。具体的には、被疑者・被告人との接見のほか、
- 被害者との示談交渉を進展させる
- 示談を成立させる
- 身元引受人から、保釈後の監督意思・監督体制について聴き取りを行う
- 専門の治療機関、被告人の受け入れ機関等との調整
などです。
そして、保釈請求書のほか必要書類を揃えて準備が整った段階で、保釈請求書等を裁判所に提出します。被疑者・被告人が一刻も早い保釈を切望している場合は、起訴された段階を見計らって保釈請求することもあります。
②裁判官が検討する
裁判官が弁護人の保釈請求を受理すると、裁判官は被疑者を起訴した検察官に、弁護人からの保釈請求があった旨を通知します。また、同時に、裁判官は検察官に弁護人の保釈請求に対する意見書を提出するよう求めます。
裁判官は、基本的には、弁護人から提出のあった書類と検察官から提出される意見書、事件記録をもとに、保釈請求を許可するかどうかを判断します(弁護人、検察官と直接面談、あるいは電話して意見を聴くときもあります)。
そのため、検察官の意見書等の提出が遅れれば遅れるほど裁判官の判断も遅れ、保釈許可までの時間もかかってしまいます。
③裁判官が保釈許可決定を出す
裁判官は弁護人の意見、検察官の意見を参考にしながら、保釈請求を許可するかどうかを判断します。保釈請求が許可されるためには、まず、以下の刑事訴訟法89条1号から6号のいずれにも該当しないことが必要です。
第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
1号から6号に該当する事情がない場合は保釈請求が許可されます。これを権利保釈といいます。
また、仮に、1号から6号に該当する事情がある場合でも、
- 逃亡または罪証隠滅のおそれがない
- 身柄拘束を受けることによる健康上、経済上、社会生活上、または裁判の準備上の不利益が大きい
という場合は、裁判官の裁量で保釈請求が許可されることがあります。これを裁量保釈といいます。
④裁判所に保釈保証金を納付する
裁判官の保釈許可・不許可の判断は、弁護人に通知されます。
保釈許可の場合は、弁護人(あるいは法律事務所の事務員)が、ご家族などからあらかじめ預かっておいた保釈保証金用のお金を裁判所に納付します。保釈保証金の額は、裁判所が犯罪の性質、被告人の性格・資金を考慮し、被告人の裁判への出頭を保証するに足りると考える金額を指定します。
裁判所に保釈保証金が納付されると、裁判所から検察官に保釈保証金が納付された旨を通知します。検察官はその通知を受けて、被告人が拘束されている施設の職員に被告人を釈放するよう指揮します。この指揮に基づいて被告人は釈放されます。
なお、保釈許可決定に対して、検察官から不服を申し立てられることがあります。そして、検察官の不服申し立てが認められた場合は、保釈許可決定は取り消され、身柄拘束が継続します。
保釈保証金を準備できない場合には?
保釈保証金を準備できない場合には、保釈保証金の立て替え払いをしてくれる「日本保釈支援協会」の利用を検討してください。
この「日本保釈支援協会」を利用するには、被告人やその家族が申込みをする必要があります。そして被告人の更生の点などから審査を経て、立て替え限度額500万円の範囲内で立て替え払い契約を締結することになります。その後担当弁護人名義の口座に立替金が入金されることになります。
立て替え期間は「2カ月」とされているため、2カ月後には返済する必要があります。
また立て替え手数料や事務手数料2200円の支払いが必要となります。立て替え手数料については段階的に定められており、立替金「50万円まで」の場合には13,750円、最大「500万円」の場合には137,500円となっています。
なお、保釈保証金ではなく、弁護士費用が支払えない場合には「国選弁護人制度」や日本弁護士連合会(日弁連)の「刑事被疑者弁護援助制度」を利用することができます。
早期釈放のためにすべきこと

まずはできるだけ早く弁護士をつける
逮捕され身体拘束を受けた際には、できるだけ早く弁護士に依頼して弁護方針を構築する必要があります。
弁護士に依頼すると高額な費用を請求されると誤解している方もいらっしゃいますが、逮捕直後には「当番弁護士制度」という無料で一回だけ弁護士を呼ぶことができる制度が用意されています。当番弁護士に相談するのは弁護士会に連絡をするだけですので被疑者本人でもその家族でも可能です。
当番弁護士にそのまま弁護活動を行ってもらいたいという場合には、その弁護士を私選弁護人として選任することができますし、またそれとは別の弁護士を私選弁護人に選任することもできます。また弁護士費用を支払う金銭的な余裕がない人の場合には「国選弁護人制度」を利用できる場合があります。
いずれにしても身体拘束を受けた直後から、弁護人としっかりとコミュニケーションをとり弁護方針を決め、早期に釈放されるように弁護活動に動いてもらうことが何より重要です。
被害者と示談を成立させる
被疑者が被害者に謝罪して示談を成立させることも早期釈放のためには重要です。被害者が被疑者の謝罪を受け入れ示談金・解決金を支払うことで被害届や告訴を取り下げてくれる場合もあります。
親告罪の場合には告訴が取り下げられた場合には検察官は公訴提起することができませんので釈放されることになります。また、非親告罪の場合であっても被害者と示談が成立したことで、ある程度被害回復されたとして「行為の違法性が事後的に減少した」と捜査機関が考える場合があります。そのような場合には被疑者に有利な事情として不起訴となったり在宅事件として捜査が進められる可能性もあります。
捜査機関や裁判所に対して釈放を訴える
警察による逮捕の場合には捜査を行い「48時間以内」に検察官に事件を送致します。弁護士はこの48時間の間に警察官に被疑者の身体拘束の必要がないことを訴えていくことができます。具体的には被疑者が犯人でないことが明らかであることや罪を認めて反省していること、逃亡・罪証隠滅のおそれがまったくないことなどを説得的に説明していくことになります。
検察官に送致されて以降は「24時間以内(身体拘束から72時間以内)」に裁判所に勾留請求するか否かを判断します。その期間については弁護士は検察官に対して勾留請求の必要がないことを主張していきます。それでも勾留請求された場合には、裁判官に対して勾留の必要性がないことをアピールし、勾留請求を却下するよう求めていきます。これらにより、早期釈放の実現を目指していきます。
裁判所に対して勾留の異議申立てを行う
裁判官が勾留決定をした場合には、弁護士は異議申し立て(準抗告)を行います。勾留期間中、被疑者に勾留の必要性がないことを裁判所に訴えていくことになります。具体的には上記のように逃亡・罪証隠滅の必要がないことなどを説得的に説明することになります。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|