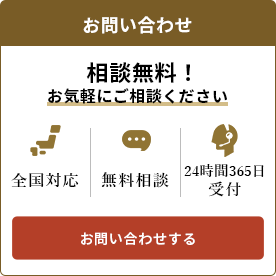書類送検(しょるいそうけん)とは、被疑者が身柄拘束されていない事件(在宅事件)を検察に送致することです。身柄拘束がされていないという点において「逮捕」と異なります。書類送検は、検察官が起訴または不起訴を判断する前段階の手続きに過ぎませんので、書類送検されただけでは前科はつきません。
この記事では、刑事事件に強い弁護士が、
- 書類送検とはどういう意味か
- 書類送検で前科や前歴はつくのか
- 書類送検と逮捕の違い
- 書類送検後に逮捕されることはあるのか
- 書類送検前後の流れ
などについてわかりやすく解説していきます。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
目次
書類送検とは
書類送検とは、被疑者が身柄拘束されていない事件(在宅事件)を検察に送致することです。
刑事事件について、一般的には被疑者を逮捕・勾留した状態で捜査をすすめる「身柄事件」を思い浮かべる方も多いかと思われますが、逮捕の要件が整わない場合や捜査機関の判断で、被疑者の身柄を拘束しない状態で捜査をすすめる「在宅事件」になることもあります。
身柄事件の場合、警察等の第一次捜査機関が、逮捕から48時間以内に被疑者の身柄と書類(書類だけではなく、事件に関連する証拠物も含む)を検察官に送致します。他方で、在宅事件の場合、被疑者の身柄は送致されずに、書類のみが検察官に送致されます。このことから「書類送検」と呼ばれているのです。
この点、書類送検につき「書類送検は逮捕もされないし、書類が検察官に送られてそれで終わりなので、軽くて意味ない処分だ」と勘違いされることもあります。しかし、書類送検を受けて事件が検察に引き継がれた後は、検察官が主体となって取調べ等の捜査を進めます。捜査の結果、逮捕の要件が満たされれば、書類送検の後であっても逮捕されることもありますし、略式起訴や正式起訴をされて略式命令や有罪判決が下ることもあります。
また、書類送検は、ニュースや新聞などで良く用いられていますが、法律に規定のある用語ではありません。書類送検は、被疑者の身体を拘束していないため、書類「だけが」検察官に送致されるということを強調するために用いられているマスコミ用語なのです。書類送検は実務上「書類送致」と言います。
ちなみに、司法警察員(司法巡査より強い権限が認められている警察官)が犯罪捜査をした場合には、原則として事件を検察官に送致しなくてはならないと法(刑事訴訟法第246条)で定められています。ただし、検察官からあらかじめ指定された犯罪事実が極めて軽微な事件は、警察官から被疑者に対する厳重注意、訓戒等で事件を終了させることができます(刑事訴訟法第246条、犯罪捜査規範第198条)。これを「微罪処分」といいます。
書類送検されると前科はつく?前歴は?
書類送検されたことのみで前科が残るということはありません。
前科とは、特定の犯罪によって有罪判決を受けたという事実です。これに対して書類送検とは、在宅事件の事件記録(書類等)が検察官に送られたことを指します。書類送検は、検察官の起訴・不起訴の判断以前の段階であるため、書類送検それ自体によって前科がつくということはありません。あくまでも、書類送検を受けた検察官が事件を起訴し、刑事裁判によって有罪判決を受けた場合に初めて、前科がつくことになります。
なお、前科と似た言葉に前歴というものがあります。
前歴とは、特定の犯罪事件の被疑者として捜査の対象となったという事実のことを指します。そのため、書類送検された場合には特定の事件の被疑者として捜査対象となっていることになるため、前歴は残すことになります。
もっとも、前歴とはあくまで本人が捜査の対象となったことがあるという事実上の履歴にすぎません。また、前歴は警察・検察などの捜査機関のデータベースに記録に記載されていますが、高度に秘匿性が高い個人情報であるため一般人がこれらの情報にアクセスすることできません。
したがって、前歴があるということで何らかの法効果が生じて不利益を受けるということはありません。
書類送検と逮捕について
書類送検と逮捕の違いは?
書類送検と逮捕の違いは、「捜査機関が被疑者の身体を拘束しているかどうか」です。
前述の通り、「書類送検」とは、被疑者の身体拘束を伴わない状態で警察官から検察官に事件記録(書類等)を送ることを指す言葉です。これに対して「逮捕」とは、捜査機関が被疑者の身体を拘束するために行う強制処分のことを指します。
逮捕された場合も、一定の制限時間内(逮捕から48時間以内)に被疑者の身柄と事件記録が検察官に送致されますので、検察官に事件が送致される点では書類送検と逮捕は共通します。ただし、身柄拘束の有無で両者には違いがあります。
また、書類送検は被疑者が身体拘束されていない事件の処理を検察官に移す手続きであるのに対し、逮捕は被疑者の身柄を強制的に拘束する手続きであるという点でも異なります。
書類送検になるか逮捕されるかの分かれ目は?
犯罪を犯した場合に、逮捕されるか在宅事件として書類送検で済むかは、さまざまな事情を考慮して判断されることになります。
個人の身体的な自由を奪う逮捕が認められるためには、一定の条件があります。この条件を満たさない場合には逮捕することは許されないため、在宅事件となります。そして、被疑者を逮捕するためには、逮捕の理由と必要がなければなりません。
逮捕の理由とは、被疑者が特定の罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があることをいいます。つまり、その人が特定の犯罪行為を行った可能性が高いと言えることが必要です。
次に逮捕の必要性については、被疑者が逃亡または罪証隠滅するおそれがあることです。
逮捕が必要か否かについては、以下のような事情を考慮して判断されることになります。
- 犯罪の種類・被害の重大性
- 犯行動機や被害者の状況
- 否認事件か自白事件か など
殺人や強盗、特殊詐欺など重大な犯罪の場合には、逃亡・罪証隠滅のおそれが大きいとして逮捕される可能性が高いでしょう。一方で万引きや取締法規違反の罪などの場合には在宅事件として書類送検になる可能性があります。
しかし、軽微な事件であっても何度も同様な犯罪を繰り返していたり、反省の態度が皆無の場合には悪質性が高いとして逮捕される可能性が高まります。
書類送検後に逮捕されることはある?
書類送検がなされた後に、逮捕されることもあります。
書類送検の結果、被疑者に逮捕の理由と必要があると捜査機関が判断した場合には、捜査機関は裁判所から逮捕状を発布してもらい、被疑者を逮捕することがあります。
そこで、書類送検後も逮捕されないような行動をとることが重要となります。
在宅事件での警察や検察官の呼び出しや取り調べに応じるか否かは任意ですが、そうであるからといって呼び出しを何度も無視したり拒否したりしていると、逃亡のおそれがあるとして逮捕されてしまう可能性が高まります。
捜査機関からの呼び出しは平日の昼間であることが多いため、仕事の都合などでどうしても外せない予定がある場合には日程調整が必要となるでしょう。しかし、何度も出頭を拒否し無視していると逮捕されるうえに心証も悪くなってしまいます。
書類送検前後の流れ
それでは、書類送検される前、書類送検された後はどのような流れになっていくのか、事件の発覚当初から逮捕されないケースの流れをみていきましょう。
- 犯行発覚
- 警察からの出頭要請&取調べ
- 書類送検
- 検察からの出頭要請&取調べ
- 起訴、不起訴
- (起訴された場合)裁判
- 判決(懲役、禁錮など)、命令(罰金、科料)
①犯行発覚
どんな事件でも、捜査機関(以下では警察を念頭に解説します)に犯行が発覚することからスタートします。発覚の端緒は、被害者の被害届・告訴状の提出、職務質問・所持品検査などが多いです。
②警察からの出頭要請&取調べ
警察に事件の被疑者として特定されると、警察から取調べのための出頭要請を受けます。いつ出頭要請を受けるのかはわかりません。突然、電話や手紙で要請を受けます。
要請に応じるか否かは自由ですが、正当な理由なく拒否すると逮捕される可能性もあるため注意が必要です。要請に応じて出頭した場合は取調べを受けます。被疑事実に対する認否、事件の難易度などによって、取調べの時間や回数は異なります。
③書類送検
警察での取調べなどの捜査が終わった後は、事件の証拠書類と証拠物が検察に送致されます。書類送検するかどうか、するとしていつ書類送検するのかは、警察は積極的に教えてくれません。気になる方は取調べ時にでも警察官に尋ねてみるとよいでしょう。
④検察からの出頭要請&取調べ
警察から書類送検された事件を検察が受理した後は、今度は、検察から取調べのための出頭要請を受けます。警察の場合と同様、いつ出頭要請を受けるのかはわからず、突然、電話や手紙で要請を受けます。
要請に応じるか否かは自由ですが、正当な理由なく拒否すると逮捕される可能性もあります。
要請に応じて出頭した場合は取調べを受けます。検察での取調べ時間は警察よりも短く、回数は少なくなる傾向にあります。
⑤起訴、不起訴
検察での取調べを終えた後、検察官が事件を起訴するか不起訴にするか判断します。
検察官は、犯行の態様、被害の結果の大きさ、被疑者の認否・反省の有無、被害弁償・示談の有無、前科・前歴の有無、適切な監督者の有無などの事情を考慮して、起訴か不起訴かを判断します。
不起訴となった場合は、刑事手続きは終了です。
不起訴となった場合は、刑事裁判を受ける必要がなく、刑事裁判を受けないということは懲役、罰金などの刑罰も受けません。
刑罰を受けないということは、前科もつきません。
⑥(起訴された場合)裁判
一方、起訴された場合は裁判を受ける必要があります。
起訴には略式起訴と正式起訴があります。
略式起訴される場合は、検察の取調べ時に、あらかじめ略式裁判を受けることへの同意を求められます。
同意書にサインした後、略式起訴されます。
略式起訴されるタイミングはわかりません。
略式裁判は書面審理で、裁判所に出廷する必要はありません。
裁判官が検察官から提出を受けた書面のみで、「100万円以下の罰金又は科料」の範囲内で略式命令を出します。
正式起訴される場合は略式起訴のような事前の手続きはありません。
正式起訴された場合は、後日、裁判所から起訴状謄本(写し)や弁護士をどうするかを問い合わせる照会書などがご自宅に送達されてきます。
この時点で弁護士を選んでいない方は、私選または国選の弁護士にするのか、あるいは弁護士を選ばないのかの選択をする必要があります。
その後、裁判所から期日を指定されますので、指定された期日に裁判所に出廷して裁判を受けます。
裁判の回数は起訴事実に対する認否や事件の難易度によって異なります。
⑦判決(懲役、禁錮など)、命令(罰金、科料)
裁判官が「罰金〇〇万円」という略式命令を発した後は、裁判所からご自宅に略式命令謄本が届きます。略式命令謄本を受け取った日の翌日から起算して14日間は正式裁判を申し立てる期間です。この期間が経過した後、略式裁判が確定し前科がつきます。罰金(または科料)は、裁判がまだ確定していない上記の14日間でも納付することができます。
正式裁判の場合は、法廷で判決を受けます。判決日の翌日から起算して14日以内が上訴(控訴、上告)期間です。この期間内に上訴せず、期間が経過した場合は裁判が確定し、実刑の場合は収容の手続きが取られ、執行猶予の場合は執行猶予期間がスタートします。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|