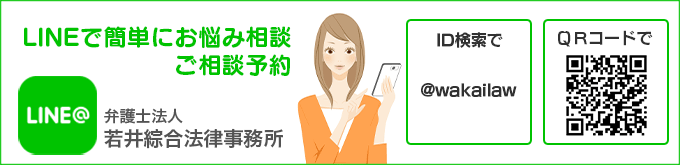離婚しようとする場合、まずは夫婦でいろいろな事柄について話し合いを行うことになります。
- 離婚するかどうか
- 離婚する場合には、慰謝料・財産分与の有無または金額
- 未成年の子供がいる場合には、夫婦どちらが親権者となり子供を引き取るか、毎月の養育費をいくらにするか
……などなど。
裁判外でこれら当事者の話し合いが成立した場合には、離婚届を提出することで離婚が成立します(協議離婚)。
話し合いが成立しない場合には、家庭裁判所で離婚に関する調停を行うことが必要になります。これを離婚調停(「夫婦関係調整調停」)といいます。
しかし、一般の方にとって家庭裁判所は敷居の高いもの。
調停では、どのような流れで、どんな手続きが行われるのか不安に思われる方もたくさんいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、「離婚調停」の手続きの流れと、手続きを自分に有利に進めるために必要となる3つのポイントをご紹介します。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|
離婚調停とは
まずは、離婚調停とは何か、どんな手続きかについて解説します。
離婚調停とは?
離婚調停とは、家庭裁判所の手続きを利用した話し合いにより離婚成立を目指す離婚方法の一つです。別名「夫婦関係調整調停(離婚)」といいます。
話し合いで離婚成立を目指すという点では離婚協議と同じですが、離婚協議は原則夫婦だけで話し合うのに対し、離婚調停は調停委員が夫婦の間に入って話をとりまとめていく点が大きな違いです。
離婚調停では離婚(離婚に合意できるかどうか)のほか、次の離婚条件についても話し合うことができます。
- 親権
- 養育費
- 面会交流
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
- 通知義務
- 禁止事項 など
調停委員が話し合いの結果をとりまとめた調停案に夫婦双方が合意した場合は調停が成立します。一方、夫婦の一方が調停の期日に出席しない、離婚に合意しない、あるいは夫婦の一方、あるいは双方が調停案に合意しない場合は調停は不成立となります。調停が不成立となった場合には、一定期間を置いて再度離婚調停を申し立てるか、離婚裁判を提起するなどして離婚成立を目指します。
離婚調停ではどんなことを聞かれる
先ほど述べたとおり、離婚調停では離婚と離婚条件について話し合います。したがって、調停委員からも離婚と離婚条件について聞かれます。主に聞かれる内容を各項目別にまとめると次にとおりです。
| 離婚 |
|
| 親権 |
|
| 養育費 |
|
| 面会交流 |
|
| 財産分与 |
|
| 慰謝料 |
|
離婚裁判との違いは?
先ほど述べたとおり、離婚調停が不成立に終わった場合は離婚裁判を提起することも検討しなければいけません。ただ、離婚調停と離婚裁判とでは次の点で大きな違いがあります。それぞれにメリット、デメリットがありますので、離婚調停で離婚を成立させるのか、離婚裁判で離婚を成立させるのか迷ったときの参考にしていただければと思います。
話し合いによる手続きかどうか
まず、すでに述べたとおり、離婚調停は相手との話し合いをベースとした合意形成の場であるのに対し、離婚裁判は話し合いではなく、法廷での立証活動をメインとする手続きという点です。このような手続きの性質上、離婚調停では一定の譲歩が必要ですが、離婚裁判ではまずは譲歩せずに自分の主張を貫くことができます。
手続きが厳格かどうか
次に、離婚裁判と比べ離婚調停の手続きは緩やかなのに対し、離婚裁判の手続きは厳格という点です。したがって、法律の素人である一般の方でも離婚調停の手続きを進めていくことができないわけではありません。一方、離婚裁判の手続きはかなり専門的で難しいですから、弁護士に依頼することが多いでしょう。
第三者が間に入るか否か
次に、すべに述べたとおり、離婚調停では夫婦の間に調停委員が入って話をまとめてくれるのに対し、離婚裁判では調停委員のような夫婦の間に入ってくれる第三者はいないという点です。離婚裁判では裁判官が裁判の進行役をつとめますが、あくまで裁判の当事者は原告(訴えた人)と被告です。
裁判所へ行く必要があるかどうか
次に、弁護士に弁護を依頼したとしても、調停が家庭裁判所で開かれる場合は依頼者本人も離婚調停に出席する必要があります。これは、離婚調停で話し合いにより離婚成立を目指す手続きであることから、調停委員が本人から直接話を聞く必要があるからです。一方、離婚裁判では、当事者尋問や和解の手続きなど必要な場合を除き、弁護士が依頼者の代わりに裁判所へ行き、訴訟活動を行います。
離婚調停にかかる時間・期間の目安
離婚調停にかかる時間・期間の目安は次のとおりです。
離婚調停1回にかかる時間・頻度
離婚調停の1回にかかる時間は2時間程度です。ただ、初回は30分程度で終わることもあります。2回目以降は、話し合いの内容などにより、2時間以内に終わることもあれば、2時間以上かかることもあります。
離婚調停は1日に1回開かれ、開かれる時間帯は午前の9時~12時、午後の1時~4時までの間の中で指定されます。離婚調停は1ヵ月に1回程度のペースで開かれます(2ヶ月空くこともあります)。
離婚調停にかかる期間・回数
弊所の経験上、離婚調停の期間は平均して半年程度、離婚調停の回数は2回~8回程度となることが多いと思われます。
令和4年度司法統計によると、令和4年度中の婚姻関係事件(婚姻費用分担調停など離婚調停以外の調停事件を含む)の審理期間と審理回数は次のとおりです。
【審理期間】
| 1月以内 | 3月以内 | 6月以内 | 1年以内 | 2年以内 | 2年超 |
| 3,107 | 12,289 | 17,774 | 16,639 | 6,520 | 733 |
【審理回数】
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6~10 | 11~15 | 16~20 | 21以上 |
| 4,620 | 7,325 | 11,118 | 9,853 | 7,413 | 5,384 | 9,923 | 1,252 | 147 | 27 |
離婚調停の期間について詳しくは、離婚調停にかかる期間は?平均・最長期間と短期終了させるコツをご覧ください。
離婚調停にかかる費用
離婚調停でかかる費用は次のとおりです。
自分で進める場合の費用
離婚調停を申し立てるときは、
- 収入印紙(手数料):申し立て一件につき1,200円分
- 連絡用の郵便切手:1,000円前後(裁判所により異なる)
を家庭裁判所に納める必要があります。離婚調停の申立て費用は、合計で2500円程度と考えておけば良いでしょう。
その他、裁判所までの交通費や夫婦の戸籍謄本(450円)が実費としてかかります。また、ケースによっては不動産登記簿などの取得費用がかかることもあります。
弁護士に依頼した場合の費用
弁護士に離婚調停の弁護活動を依頼した場合は上記の費用のほか弁護士費用がかかります。弁護士費用の内訳や金額等は事務所によって異なりますが、一般的には「着手金」、「報酬金(基礎報酬金、追加報酬金)」、「日当費」、「実費」にわかれます(金額はいずれも税抜き)。
| 着手金 | 着手金は、弁護士と委任契約を締結した(弁護士に弁護活動を依頼した)直後に発生し、弁護士の弁護活動の成果の如何にかかわらず返金されない費用です。20万円~30万円が相場です。 |
| 報酬金 | 調停で離婚問題が解決した場合に発生する費用です。
|
| 日当費 | 日当費とは、弁護士が裁判所に出廷するたびにかかる費用です。
|
| 実費 | 実費とは、弁護士が裁判所へ出廷するための交通費、相手方や裁判所、公的機関などとの文書のやり取りをするための郵送費、訴状に貼付しなければ印紙代(手数料)など、弁護活動によって実際に発生した費用です。弁護活動により変動します。 |
以上からすると、離婚調停のトータル弁護士費用は最低でも50万円程度はかかります。また、離婚調停で合意できた金銭の額が多くなればなるほど「追加報酬金」が高くなりますし、離婚調停が長期化し、弁護士が裁判所に出席する回数が多くなればなるほど日当費が高くなり、トータルの弁護士費用は高くなります。
離婚調停の費用について詳しくは、離婚調停の費用相場は?弁護士に依頼するメリットを解説をご覧になってください。
離婚調停の流れ
家庭裁判所で離婚調停を行う場合、申立人として行うべき手続きの流れは、主につぎのようになります。
- 離婚調停の申立て
- 第1回期日の決定
- 第1回期日の開催
- 第2回以降の期日の開催
- 離婚調停の終了
順を追って、見てみることにしましょう。
①離婚調停の申立て
離婚調停は、離婚しようとしている夫婦のどちらか(夫または妻)が申立てることができます。
離婚調停の申立て先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。調停を行う裁判所に関して当事者に合意がある場合には、その合意のある家庭裁判所でも調停を行うことが可能です。
②第1回期日の決定
調停の申立て後、申立人に対して家庭裁判所から第1回調停期日の日時などの調整のため連絡があります。これによって、第1回目の調停期日(調停が開かれる日)が決まります。
調停期日が決まると、家庭裁判所は調停の当事者双方に「期日呼出状」を送達します。当事者は、呼出状に記載された日時に家庭裁判所を訪れ、調停を行うことになります。
呼出状は、調停の申立てから2週間前後で到着するのが一般的です。第1回目の調停期日は、調停の申立て後1か月前後から2か月くらいの間に開催されることが多くなっています。
③第1回期日の開催
呼出状に書かれた期日に家庭裁判所に到着したら、裁判所の受付に声をかけ、待合室で調停が始まるのを待つことになります。
待合室は夫婦別々となりますので、仮に相手方と顔を合わせたくない事情がある場合でも心配する必要はありません。
しばらく待合室で待機していると、調停室(話し合いをする部屋)に入るよう調停委員から呼び出されます。調停室では、調停委員2人が待機しています。場合によっては、裁判官が同席することもあります。
調停での話し合いは、夫婦が交代して行われるのが原則ですので、待合室だけでなく、調停室でも相手方と顔を合わせる心配がありません。
1回の話し合いにかかる時間は30分前後で、話し合いが終了すると待合室に戻って待機し、相手の話し合いが終了したら2度目の呼び出しを受けて再び調停室で話し合いをします。
夫婦それぞれが2回ほど呼び出されて調停室で話し合いを行いますので、1回の調停でかかる時間はおおよそ2時間程度となります。もちろん、当事者の事情によっては、より長い時間がかかることもあります。
④第2回以降の期日の開催
1回目の調停で話し合いが成立しない場合、第2回目の調停期日が指定されることになります。2回目以降の調停期日は裁判所と当事者の都合を調整し決定されますが、一般的には前の調停期日から1ヵ月ほど後に指定されることが多いです。
2回目以降の調停での話し合いは、基本的に第1回目のものと同様です。しかし、2回目以降の期日では徐々に話し合いをすべき焦点が絞られてきますので、必要に応じて自分に有利な証拠などの提出をすることになります。
離婚調停は、当事者の話し合いの内容によって必要な回数開かれます。
⑤離婚調停の終了
調停での話し合いによって当事者に合意が成立した場合は調停成立となり、当事者に離婚に関する合意が成立する見込みがない場合には調停不成立として調停は終了します。
調停が成立した場合、裁判所によって当事者の合意内容を記載した調停調書が作成されます。調停調書には、離婚の合意や財産分与、慰謝料、養育費など離婚条件に関する当事者の合意内容が調停調書に明記されることになります。
法律上、調停調書には確定判決と同一の法的効力が認められます。このため、万一相手方が約束を守らない場合には調停調書に基づき、相手方の財産に対して強制執行をすることが認められます。具体的には、相手方の給料や預貯金などを差し押さえることができるのです。
一方、調停が不成立となった場合、離婚をするには離婚裁判を提起する必要があります。ただし、稀にですが、調停不成立となった場合に「調停に代わる審判」がなされることがあります。調停に代わる審判とは、たとえば離婚することや離婚の条件について大筋で合意できているという場合に、残りの細かい条件については裁判官が一方的に条件を決めてしまう、という手続きのことです。
調停が不成立となった後について詳しく知りたい方は、離婚調停の不成立でその後どうなる?不成立の割合や弁護士費用を解説をご覧になってください。
離婚調停を有利に進めるポイント
それでは最後に、離婚調停を有利に進めるために必要となる3つのポイントをご紹介します。
- (1)証拠をそろえておく
- (2)主張すべき点は主張する
- (3)譲歩すべき点は譲歩する
それぞれのポイントについて、詳しくご説明いたします。
証拠をそろえておく
離婚調停は、裁判所で行われる手続きです。調停では調停委員の仲介によって、当事者が間接的に話し合いを行うことになります。
調停を有利に導くためには、調停委員に対して自分の主張がいかに説得力のあるものであるか示さなければいけません。
例えば、DVの慰謝料を求めるためには、負傷して通院した場合の医師の診断書や負傷した箇所を撮影した写真などが有力な証拠となり得ます。しかしこういった証拠が一切ないと、相手がしらを切った場合に慰謝料請求が認められなくなってしまいます。
そのため、調停で証拠資料を提示して説得力のある主張ができるよう、調停前から証拠となる資料をコツコツ集めておくことが大切です。
主張すべき点は主張する
離婚調停では、離婚するかどうかという問題だけでなく、離婚条件に関しえても話し合いの対象となります。
慰謝料や財産分与を支払うのかどうか、養育費はいくら払うのか、面会交流の方法や頻度はどうするのか……などなど、離婚調停で話し合うべき項目はたくさんあります。
これら各項目に関しては、調停の前に自分で希望する条件を明確に決めておきましょう。
そして調停の場では、それらをしっかりと主張することが大切です。
譲歩すべき点は譲歩する
調停委員の仲介があるとは言っても、調停は当事者の話し合いであることには変わりがありません。話し合いでは、あまりに自分の希望条件にこだわってしまうと、かえって話し合いがまとまらなくなってしまうものです。
話し合いをできるだけスムーズに進め、なるべく早く調停離婚を成立させるためには、譲れる条件は譲ることが大切です。調停では、柔軟に話し合いを行うことを心がけてください。
なお、離婚調停を有利に進めたい方は、離婚調停で勝つには?勝利のための8個のポイントを徹底解説も合わせて読んでみてください。
裁判上の離婚事由があることを主張する
次に、相手に以下のいずれかの裁判上の離婚事由があるときは、それを主張することです。
- 不貞
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復し難い重度の精神病
- 婚姻を継続し難い重大な事由
確かに、相手に離婚調停では裁判上の離婚事由があることを証明することは求められていいませんが、調停委員は「仮に、調停不成立となった裁判まで手続きが進んだ場合にどういう結果になるか」ということまで視野に入れながら、夫婦の双方から話を聴いています。そこで、調停委員に対し、集めた証拠を使って相手に裁判上の離婚事由があることを主張できれば、相手に対する調停委員の心証は悪くなり(反対に、あなたに対する心証はよくなり)、相手と争っている離婚条件について、有利に取り計らってもらえる可能性があります。また、裁判で争っても勝ち目がない程度にまで証明できれば、調停委員から相手に調停で手続きを終わらせるよう説得してもらうこともできるでしょう。
調停委員を味方につける
次に、調停委員を味方につけることです。
確かに、調停委員は公平・中立な立場をとらなければならないとされていますが、そうはいっても調停委員も一人の人間です。調停委員にいい印象をもたれればあなたの立場に立ってアドバイスしてくれたり、離婚条項を考えてくれる可能性がありますし、反対に悪い印象をもたれれば不利な条件を飲まざるを得なくなる可能性もあります。
調停委員を味方につけるには、指定された日時に調停に出席することはもちろん、服装、装飾品、髪型などの外見、言葉遣いにも注意する必要があります。普段、派手なものやブランド品を身につけている方は調停のときだけはあらためた方がよいかもしれません。裁判所はいわば「神聖な場所」ですので、暴力的な行為に出たり、声を荒げるたりする行為はNGです。
調停委員ときちんとコミュニケーションをとれるよう心がけることも大事です。調停委員に聴かれていることに対して端的に答え、「この人とは会話ができる」と思ってもらうことが大切です
弁護士に依頼する
次に、弁護士に依頼することです。
離婚調停はご自分で進めることもでき、裁判ほど厳格なルールに縛られるわけではありませんが、そうはいっても法律に詳しくない方が自分一人の力で進めるのは大きな負担です。離婚調停が進めば進むほど、長くなればなるほど途中で投げ出したくなる気持ちになり、それが調停の結果として現れるかもしれません。
また、調停で有利な結果を得るためには調停委員を味方につけると同時に、調停委員に自分の主張を冷静に順序だててわかりやすく説明することが求められます。弁護士であれば依頼者から詳しく話を聴いて要望を汲み取り、それを冷静に論理的に調停委員に対し説明することができます。
まとめ
今回は、離婚調停の具体的な流れや、調停を有利に進めるポイントなどをご紹介いたしました。
協議離婚が成立しない場合、日本では大多数のケースで調停の段階で離婚が成立しています。
離婚の条件を少しでも有利にするためには、調停を有利にすすめる必要があります。
しかし、一般的なケースでは、当事者は法律の知識に乏しいのが現状です。
少しでも調停を有利に進めるためには、弁護士に相談・依頼することが大切です。
離婚後の生活は長いものです。
調停で少しでも有利な離婚条件を獲得することは、離婚後の生活にとって非常に大きな影響を与えます。
財産分与や慰謝料、養育費などを少しでも有利にした場合には、当事務所にご相談ください。
当事務所では、全国どちらからのご相談でも24時間無料で承っております。
当事務所は親身・誠実をモットーとしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
| 誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|