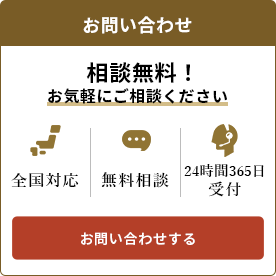夫婦間であっても、盗撮や盗聴は犯罪として処罰される可能性があります。たとえ刑事事件にならなくても、民法上の不法行為として損害賠償責任を問われるおそれがあります。
たとえば、こんな疑問をお持ちではないでしょうか?
- 夫婦の一方が、性行為を盗撮したら犯罪になるのだろうか?
- 離婚に向けた証拠集めとして、盗聴や録音をしても問題ないのか?
夫婦間では、さまざまな事情で「盗撮」や「盗聴」といった行為が行われることがあります。
たとえば、夫が妻の行動を記録しておこうという自己防衛的な動機や、妻が夫の浮気を疑って証拠を得ようとする場合のほか、性的嗜好や好奇心から無断で撮影・録音してしまうケースもあります。
しかし、どのような動機であっても、盗撮や盗聴が法的責任を問われる可能性があることには変わりません。
この記事では、夫婦間での盗撮・盗聴行為が刑事責任・民事責任を問われる場面や、証拠としての扱いについて、裁判例も交えながらわかりやすく解説します。
法律のボーダーラインを正しく理解し、後悔しないための判断材料として、ぜひ最後までお読みください。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
目次
夫婦間の盗撮・盗聴はどちらも犯罪になり得る
夫婦間のプライベートな問題であっても、盗撮や盗聴といった行為は、状況によって刑事責任や民事責任を問われる可能性があります。
当記事では、近年処罰が強化された「盗撮」に加え、見落とされがちな「盗聴・無断録音」のリスクについても、刑事・民事の観点から詳しく解説します。
夫婦間における盗撮行為の法的責任
夫婦間であっても、盗撮は犯罪に該当する可能性があります。配偶者だからといって、無断で撮影しても許されるとは限りません。
2023年7月13日、性的姿態撮影等処罰法が施行され、盗撮に関する撮影罪が新たに規定されました。この日以降の盗撮行為には、原則として撮影罪が適用されます。
参考:撮影罪とは?該当する行為や条例違反との違いをわかりやすく解説
撮影罪は、以下のような方法で人の性的姿態等を撮影した場合に成立します。
- 正当な理由がないのに、ひそかに撮影した場合
- 相手が同意できない状態にある中で撮影した場合
ここでいう「性的姿態等」には、陰部、乳房、臀部、これらの部位を隠す下着(ブラジャーやパンツなど)、および性交等をしている姿態が含まれます。
相手が配偶者だからといって、刑を免除する規定は設けられていません。
このため、たとえば夫が妻を撮影する場合であっても、無断で隠しカメラを設置したり、スマホなどの撮影機器を差し向けるなどして、性的な部位や、夫婦の夜の営みを撮影した場合、撮影罪に問われる可能性があります。
罰則は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。
一方、撮影罪が施行される前の盗撮行為については、各都道府県の迷惑防止条例が適用されます。
東京都など一部自治体では、住居や浴場、更衣室などの私的空間も対象としており、夫が妻を、または妻が夫を盗撮した場合でも条例違反となる可能性があります。
迷惑行為防止条例違反の罰則は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金とされていることが一般的です。
夫婦間における盗聴行為の法的責任
刑事責任を問われるケース
夫婦の一方が、相手に無断で会話を録音・盗聴した場合でも、その手段や方法によっては刑事罰の対象となる可能性があります。
- 住居侵入罪(刑法130条):別居中の住居に無断で立ち入り、録音機を設置した場合など
罰則:3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 - 不正指令電磁的記録供用罪(刑法168条の2):スマホに盗聴アプリを無断で仕込んだ場合など
罰則:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 - 不正アクセス禁止法違反:配偶者のIDやパスワードを使ってGmailやGoogleフォトにアクセスした場合など
罰則:3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(不正アクセス禁止法11条)
参考:人のスマホを勝手に見ると不正アクセス禁止法違反の罪になる?
犯罪にならない場合でもプライバシー侵害で違法になることも
たとえ刑事事件として処罰されない場合でも、盗聴行為が民法上の不法行為(民法709条)に該当する可能性があります。
実際の裁判例では、夫婦間でのICレコーダーによる録音が違法と判断されたケースもあります。
自己防衛のための録音は違法にならない可能性もある
DVやモラハラなどから身を守るために行った録音行為は、違法性が否定される可能性があります。
同意を得ないで録音したデータは証拠になる?
刑事・民事いずれの場面でも、同意のない録音がただちに証拠能力を否定されるわけではありません。
特に、自分が会話に参加している状況で録音を行った場合には、違法収集証拠として排除されるリスクは低くなります。
【東京高裁昭和52年7月15日判決】無断で録音された会話であっても、「録音の手段・方法・態様が社会通念上是認しうる相当なものである限り、違法とはならない」と判断。
【最高裁平成12年7月12日決定】詐欺の被害者が、後日の証拠保全のために相手との会話を無断で録音した行為について、「相手方の同意を得ない録音であっても、違法ではなく、録音テープの証拠能力は否定されない」と判断。
夫婦間の盗撮・盗聴は民事上の責任を負うことも
夫婦間での盗撮や盗聴の行為は、民法上の不法行為に該当し、損害賠償責任が生じる可能性があります。民法709条では、不法行為によって他人に損害を与えた場合、加害者が損害賠償責任を負うと規定されています。
相手が妻や夫といった配偶者だからといってこの責任を免除する規定は設けられていません。
もっとも、刑事責任も民事責任も、配偶者が責任追及する意思表示を示さない限りは追及されることはありません。配偶者が責任を追及するかどうかは、配偶者との関係性にもよるでしょう。
なお、盗撮や盗聴が発覚すると、夫婦関係が悪化し、離婚に発展するリスクもあります。裁判で争われた場合、こうした行為が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断されれば、離婚が認められる可能性もあります。
まとめ
夫婦間であっても、無断での盗撮や盗聴は刑事上の犯罪となる可能性があり、民事上の責任も問われることがあります。
「証拠を残すためだった」と主張しても、行き過ぎた手段であれば、かえって自らが責任を問われるおそれがある点に注意が必要です。
配偶者に被害届を出された場合、逮捕や損害賠償請求といった重大な問題に発展するリスクもあり、決して軽視できません。
夫婦間の問題として捜査機関が慎重に対応し、あえて立件しないケースも考えられます。ただし、状況によっては厳正に対処される可能性もあるため、安易に考えるべきではありません。
もし夫婦間の盗撮・盗聴トラブルに巻き込まれた場合は、早めに弁護士に相談し、適切な対応を取ることをおすすめします。
当事務所では、夫婦間の盗撮や盗聴に関する法的トラブルの解決、刑事責任の回避など、幅広い対応が可能です。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|