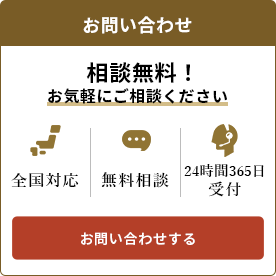盗撮で刑事裁判にかけられた場合、どんな判決が下されるのか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。実刑になる可能性はあるのか、執行猶予がつく場合もあるのか、といった疑問が浮かぶことでしょう。
このような不安や疑問を抱えている方に向けて、本記事では、盗撮事件に強い弁護士が次のポイントについて詳しく解説します。
- 盗撮で実刑になりやすいケースとは?
- 盗撮の初犯でも実刑になることはあるのか?
- 盗撮で実刑判決が出た後、どのような流れになるのか?
- 執行猶予がつく可能性は?
なお、ご家族が盗撮事件で逮捕されており、懲役実刑を回避するために早急に対応したいとお考えの方は、この記事を読まれた上で、全国無料相談の弁護士までご相談ください。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
目次
盗撮で問われる罪と罰則
盗撮で問われる可能性のある罪と罰則は以下のとおりです。
撮影罪
まずは、撮影罪です。
撮影罪は性的姿態撮影等処罰法とう法律に規定されている罪です。撮影罪では、女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れて下着や身体の一部を撮影するなどのいわゆる盗撮行為のほか、
- 被害者が拒否できないような状態にさせ、あるいはそのような状態にあることを利用して被害者の身体等を撮影する行為
- 被害者に性的なものではない、特定の者以外の者にみられることはないと信じ込ませる、あるいはそう信じていることを利用して被害者の身体等を撮影する行為
など、盗撮行為以外の行為も処罰対象とされており、それゆえに「盗撮罪」ではなく「撮影罪」と規定されているのです。性的姿態撮影等処罰法は令和5年(2023年)7月13日に施行されていますので、同日以降に行った上記の行為には撮影罪が適用されます。
撮影罪の罰則は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。女性のスカートにスマートフォンを差し向けたものの身体等を撮影することができなかったなどの未遂も処罰の対象とされています。
【合わせて読みたい】撮影罪とは?該当する行為や条例違反との違いをわかりやすく解説
迷惑防止条例違反
次に、迷惑防止条例違反です。
迷惑防止条例は各都道府県が定める条例であり、条例の中で盗撮行為を処罰する規定が設けられています。多くの都道府県では、「公共の場所」だけでなく、住居・事務所・更衣室・浴場などの私的な空間での盗撮行為も処罰の対象としています。
性的姿態撮影等処罰法が施行されるまでの盗撮行為にはこの条例が適用されます。時効は盗撮したときから3年です。
罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習の場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
住居侵入罪、建造物侵入罪
次に、住居侵入罪、建造物侵入罪です。
住居侵入罪とは、正当な理由がないのに他人の住居に無断で立ち入った場合、建造物侵入罪とは、正当な理由がないのに他人の建造物に無断で立ち入った場合に問われる罪です。住居には家の敷地(庭)も含まれます。したがって、入浴中の身体を盗撮しようと思って他人の家の敷地に立ち入った場合は住居侵入罪に問われます。また、建造物には、トイレ、更衣室など建物を構成しているある一室も含まれます。したがって、盗撮目的で異性のトイレに立ち入った場合には建造物侵入罪に問われます。
両罪の罰則は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
盗撮で実刑になりやすいケースは?
盗撮で実刑になりやすいケースとは以下のようなケースです。
- ①盗撮の前科がある
- ②執行猶予期間中に盗撮した
- ③複数の余罪を立件・起訴された
- ④犯行が悪質
①盗撮の前科がある
まず、盗撮の前科を持っている場合です。
以前に盗撮で刑に処されていながら再び盗撮をしたということは、以前の刑では反省せず、更生していないことの証でもあります。したがって、本人に反省を促し、更生させるためにはより重たい刑を科す必要があるとの判断になりやすいといえます。もっとも、実刑を科すにあたってどこまで前科が重要視されるのかは、前科の内容、数、前科がついた年度にもよります。たとえば、盗撮の前科で執行猶予期間中に盗撮を繰り返した場合はほぼ間違いなく実刑になるでしょう。一方、前科が盗撮ではなく窃盗の前科である場合は初犯と同様に扱われる可能性もあります。また、過去、5年以内に盗撮の前科を1つ持っているよりかは、複数持っている方が実刑となる可能性は高くあります。
②執行猶予期間中に盗撮した
次に、執行猶予期間中に盗撮をした場合です。
執行猶予とは本来、刑務所に収容されるべき事案であるところ、諸般の事情から社会内での更生の機会を与えられているということになります。にもかかわらず、その期間内に再び罪を犯したということは、自ら社会内で更生する機会を放棄したということにほかなりません。したがって、執行猶予期間中に盗撮した場合は実刑となる可能性が極めて高くなります。今回犯した罪で実刑となれば、執行猶予も取り消され、その罪についても服役しなければなりません。なお、執行猶予期間中に罪を犯しても再度の執行猶予を受けることもできないわけではありませんが、再度の執行猶予を受けるには以下の厳しい要件をクリアする必要があります。
【再度の執行猶予を受けるための要件】
- 前回の執行猶予付き判決に保護観察がついていないこと
- 今回の受ける懲役の長さが1年以下であること
- 情状に「特に」酌量すべきものがあること
【合わせて読みたい】再度の執行猶予とは?条文や要件、獲得確率を解説
③複数の余罪を立件・起訴された
次に、複数の余罪があり、かつ、立件・起訴された場合です。
余罪が複数認められる場合、常習性がある→盗撮にのめり込んでいる→社会内での更生が難しいと判断され、実刑となる可能性もないとはいえません。前科がある場合はもちろん、初犯の場合でも実刑の可能性はないとはいえないでしょう。もっとも、これまで盗撮を繰り返してきた証拠を残していたとしても、実際に立件・起訴まで行きつくのはそのうちの一部に限られます。残された証拠から盗撮の日時・場所、被害者等の事実を特定することは難しいからです。仮に余罪で立件・起訴されてもはじめは執行猶予がつくことも十分に考えられます。
【合わせて読みたい】盗撮は余罪捜査で立件される?初犯の場合は?弁護士が解説
④犯行が悪質
次に、犯行が悪質な場合です。
盗撮が用意周到に行われていた、執拗的だった、盗撮した動画をネット上にアップして拡散させた、盗撮した動画で収益をあげていたなどという場合は不利な情状としてくみ取られる可能性があります。
盗撮の初犯でも実刑になることはある?
では、盗撮が初犯だった場合、いきなり実刑になることはあるのでしょうか?
盗撮は不起訴になりやすい犯罪
まず、盗撮が初犯の場合、通常は軽い処分で終わることが多いです。軽い処分とは、略式起訴または不起訴のいずれかです。
略式起訴とは、簡易な手続きで行われる起訴のことで、裁判所が書面審理のみで罰金を命じるものです。罰金を納付すれば、刑務所に収容されることはありません。
一方、不起訴とは、文字通り起訴されない処分のことを指します。不起訴になれば裁判を受ける必要はなく、刑罰も科されません。また、前科もつかないため、略式起訴よりもさらに軽い処分といえます。
なお、略式起訴か不起訴かの判断を大きく左右するのは示談成立の有無です。処分を受ける前に示談が成立した場合には不起訴となる可能性が高くなります。
初犯でも実刑になりやすいケースは?
では、盗撮が初犯でも懲役実刑となる可能性があるのは、どのようなケースなのでしょうか?具体的には、次のような事情が認められる場合です。
- 犯行が用意周到・計画的
- 執拗に盗撮を繰り返しているなど悪質
- 常習性が認められる
- 盗撮、性犯罪関連の前歴がある
- 犯行を否認している
- 反省の態度がみられない
- 被害者の処罰感情が厳しい
- 示談が成立していない
- 被害弁償ができていない
- 社会復帰後の適切な監督者がいない
更生の可能性が低い、または再犯のリスクが高いと判断された場合、実刑となる可能性が高まります。
盗撮で実刑判決となった後の流れ
刑事裁判で「被告人を懲役〇〇年に処する」という実刑判決を受けた場合、その後の手続きはどのように進むのでしょうか。ここでは、在宅事件・身柄事件・保釈中のケースに分けて説明します。
在宅事件で実刑判決を受けた場合
在宅事件として起訴され、実刑判決を受けた場合でも、直ちに刑務所に収容されるわけではありません。実刑判決を受けた後、その日の翌日から14日間は控訴できる期間が保障されています。この期間内に控訴した場合、事件は高等裁判所に引き継がれ、控訴審での審理が開始されます。高等裁判所で審理中は刑務所に収容されることはありません。
一方、控訴しなかった場合、または控訴を取り下げた場合は、判決が確定し、刑の執行手続きが開始されます。このように、実刑判決を受けただけで直ちに刑務所に収容されるわけではなく、判決が確定して初めて収容に向けた手続きが取られます。
具体的には、検察庁から呼出状が送付され、指定された日時に出頭するよう求められます。そして、検察庁へ出頭すると、必要な手続きを経た後、検察庁の職員に同行され、刑務所へ移送されます。
なお、呼び出しに応じず出頭しない場合は、収容状が発付されます。収容状が発付されると、警察や検察の職員が自宅などに訪れ、強制的に身柄を拘束されることになります。
身柄事件で実刑判決を受けた場合
逮捕・勾留された状態で起訴され、身柄拘束下で裁判を受けた場合、実刑判決が言い渡されると引き続き拘置所に収容されたままとなります。判決確定までは、引き続き未決拘禁者(確定前の被収容者)として拘置所に留め置かれます。
控訴しない場合、または控訴が棄却された場合、14日後に判決が確定し、刑の執行が開始されます。その後、受刑者として刑務所へ移送され、刑に服することになります。
保釈中に実刑判決を受けた場合
起訴後に保釈されていた被告人が実刑判決を受けた場合、判決の言い渡しと同時に保釈の効力が失われます。そのため、法廷で直ちに身柄を拘束され、拘置所へ移送されます。
その後、控訴しなければ14日後に判決が確定し、刑務所へ収監されます。控訴した場合は、控訴審の審理が終了するまで拘置所での身柄拘束が続きます。
盗撮で実刑判決以外の可能性は?
盗撮事件を起こした場合でも、必ずしも実刑判決を受けるとは限りません。事件の内容や状況によって、以下のような処分となる可能性があります。
- ①罰金刑の可能性
- ②執行猶予の可能性
- ③無罪の可能性
ここでは、それぞれのケースについて詳しく説明します。
①罰金刑となる可能性
盗撮事件では、初犯で悪質性が低い場合、罰金刑が科される可能性が高いといえます。罰金刑は懲役刑と同じ刑罰の一種であり、裁判が確定すると前科がつきます。 ただし、懲役刑とは異なり、身体拘束を受けることなく事件が終結するため、比較的軽い刑罰とされています。
罰金刑が科されるかどうかは、以下の事情によって判断されます。
- 初犯である
- 計画的ではなく、衝動的に行われた
- 被害者と示談が成立している
- 被害者の処罰感情がそれほど強くない
- 深く反省し、再発防止の意志を示している
また、盗撮事件では「略式手続」により罰金刑が科されることが多いのも特徴です。略式手続では、裁判所に出頭せず、書面のみで審理が行われ、速やかに罰金刑が確定します。迅速に事件が終結する反面、有罪判決と同じ扱いとなるため前科がつきます。 また、罰金を納付しない場合は「労役場留置」となり、一定期間身体拘束を受ける可能性があります。
一方、罰金刑では済まない可能性が高いケースもあります。
- 前科や余罪がある
- 計画的・常習的な盗撮で悪質性が高い
- 被害者の処罰感情が強く、示談が成立していない
- 裁判で罪を否認し続けている
このような場合、正式裁判となり、懲役刑が科される可能性が高くなります。初犯であっても必ず罰金刑で済むとは限らないため、慎重な対応が求められます。
②執行猶予がつく可能性
盗撮事件で執行猶予がつくかどうかは、法律上の条件を満たし、さらに情状に酌むべき事情があるかどうかによって判断されます。執行猶予付き判決を受けると前科はつくものの、刑務所に収容されず、一定期間(1~5年)新たな犯罪を犯さずに過ごせば、刑の執行が免除されます。 そのため、刑の執行を受けることなく社会復帰することが可能です。
執行猶予が認められるには、次の条件を満たす必要があります。
- 過去に禁錮以上の刑を受けていない、または刑の執行を終えて5年以上が経過していること。
→懲役刑は禁錮以上にあたるため、過去に懲役刑や禁錮刑を受けた場合、執行終了から5年以内なら執行猶予は認められません。 - 今回の刑が3年以下の懲役または禁錮であること。
→3年を超える懲役刑が言い渡された場合は執行猶予は適用されません。盗撮事件では1年未満の懲役刑となることが多く、この条件を満たしやすいといえます。
これらの条件を満たし、さらに情状に酌むべき事情がある場合には、執行猶予がつく可能性が高くなります。たとえば、以下のような事情が考慮されます。
- 初犯であること
- 被害者との示談が成立していること
- 被害弁償を行い、被害者が処罰感情を示していないこと
- 深く反省しており、再発防止に向けた取り組みをしていること(例:治療・カウンセリングを受けるなど)
- 家族や職場の上司など、適切な監督者がいること
- 社会復帰後の生活基盤が安定していること
一方で、過去に盗撮で逮捕されたことがある場合や、初犯でも余罪が多数判明している場合、示談が成立していない場合、計画的で悪質性が高い場合は、執行猶予が認められにくくなります。 また、裁判で罪を否認し続けたり、反省の態度が見られない場合も、実刑判決となる可能性が高くなります。
このように、執行猶予がつくかどうかは、法律上の条件を満たしているかに加え、情状に酌むべき事情がどの程度あるかによって判断されます。
③無罪になる可能性
盗撮事件で無罪が認められるには、盗撮の事実がなかった、誤認逮捕であった、または証拠が不十分で盗撮行為を立証できないことが必要です。さらに、違法な捜査で得られた証拠が排除されれば、無罪となる可能性があります。しかし、日本の刑事裁判における有罪率は99%以上とされ、裁判で無罪判決を得るのは極めて困難です。
そのため、起訴されると無罪を争うのは難しく、示談を成立させて不起訴処分を目指す方が現実的な解決策となることが多いです。早期解決のためにも、弁護士に相談し適切な対応を取ることが重要です。
一方で、無罪が認められた場合は前科がつかず、身柄を拘束されていた場合は国に補償金を請求できます。補償額は1日あたり1000円~1万2500円とされ、裁判費用の補償も求めることが可能です。
盗撮事件で実刑を回避するには?
盗撮で実刑を回避するには以下の対応をとることが考えられます。
- ①示談を成立させる
- ②盗撮したことを素直に認める
- ③社会内での更生可能性があることを示す
- ④盗撮事件に強い弁護士に依頼する
①示談を成立させる
まず、盗撮の被害者と示談交渉し示談を成立させることが考えられます。
通常示談交渉では、示談金の支払いを条件に被害届を取り下げてもらうことに合意してもらうよう被害者に働きかけていきます。そして、仮に示談が成立し、示談金を支払った場合には被害届が取り下げられます。検察官が被害届が取り下げられた事件を起訴する可能性は低いですから、検察官が起訴する前に示談を成立させることができれば不起訴となる可能性が高いでしょう。また、起訴される前に示談を成立させることができず裁判中に示談を成立させた場合にも、そのことが判決では有利な事情として考慮され、執行猶予や罰金となる可能性があります。
②盗撮したことを素直に認める
次に、盗撮したことを素直に認めることです。
もちろん、冤罪と考えている場合は無理に認める必要はありません。一方で、盗撮したことが明らかな場合や、本当は盗撮をした認識があるのにあえて否認している場合に盗撮したことを否認し続けていると、反省していない→再犯の可能性があると判断され、実刑となる可能性を高める結果となってしまいます。盗撮した認識があるのであれば、素直に罪を認め、盗撮を繰り返さないためには今後どうしたらいいのかという点に頭を切り替えた方がよいでしょう。なお、示談交渉するにあたっては盗撮したことを認め、被害者に謝罪することが前提となります。被害者が盗撮したことを否認していることを知れば、被害者の処罰感情はますます悪化し、示談交渉を始めることすら困難となる場合がありますので注意が必要です。
③社会内での更生可能性があることを示す
次に、社会内での更生可能性があることを示すことです。
社会内での更生可能性がないと判断されると、刑務所内で更生してもらうしかないと判断され実刑となる可能性が高くなります。したがって、刑務所内ではなく社会内で更生できることを裁判官にいかにアピールできるかが実刑を回避する上でポイントとなります。社会内での更生可能性があることを示す事情としては、
- 家族などの周囲の理解、協力が得られていること
- 盗撮治療専門の病院に定期的に通える状況にあること(実際に通っていること)
などが考えられます。
④盗撮事件に強い弁護士に依頼する
最後に、盗撮事件を専門に取り扱っている弁護士に依頼することです。
被害者と示談交渉するにも、反省していること、更生可能性があることを裁判で効果的にアピールするにも弁護士の協力が不可欠です。また、同じ弁護士でも、盗撮事件に不慣れな弁護士よりも、何度も取扱い実績のある弁護士に依頼した方が不安なく依頼することができますし、個別具体的事情に応じた効果的なアドバイスを受けることができるでしょう。
まとめ
盗撮で検挙された場合、撮影罪等に問われる可能性があります。撮影罪の罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。初犯だと罰金あるいは不起訴で終わる可能性があります。一方、直近に盗撮の前科がある場合などは懲役実刑となる可能性もあります。実刑を避け、不起訴あるいは執行猶予を獲得するには被害者との示談交渉等が有効な手段ですが、実現するには弁護士のサポートが必要です。実刑を回避したい方ははやめに弁護士にご相談ください。
当事務所では、盗撮事件に関する不起訴、執行猶予の獲得実績が豊富にあります。親身かつ誠実に弁護士が依頼者を全力でまもりますので、盗撮事件で実刑を回避したいとお考えの方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|